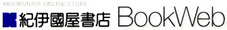しあわせな会社 社員みんなが「オーナー」になるコーオウンド・ビジネスの世界
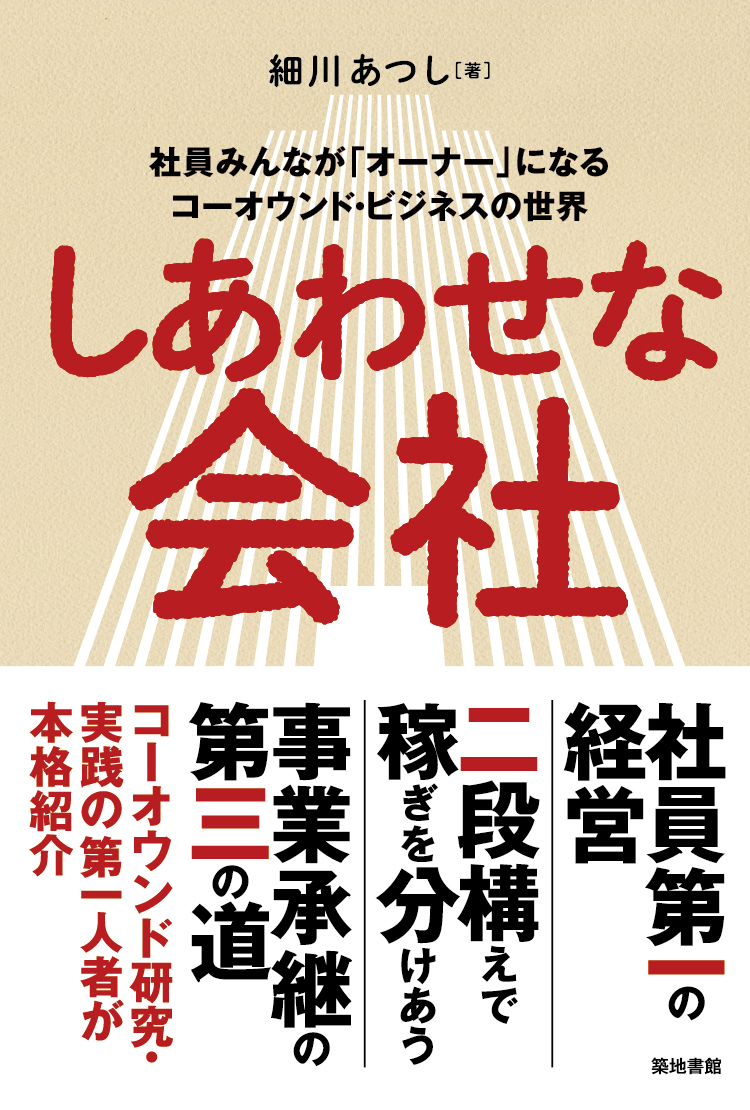
| 細川あつし[著] 2,400円+税 四六判並製 280頁 2025年5月刊行 ISBN978-4-8067-1684-6 事業承継、ビジネスモデル、業務参画、 プロフィット・シェアとパワハラ・モラハラのない融和的経営――― 事業環境の変化で、確かな潮流になりつつあるビジネスモデルを、 コーオウンド研究の第一人者が本格紹介。 |
著者紹介
目次
プロローグ しあわせな会社 わかちあいの資本主義
ネット書店で購入する