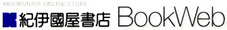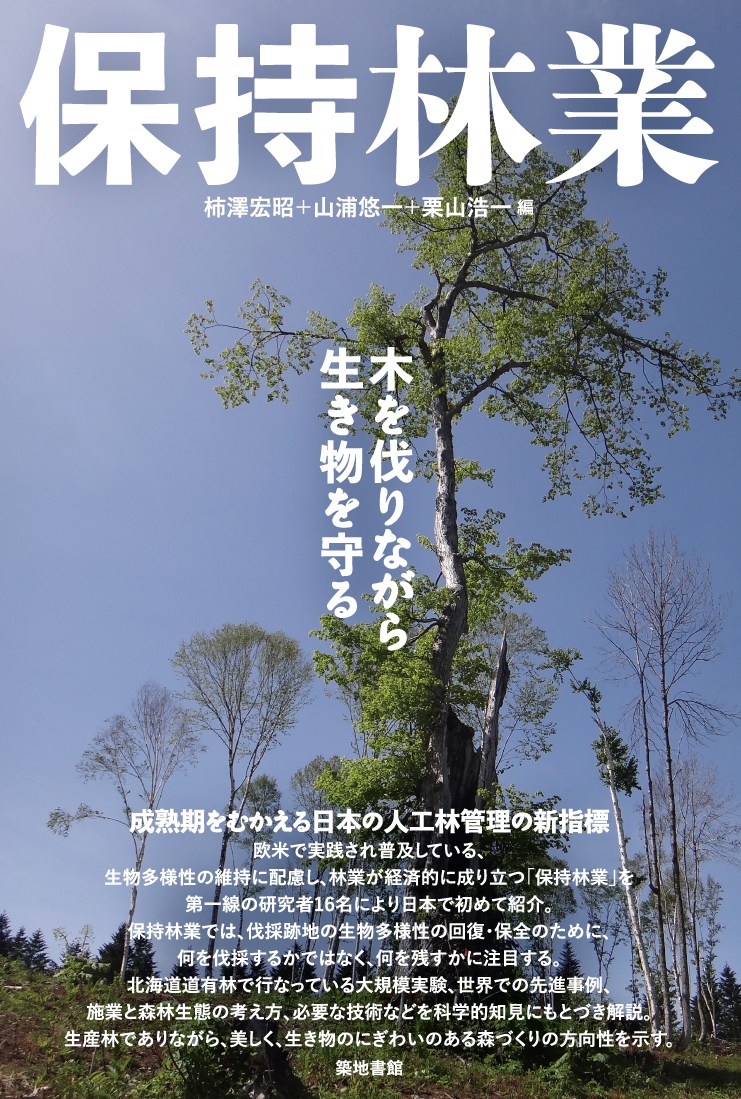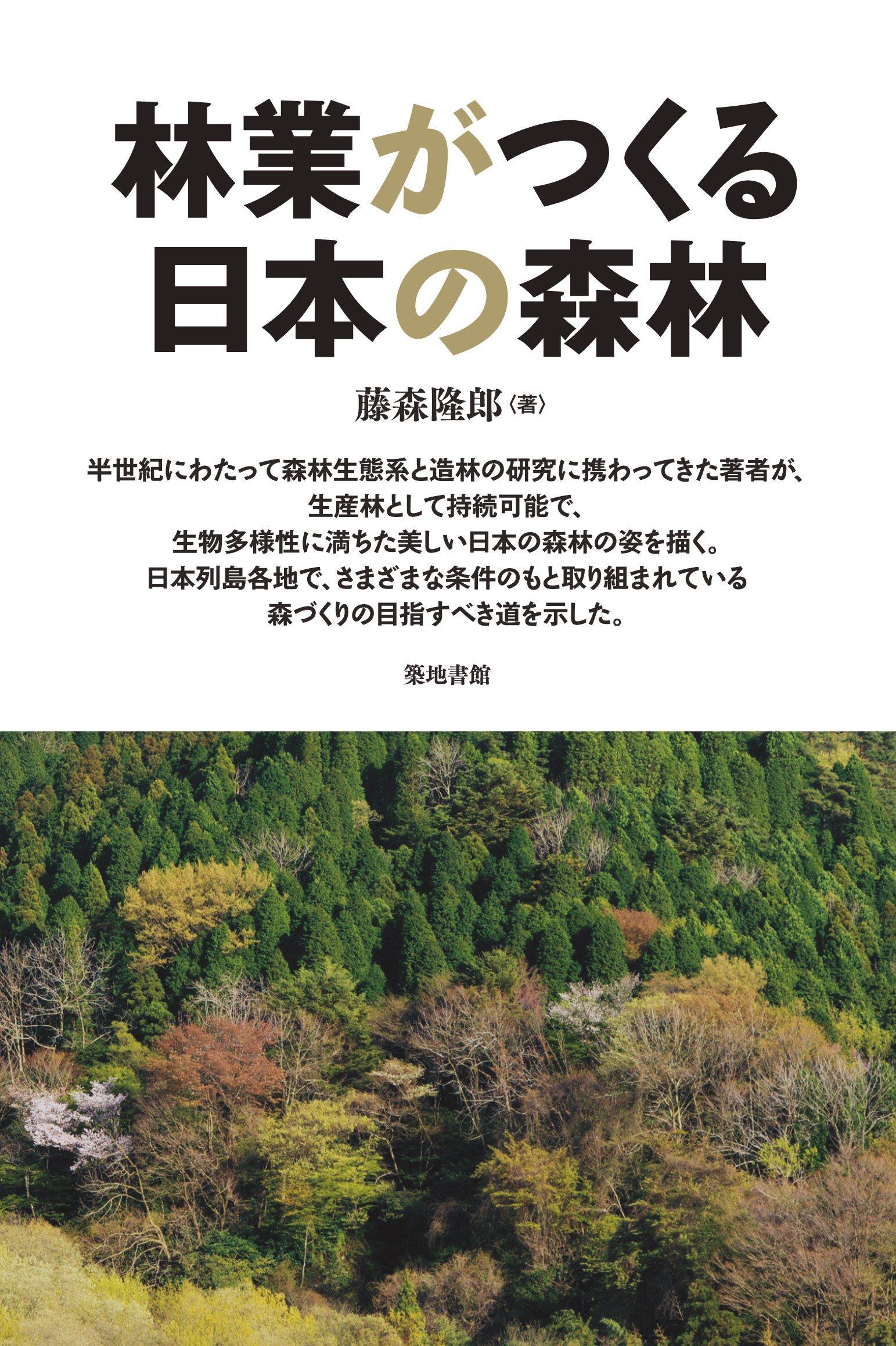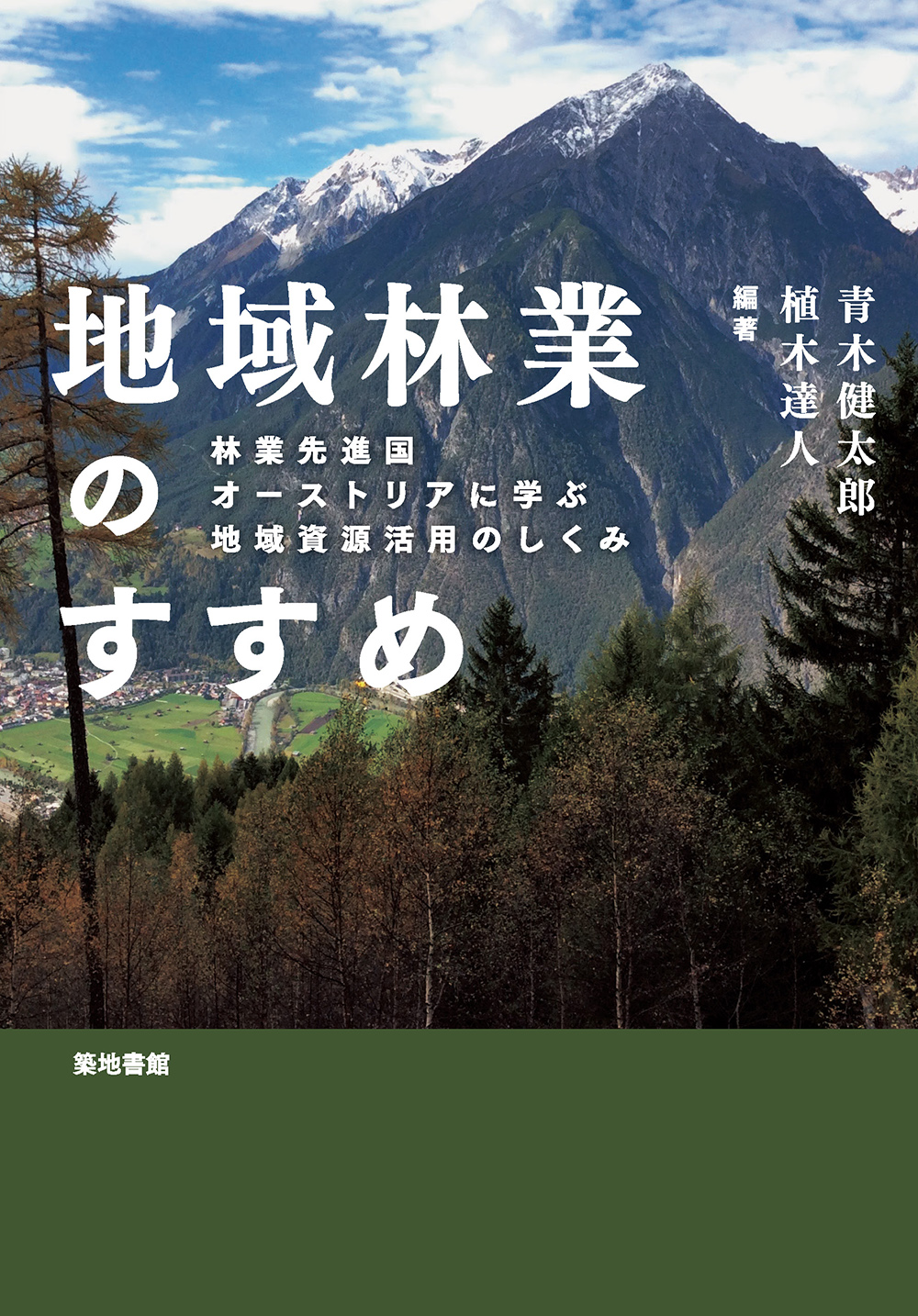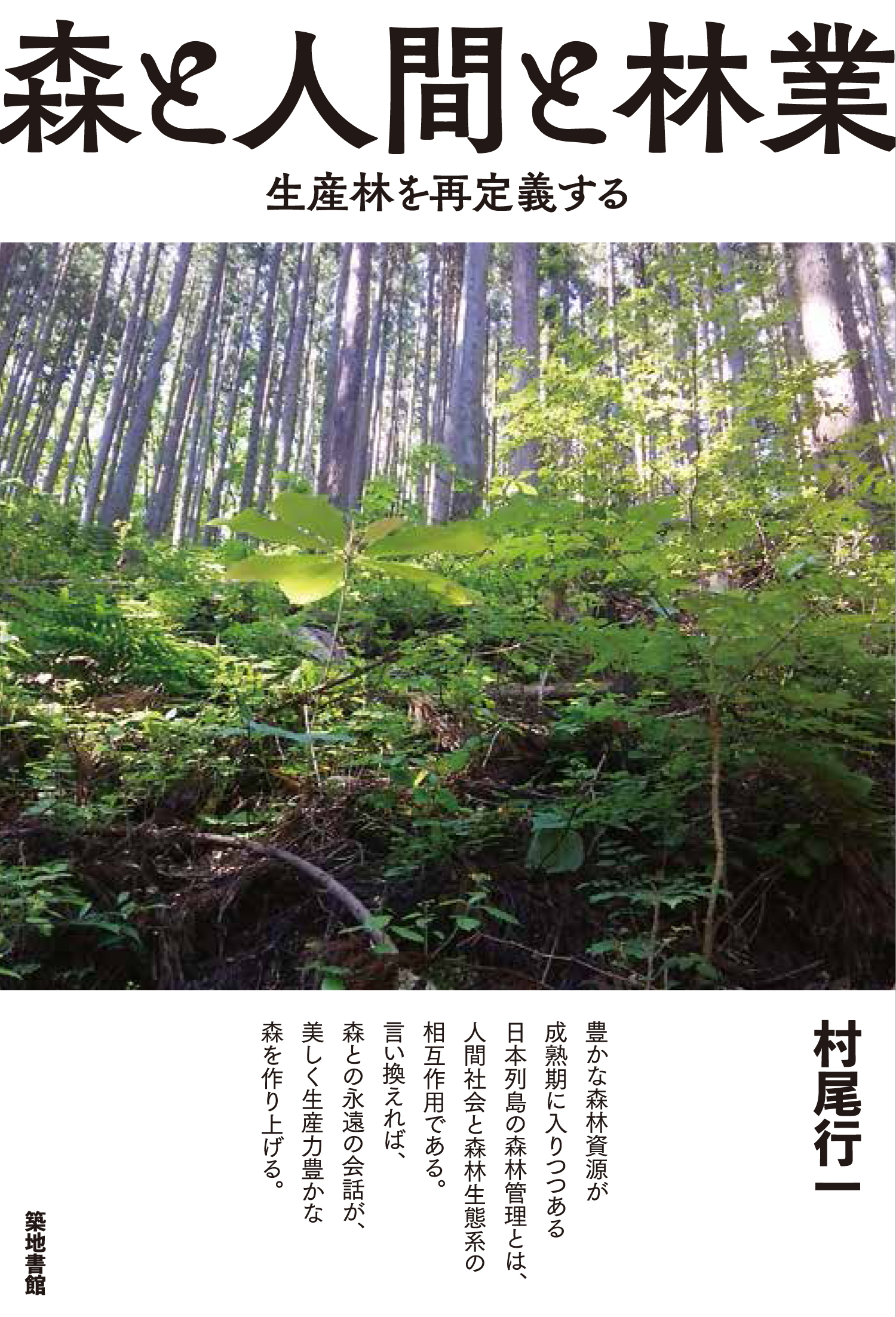���؎����E�ێ��ы� �L�t�����c���Đ����������
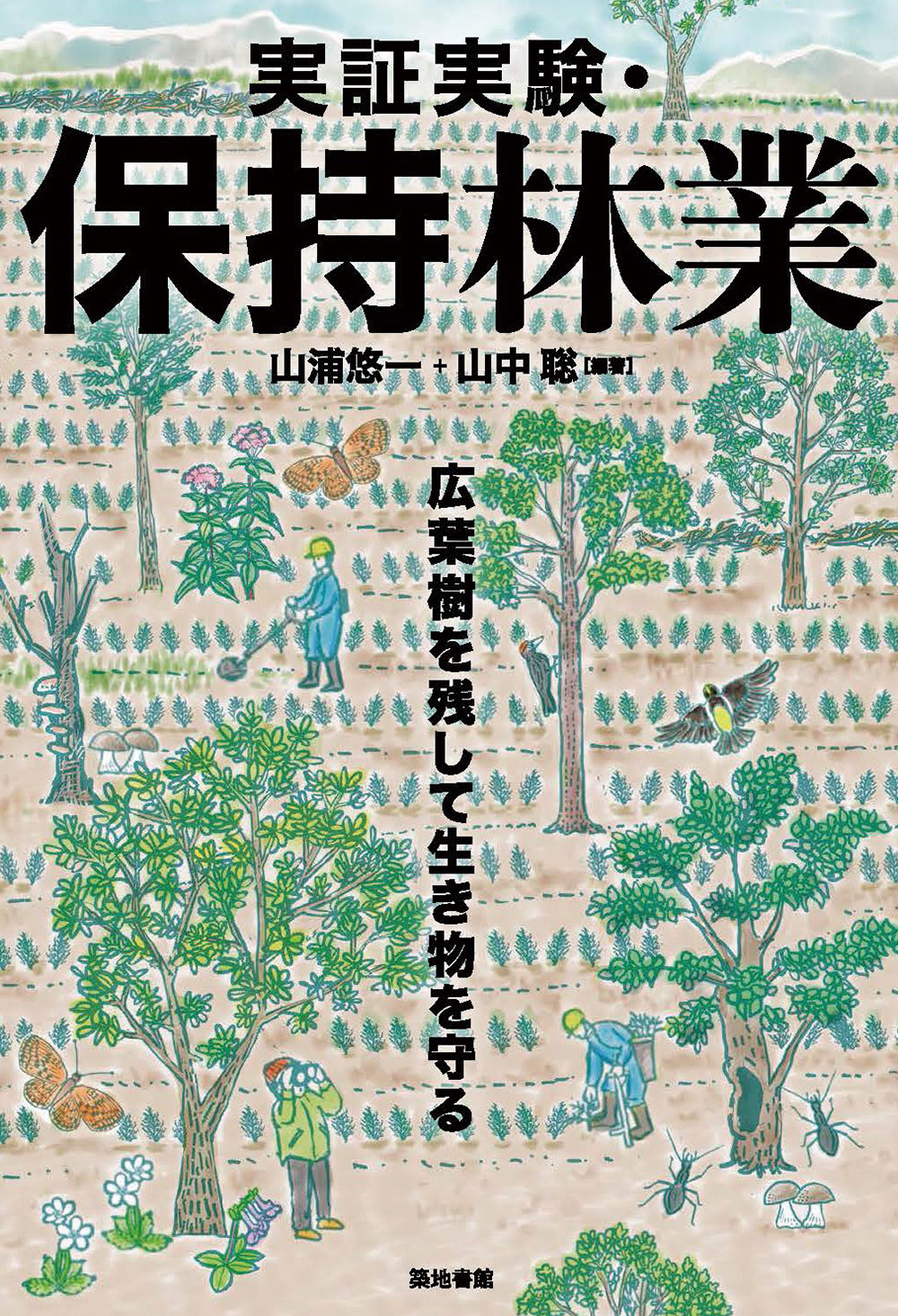
| �R�Y�I��{�R�����m�Ғ��n 2,500�~+�Ł@�l�Z�������@240�Œ�@2025�N6�����s�@ISBN978-4-8067-1686-0 �P��̗ѕ����Ŗ؍ސ��Y�Ɛ������l���ۑS�̗�����ڎw���A �k�C���L�т̃g�h�}�c�l�H��160�w�N�^�[���ŁA �ێ��т̑�K�͎��؎������s����12�N�B ��A�̐��ʂ��A�����ҁA�ыƎ��Ƒ́A��ƁA�s���̒S���҂������Љ�B |
�R�Y�I���i��܂���E�䂤�����j
���������J���@�l�X�ь����E�����@�\�X�ё����������l���x���@��C�������@���m�i�_�w�j
����w�Ⓦ����w�A���쌧�E���A�k�C����w�Ȃǂ��o�Č��E�B
20�N�ȏ�ɂ킽��A�X�т̐������l���̕ۑS�ɂ��Č����B
���L�тɂ�����ێ��ыƎ��؎����̔��Ď҂̈�l�ł���A�������m���̒�Ă��Ė{���̕ҏW�����ӂ����B
2018�N�ɏo�ł��ꂽ�O�������Ў�Ɏ���Ă������������B
�R���@���i��܂Ȃ��E���Ƃ��j
���������J���@�l�X�ь����E�����@�\�X�ё����������k�C���x���@��C�������@���m�i�_�w�j
�k�C����w��w�@�_�w�@���m����ے��C���A����w�@�|�X�h�N���������o�Č��E�B
��Ȍ����e�[�}�͐������l���ۑS�ƗыƊ����𗼗����邽�߂̐X�ъǗ���@�̊J���B
���茤���i�������E�����j
���������J���@�l�X�ь����E�����@�\�X�ё����������k�C���x���@���ΐE���@���m�i�_�w�j
�����_�H��w��w�@�_�w�����ȏC���A�_�ѐ��Y�ȗыƎ�����i���݂̐X�ё����������j�A
�X�ё��������������f�B���N�^�[�i�������l���E�X�є�Q�S���j���o�Č��E�B
��Ȍ����e�[�}�͐X�т̐������l���ۑS�ƊQ���Ǘ��B��Ȓ����́w�X�тƍ����@�X�щȊw�V���[�Y�X�x�i���ҁA�����o�Łj�A
"Galling Arthropods and Their Associates: Ecology and Evolution"�i���ҁASpringer-Verlag�j�ȂǁB
���ΐM�A�i�������E�̂ԂЂ�j
�k�C�������������@�\�ыƎ�����@�ی��c�����@���m�i���w�j
���s��w��w�@���w�����ȏC�m�ے��C���A�k�C�����ыƎ�����i���k�C�������������@�\�ыƎ�����j�ɂ����āA
�X�тɂ�����V�J���ыƂƐ������l���ۑS�̗����Ɍ����������������s���Ă���B
��Ȓ����́w�V�J�̋��ЂƐX�̖������V�J��ɂ��A���ۑS�̗L�����ƌ��E�x�i���S���M�A���ꑍ���o�Łj�A
�w���{�̃V�J�������������̌Q�̉Ȋw�ƊǗ��x�i���S���M�A������w�o�ʼn�j�ȂǁB
�_��@���i����́E������j
�k�C�������������@�\�ыƎ�����@�����劲
�k�C����w��w�@�_�w�����ȏC�m�ے��C���A�k�C�����ыƎ�����i���k�C�������������@�\�ыƎ�����j�ɂ����āA
���і̖�l�Y�~��Q���ыƂƐ������l���ۑS�i��ɒ��ށj�̗����Ɍ��������������ɏ]���B
�����J�[���i�����E���������j
���������J���@�l�X�ь����E�����@�\�X�ё����������k�C���x���@��C�������@���m�i�_�w�j
�k�C����w��w�@�_�w�����@���m����ے��C���A�]����w�Z�i�؍��j�E�O�d��w�E�t�����_��w�i�A�����J�j�|�X�h�N�������A
�X�ё����������{����C���������o�Č��E�B��Ȍ����e�[�}�͐A���̍��ɋ�������������̑��l�������B
��Ȓ����́w�ۍ��̐��E���ۂƐA���̂����Ă�����Ȃ��W�x�i���S���M�A�z�n���فj�B
�͑��a�m�i����ނ�E�����Ђ�j
���������J���@�l�X�ь����E�����@�\�X�ё����������k�C���x���@�������@���m�i�_�w�j
�k�C����w��w�@�_�w�@���m�ے��C���A�X�ё����������쐶���������̈�C���t���������o�Č��E�B
���{�S���ɍL���鑽�l�ȐX�ѐ��Ԍn�ɕ��L���S�������A
�l�H�тɂ�����쐶�����̌����I�ȕۑS��̗��Ă�ڎw���Č������Ă���B
�D���ȃt�B�[���h�͐�R�i�R�X�L�[�j�A��̐X�i���^�J�A�t�N���E�ނ̒����j�B
�ߔN�̒���́u�l�H�тł��������l���̕ۑS�����A�͎���E�唰�E�L�t���ێ��̌��ʁv�i�X�тƗыƁj�ȂǁB
�ԍ����i���������E�����݁j
�k�C��������w�@�\�эL�{�Y��w�@�y�����@���m�i�_�w�j
�k�C����w��w�@�_�w�����@���m����ے��C���A�k�C��������w�@�\�эL�{�Y��w�������o�Č��E�B
�������l���ۑS�Ɛl�̍K���̗����ɊS�������������s���Ă���B
���ɔ_�ыƂȂǐl�̐��Ƃɑ���쐶�����̖����ɂ��Ă̌����ɏ]�����Ă���B
���a���i�������́E�����̂�j
�x��ыƊ�����Ё@�
�k�C����w�_�w���ъw�ȑ��B
�`�@�a���i�ł�ۂ��E������j
�x��ыƊ�����Ё@���Y����
�k�C���〈��_�ƍ����w�Z�X�щȊw�ȑ��B��ɔ��̕�����B
������F�i���Ƃ��E�܂��Ђ��j
�x��ыƊ�����Ё@�X�ѐ�������
�k�C���〈��_�ƍ����w�Z�X�щȊw�ȑ��B��ɑ��ѕ�����B
���ݕq�s�i�݂˂����E�Ƃ��䂫�j
�k�C�����Y�і����X�ъC�m���Ǔ��L�щہ@�ے��⍲�i���L�ѐ����j
�����_�Ƒ�w�_�w���ъw�ȑ��ƌ�A�k�C�����ɓ����B
����܂łɓ��L�тɊւ���Ɩ���20�N�A�і��s����9�N�o�������̂��A�ߘa6�N4����茻�E�B
���L�т̌���ł́A��ɓV�R�тȂǂ̔��̎��Ƃ⓹�L�эނ̔̔��Ɩ��A
�і��s���ł́A���Y�؍ނ�؎��o�C�I�}�X�̕��y�Ɩ��ɏ]���B
���X�@�~�i��������E�����j
�O�䕨�Y�t�H���X�g������Ё@�Ɩ��{���Ɩ�����
����w�_�w���_�ѐ��Y�w�ȑ��ƌ�A�O�䕨�Y�ыƊ�����Ёi���O�䕨�Y�t�H���X�g������Ёj�ɓ��ЁB
�эL�R�ю������A����R�ю������A���c�R�ю��������A�k�C�����̊e�������Ζ����o�Č��E�B
�P�˔����i���ƁE�݂ӂ݁j
���m��w��w�@�����l�Ԏ��R�Ȋw�����ȁ@���m�ے��O�N�@�C�m�i���w�j
���m��w��w�@�����l�Ԏ��R�Ȋw�����ȏC�m�ے��C���B
��Ȍ����e�[�}�́A���ɌŒ����Đ��炷��ۊǑ������A���̕��z�E�푽�l�����K�肷��v���̉𖾁A
�l�דI�����Ɉˑ����Đ��炷�鑐�����A���̐��ԓI�����ƌ����v���Z�X�Ƃ̊W�̉𖾂ȂǁB
�x�c�����i�Ƃ݂��E���j
���m��w�_�ъC�m�Ȋw���@�����@���m�i���Ȋw�j
��^�M���ނ̐��ԓI�e���ɋ����������Č������Ă���B
�w������́A�k�C���m�������ŃZ�~�̗c�����̂邽�߂Ƀq�O�}���n�ʂ��@��N�������Ƃ��A
�y�����̐����ɂǂ̂悤�ɉe�����邩���������Ă����B
���݂͎l���ŕێ��ыƂ�쐶�����ɂ��b�Q��̌����Ɏ��g��ł���B
�͂��߂�
��1���@���_
��1�́@�Ȃ����A�ێ��ыƂ��H�c�c�R�Y�I��
�v���������̃n���M��
�ێ��ыƂƂ�
�l�H�тƐ������l��
���R�ی��̖����Ƃ��̌��E
�ی�����芪���}�g���b�N�X�̏d�v��
���E�̐l�H�ьo�c�͊��ۑS�^��
�{���̍\��
�k�C���ł̑�K�͎��؎���
�Ȃ��ێ��ыƂ��H
���\�N����v���`���Ȃ���A���c��
��2���@��K�͎����̐���
��2�́@�ێ��ыƂ̖؍ސ��Y���c�c���茤��
�͂��߂�
���̂Ƃ�
���̂̌o��
�ێ��ыƂ̔��̌o��
�������ʂ���l�����邱��
������
��3�́@�ێ��̐��c�c�c���ΐM�A�E�_��@��
�͂��߂�
�ێ��ؒ���
�ێ��̎��S��
���̂ɑ�����킲�Ƃ̔����̈Ⴂ
�C��ɍ��E�����ێ��̐��c
������
��4�́@���w�A���c�c���ΐM�A
�͂��߂�
�������@
���̑O�̐A���Ɛl�H�т̊Ǘ��̉e��
���̌�̎�g���̕ω��ƕێ��ыƂ̌���
������
��5�́@�O���ۍ��ہc�c�����J�[��
�͂��߂�
�O���ۍ� ���X�т��x����ۂƂ̋���
�������@ ���k�C���̑�K�͎��؎���
�Q��ێ���̌��� ���p�b�`�����̗т̑��l��
�P�ؕێ���̌��� ���L�t���ێ��̎���ɍ��ꂽ�Ɠ��ȌQ�W
�l�@ �������Ă����ۂ̉����p�^�[��
������ �����l���ɔz�������̎c�����́H
��6�́@�n�\���b���c�c�R���@��
�͂��߂�
�������@
���؎������番����������
�I�T���V�E�S�~���V�ނ̉���
�����H���V�f���V�E�����ނ̉���
������
��7�́@�R�E�����c�c�͑��a�m�E�ԍ���
�͂��߂�
�R�E�����ɂƂ��Ă̐X��
�X�тɂƂ��ẴR�E����
�������@
�ӊO�ɂ����C����l�H��
�F���̉e���A�L�t���ێ��̌���
������
��8�́@���ށc�c�R�Y�I��E�_��@��
�͂��߂�
�y�n�̐ߖ�vs���L
�������@
�ώ@���ꂽ����
���̑O�̍L�t���̖���
�e�����̌���
���̌�̍L�t���̖���
������
�R�����P�@�|�c���Ǝc���ꂽ�Ǘ��ʼnc������N�}�Q���c�c�_��@��
�R�����Q�@���^�J�����̂Ŏ��J�ڏ�����c�c�͑��a�m
��3���@�����̂Ƃ�܂Ƃ߂ƐU��Ԃ�
��9�́@���؎�����10�N�Ԃ̐��ʂ��܂Ƃ߂āc�c���茤��
�͂��߂�
���E�ōs���Ă���ێ��ы�
���ʂ̂Ƃ�܂Ƃ�
�������l���ۑS
���̒n�̕��i�I���l�i�ی��x�{�@�\�j
�@�\�Ԃ̔�r
�l�H�тɓK�����ێ��ы�
����ێ�����̂�
�ǂꂭ�炢�ێ�����̂�
�ǂ̂悤�ɕێ�����̂�
������
��10�́@�ێ��ыƂ�����ō�Ƃ��āc�c���a���E�`�@�a��E������F
�͂��߂�
���̍�Ƃɂ���
���̌�̕ۈ��Ƃ┰�̒n�̗l�q
������
��11�́@���L�тŕێ��ыƂ����H���āc�c���ݕq�s
�͂��߂�
���L�тɂ���
�ێ��ыƂ̓����Ɏ������o�܂ɂ���
�����n�̐ݒ�E���p�ɂ���
�������ʂ̊��p�Ɍ�����
��4���@�ێ��ыƂ̎��H
��12�́@�k�C���̎ЗL�тŕێ��ыƂ����H���āc�c���X�@�~
�͂��߂�
���g�o��
�Έ�R�т̑���
�h�C�c�̐X�уR���T���^���g���K
�A�C�k�����ۑS�Ƃ��Ă̎��g��
����ł̋�J�A����̎��g��
������
��13�́@���m���̃X�M�E�q�m�L�l�H�тŕێ��ыƂɎ��g��Łc�c�P�˔����E�x�c�����E�R�Y�I��
�͂��߂� ���{�B�ȓ�̐l�H�тł̕ێ��ыƂ̎��،����̕K�v��
�唰��̗ђn�ŕێ����ꂽ�L�t���̎���E�{��
�X�M�E�q�m�L�l�H�тɂ�����ێ��ыƂ����ޑ��l���ɗ^����e��v
������ ���W�]
��5���@����Ɍ�����
��14�́@�ێ��ыƂ̉ۑ�ƓW�]�c�c�R�Y�I��
2024�N6��28���A�X�g�b�N�z����
���{�ł����ł���
�u�L�t�����͕K�������e�ՂɎc���Ȃ��v
�ێ��ыƂ͖��\��ł͂Ȃ�
�I�[�v���E�N�G�X�`����
���|���X�N
�{�Ǝw�j
�J���ЊQ�̖h�~
���낻�뎟�̃X�e�b�v��
������
�p����
����
�j�t���l�H�т̂���ۂɍL�t�����c���ێ��ыƂ́A���{�Ő��܂ꂽ�X�ъǗ��̐V���ȃA�v���[�`�ł���B
2011�N9��29���A�ێ��ыƂɊւ���_�������Q���Ėk�C�����̓��L�щۂ�K�ꂽ���Ƃ����ׂĂ̎n�܂肾�����B���Q���������́A�l�H�тɂ����鐶�����l���ۑS�̏d�v�������������g�̕��́i�R�Y 2011�j��A�J�i�_��X�E�F�[�f���̕ێ��ыƂ��Љ�����茤�ꎁ��X�͎��̓��{��_���������i�X 2009�A���� 2011�j�B�O���w�ێ��ыƄ���Ȃ��琶���������x�i�`�V�ق� 2018�j�̑�T�͂ŋL�����悤�ɁA���L�щۂŘb���Ă��ꂽ�y���������͓����̃V���o��i�k�C����w�_�w���X�щȊw�Ȃ̓�����j���������߂Ă���A�����߂Ă����k�C����w�_�w���X�ѐ��Ԍn�Ǘ��w�������i�y�������ݐЂ��Ă��������͐X�ю{�ƌv��w�������j�̑��Ɛ��ŁA�O�サ�Ċ猩�m��̊ԕ��ƂȂ����B
���ꂩ��c�_���o�āA�������͓��L�т̃g�h�}�c�l�H�тŕێ��ыƂ̑�K�͎��؎������s�����ƂɂȂ����B�����ł͘Z�ʂ�̕��@�Ől�H�т̂��A�������@�łق�3�̗ѕ��i���Ԃ�j�̂����B�e�ѕ��̖ʐς͕���7�E0�w�N�^�[���A���̂��Ȃ��ΏƋ���܂߂�Ɨѕ�23�A���v�ʐ�161�w�N�^�[���Ƃ����A�����ő勉�̑�K�͎����ł���B�ڎw�����̂́A�P��̗ѕ����ł̖؍ސ��Y�Ɛ������l���ۑS�̗����ł���B���Ɏ������͒n�ʂ�n���������A���Ȃ킿�ыƐ��Y��L���ȏꏊ�Ŏ������s���A���Y�u���^�̐������l���ۑS��ڎw�����B���݁A���{�Ŗ؍ނ͎�ɐj�t���l�H�сi�j�t���̕c��A���Ďd���Ă�ꂽ�X�сj���琶�Y����Ă���A�F���i�����j�Ƃ����Ă��ׂĂ̎��̂��Ė؍ނ����n����A�ĂђP�����̐j�t���̕c���A������B���Ȃ킿�����������A�������l���ɖR�����l�H�т��Đ��Y����Ă���B�������͕ێ��ыƂ�l�H�тŎ��{���邱�Ƃɂ���āA�X�сE�ыƁE�؍ނ̎Љ�I���l�̌����ڎw�����̂ł���B
�ێ��ыƂ�1980�N�ォ�牢�ĂŒ�āE���{����Ă����B���Ăł͗ыƎ��킪���R�ɒ蒅�E�����i�V�R�X�V�j���邱�Ƃ������A�ی�тƐ��Y�т̊ԂŎ���\�����ގ����Ă���B���������{�ł́A��������≠���ȐA���Ƃ̋������田�̌�ɓ��l�̓V�R�X�V�����҂���͓̂���A��Ԃ������ĕc��A����K�v������i�O���̑�V�͂ŏڏq����Ă���j�B���̂悤�ɓ��{�ł́A���Y�т͐j�t����A���đ��������l�H�тŁA�L�t������̂Ƃ����ی�̑ΏۂƂȂ�V�R�тƂ͎���̑g�����傫���قȂ�B���������l�H�тōL�t�����c���\���̑g���ɏd�_��u���Ă���̂��A�������̕ێ��ыƂ̑傫�ȓ����ł���B����ɂ��A�l�H�ю{�ƂŎ�����X�т̖{���̗v�f�Y�ѓ��ŕ����I�Ɏ��߂��B
����A�l�H�т͋ߔN���E�I�Ɋg�債�A����ɔ����������l���̗����O����A�l�H�ѓ��ł̐������l���ۑS���c�_�����悤�ɂȂ����B�����ĉ��т⊦�тł͐j�t������v�ȐA�͎���ł���B���������āA�j�t���l�H�тōL�t�����c���ێ��ыƂ͓��{�����łȂ��A���E�I�ɂ�������̓Ǝ�����Ӌ`������ƍl����ꂽ�B
�{���̓A�W�A���̕ێ��ыƂ̑�K�͎��؎�����12�N�Ԃ̐��ʂ����܂Ƃ߁A�������l���ۑS�Ɩ؍ސ��Y�̗�������������V�����X�ъǗ���@�𐢂ɖ₤���̂ł���B��P�͂͐l�H�тŕێ��ыƂɒ��ڂ��闝�R�ɂ��Đ������A�����f�U�C�����������B��Q?�X�͂ł͎��؎����̑���ɂ킽�錤���̐��ʂ��Ȍ��Ɏ������B���̌�̑�10?12�͂ł́A���ۂɕێ��ыƂ�����Ő����������ыƎ��Ƒ̂�����Ɋւ�������L�щۂ̊��z�〈���A���łɕێ��ыƂ����{���Ă����ыƉ�Ђ̎��g�݂��Љ���B����ɑ�13�͂ł͍��m���ł̕ێ��ыƂ̐V���Ȏ��H�ɂ��Ă����グ��B�Ō�̑�14�͂ł͂����܂��ĕێ��ыƂ̍���̓W�]���q�ׂ�B
���̈ӌ���l���͑�P�͂��14�͂ŃX�y�[�X�������ċL���Ă���B�͂��߂ɂ͂��낻��I���Ė{���Ɉڂ肽���Ǝv���B�{�����ێ��ыƂ̉��l���L���`���A�X�ъǗ��̖����ɐV���ȓ��������ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ�S�������Ă���B
�R�Y�I��@���ҁE�Ҏ҂��\����