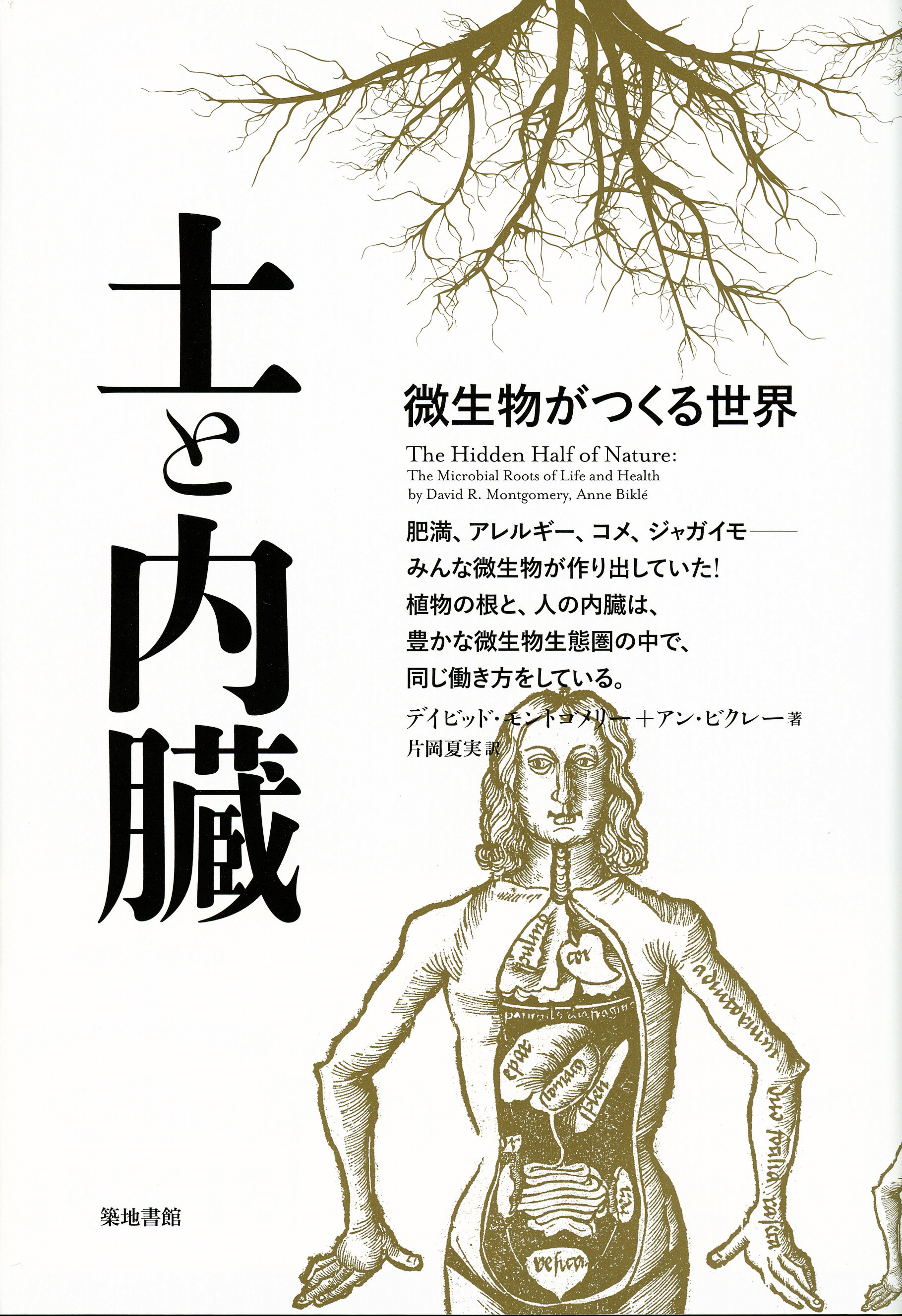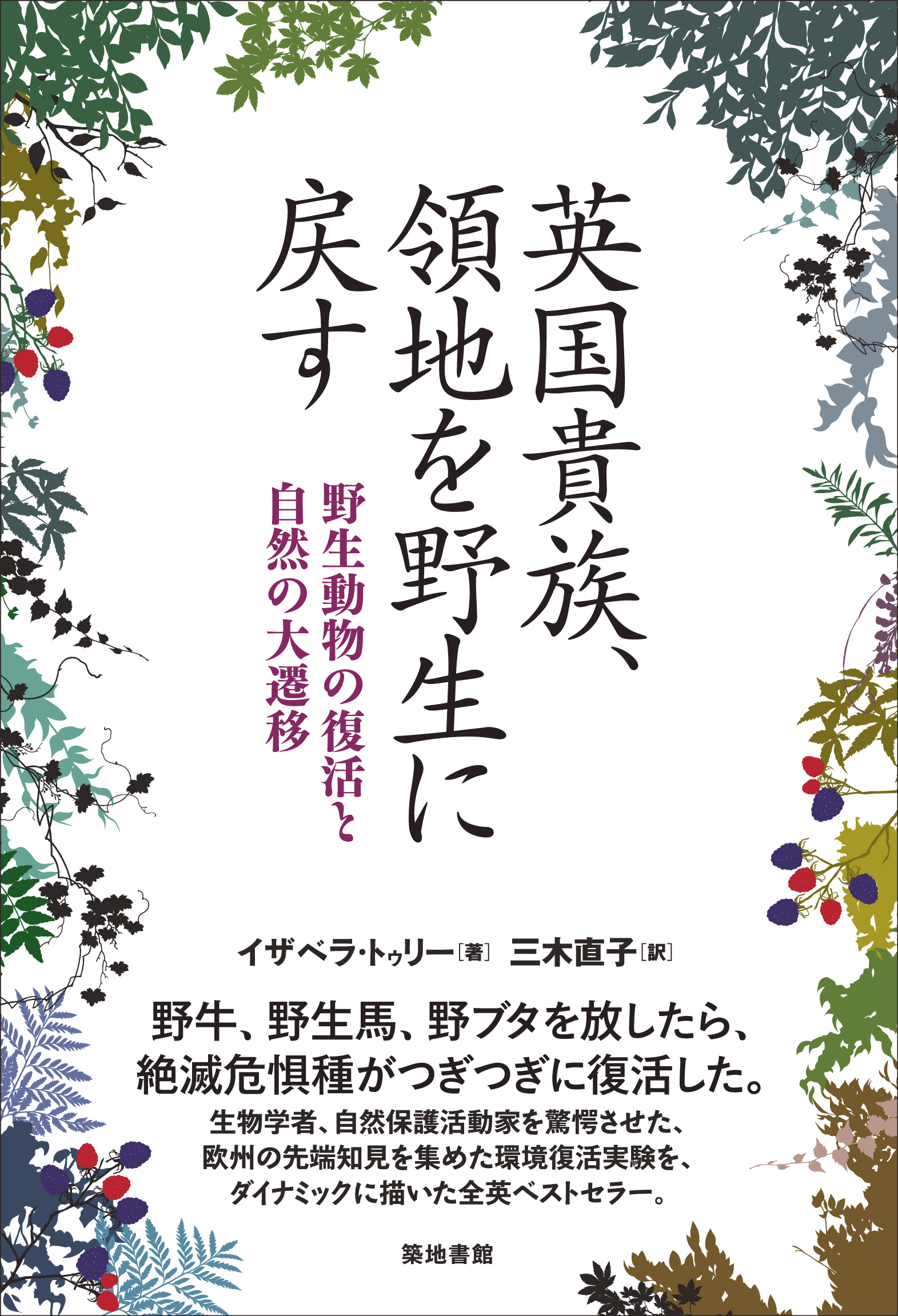互恵で栄える生物界 利己主義と競争の進化論を超えて

| クリスティン・オールソン[著] 西田美緒子[訳] 2,900円+税 四六判上製 324頁+カラー口絵8頁 2024年10月刊行予定 ISBN:978-4-8067-1670-9 ダーウィン進化論以降、適者生存、競争に勝ったものが生き残るとされてきた。 しかし、土壌微生物、植物、昆虫など、生物同士がいかに緊密に協力しあっているかが、 近年の研究で次々と明らかになっていく。 自然への理解と関わりを深め、 行動を起こした各地の研究者、農場主、牧場主、市民たちを訪ね歩き、 生物界に隠された「互恵」をめぐる冒険を描く、驚きと希望のリポート。 アウトドアウェアメーカーパタゴニア書籍部門、 パタゴニア・ブックスで刊行された 話題の本の翻訳書です。 パタゴニアWEBショップでも購入できます! こちらをクリック |
クリスティン・オールソン(Kristin Ohlson)
オレゴン州在住のライター、作家。
『Discover』誌ほかさまざまな媒体に記事やエッセイが掲載されている。
土壌微生物と植物の共生関係から農業・牧畜の将来を鮮やかに描いた
『The Soil Will Save Us』(2014 年)は大きな反響を呼んだ。
西田美緒子(にしだ・みおこ)
翻訳家。津田塾大学英文学科卒業。
訳書に、『FBI 捜査官が教える「しぐさ」の心理学』『動物になって生きてみた』『世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え』(以上、河出書房新社)、
『細菌が世界を支配する』『プリンストン大学教授が教える" 数字" に強くなるレッスン14』(以上、白揚社)、
『心を操る寄生生物』『猫はこうして地球を征服した』(以上、インターシフト)、
『第6の大絶滅は起こるのか』『月の科学と人間の歴史』『太陽の支配』(以上、築地書館)ほか多数。
はじめに─私たちはダーウィンの洞察を誤ったやり方で世界にあてはめていないだろうか
楽観的でいる以外に選択肢はない
植物と土壌微生物の互いに生命を与え合うパートナーシップ
科学は人間が自然からの収穫の限度を理解する道具
第1章 地面の下にある「ギブ・アンド・テイク」のタペストリー
森林生態学者スザンヌ・シマードと「マザーツリー・プロジェクト」
皆伐して一種類のみの苗木で森を作ることへの違和感
菌根菌のネットワークが森林にもたらす意味とは
私たちはまだ十分詳しく調べきれていないだけ
サーモンが森にもたらす恵み
ポプラと根粒菌
次に生きる共同体にDNAをもたらすすべてのもの─森の記憶を記録する
第2章 もっとよい隠喩(メタファー)が必要
「ごまかす」生き物たち
不可解な相利共生
社会情勢と科学
無政府主義者にしてすぐれた生物学者でもあったクロポトキン
利己主義と闘争の生物界
穏やかな選択がもたらすもの
第3章 私たち一人ひとりが生態系
大気中に漂う微生物
多種多様な細菌
すべての生き物は微生物叢の宿主
臨機応変に振る舞う微生物
自然とのつながり
土と健康
第4章 砂漠を湿地に変える
アメリカ西部を水で潤す
瀕死の川
持続可能な放牧
ビーバーの復活
タッグを組んだ牧場主と役人と科学者
第5章 自然を育てる農業
昆虫学者、農業研究に乗りだす
土壌炭素と微生物
環境再生型農業と科学者
化学的混乱から環境再生へ
積み上がる成功事例
土地に適した種子の消失
参加型育種と農場主
スイートコーンをめぐる攻防
第6章 鳥たちと一緒にコーヒーを
生態学者と有機栽培コーヒー農園
土地の共用か、それとも節約か
コーヒー農法集約化の影響
3番目の役者
害虫予防の原則
森林農業と野生生物
第7章 尾根の頂上から岩礁までを癒やす
ミッドコースト流域協議会の歩み
サーモン復活への道のり
ネズミとサンゴ礁
サンゴと藻類と魚と鳥
第8章 青々とした街で暮らす
厳しい気候と屋上緑化
バイオフィリック・シティーズ
シンガポールの取り組み
わずかな草木でも効果を発揮
都市に水路を取り戻す
環境教育の格差をなくす
個人の庭から自然に優しく
ニューヨーク緑化プロジェクト
都市で進化する動物たち
再び、ビーバー登場
半寄生植物が少しだけ許せない
謝辞
訳者あとがき
索引
もう何年も前になるが、私はオハイオ州クリーブランドのマレーヒルに近い画廊で、数人の男性と多くの女性が集まったグループに加わったことがある。その日の夕方、ジャーナリング(訳注/頭に浮かんだ考えや思いを言葉にして書き出すこと)をしてそれぞれが感想を述べながら、楽しくおしゃべりをする会が予定されていたからだ。
私はもともと引っ込み思案だし、当時は今よりもっとその傾向が強く、どうして出席することになったのかはまったく思い出せない。その集まりの詳しいことも、ほとんど覚えていない─レゴブロックを並べたようなレンガ敷きの外の通りはいつものように氷で滑りやすくなっていたのか、家ではまだ小さかった子どもたちが私の帰りを待っていたのか、どうにも思い出せないのだ。
ところが、進行係の言葉に従ったある場面だけは、今でもまだ鮮明に私の記憶に焼きついている。参加者全員が膝をつきあわせて床に座っていると、進行係の女性が私たちに向かって、まず部屋全体を見回して目についた青いものすべてを記憶するようにと言った。青いものはたくさんあったから、私は大急ぎで見つけては、ひとつずつしっかり頭に刻み込んだ。それから目を閉じ、進行係からの次の指示を待った。
すると思いがけないことに、その指示は部屋にある黄色いものをひとつあげるようにというものだった! 思い出す限りでは、そのとき黄色いものをあげられた人は─もちろん私も含めて─ひとりもいなかった。全員が青いものばかりに意識を集中していたせいだ。そのために黄色いものは、他の緑や紫や赤のものと一緒に背景へと姿を消していた。私たちが注意を向けなかったことで、まったく見えなくなっていたのだった。
楽観的でいる以外に選択肢はない
この課題は、進行係がその日に伝えたかったテーマのひとつを明確にする役割を果たした。つまり、人がしっかり焦点を合わせようと心に決めたものだけが、その人の世界観を表わすだけでなく、その人が世界で進むべき道をも示してくれる。そして私は自分の人生の紆余曲折を経験するにつれ、なかでも恐怖や絶望に打ちひしがれたとき、その考えが貴重だと思えるようになった。
たとえば最近のパンデミックのさなかには、イヌを連れて散歩しながら探すのを忘れさえしなければ、小さいながらも気晴らしになるさまざまな光景に出合うことができた。歩道に古びた文字を書いたように生えているコケ、低木の茂みに住み着いた賑やかなヤブガラの群れ、クルクルした巻き毛にしか見えないカバノキの樹皮。他の人たちからきちんと2メートルのソーシャルディスタンスをとって歩く人々に、手をつないで近くを散歩するカップルの姿。夏と秋の間じゅう、自宅前の芝生でロウソクをともしながらささやかなパーティーを開いていた隣人たち。道をはさんだわが家の向かいにある小さな公園にコントラバスとバイオリンを持ち出して、いつも一時間だけ演奏していた若い音楽家のグループ。自らも災難に見舞われながら、もっとひどい目に遭っている人たちを力いっぱい支援しようと夢中になっていた人々。すばらしいフレッド・ロジャース(アメリカのテレビ番組の司会者、別名ミスター・ロジャース)が9.11の1年後に、「助けてくれる人たちを探そう」と言った通り、助けてくれる人たちはとてもたくさんいた。
私は生まれつきの楽観主義者で、その性格は優しい父から譲り受けたものだ。実のところ、自分はただ頭が悪いだけなのではないかと心配もしていたが、活動家で大学教授のアンジェラ・デイヴィスによる次の言葉を読んでほっとした─「私は楽観的でいる以外に選択肢はないと思っている。楽観主義はぜったいに必要なものだ。たとえそれが楽観主義への願望にすぎず……頭の中では悲観主義だとしても」。
とはいえ、つねに楽観主義を保つのは難しい。私も他の人たちと同じように(たぶん読者のみなさんも同じだと思うが)人間が周囲の自然界を傷つけているという紛れもない、増える一方の証拠にうろたえ、私たち人間にはもうそれをなんとかしようという気持ちなどないのではないかと恐れてしまう。何しろ政治も文化も、最もひどいやり方で衝突を続けるばかりなのだ。
私は前著『土は私たちを救う(The Soil Will Save Us)』執筆のために、傷ついた農地を回復させる方法を見つけようと奮闘する農場主、牧場主、科学者などに会って楽観主義の源泉を見出しはしたものの、多くの人が思っているように世界が欲張りで執拗で身勝手なものだとしたら、平凡な環境保護のヒーローが増えるだけで十分なのだろうかという疑問が浮かんでくる。
植物と土壌微生物の互いに生命を与え合うパートナーシップ
ロサンゼルスで開催された2015年都市土壌会議でカナダの森林生態学者スザンヌ・シマードが話すのを聞いたのは、それからまもなくのころだ。彼女はこれまで30年にわたって研究を続け、森の中の樹木やその他の生物が、私たちの目には見えないところで協力していることを明らかにしている。
私はちょうど『土は私たちを救う』を書いている最中だったから、植物と土壌微生物の互いに生命を与え合うパートナーシップを知って感動した。実際には、植物がただ土から栄養物を吸い尽くしてジャンクスナックのような滋養分のないものに変えてしまうのではなく、土中にいる無数の微生物とつねに持ちつ持たれつの関係を維持していると気づいたのは、最も思いがけない発見だった。
その会議でシマードは、こうした実りあるパートナーシップは森林全体にわたって広がり、地中に網の目のように張り巡らされた広大な菌類の集まりから力を得ていると話した。私はそれを聞いてワクワクしてしまい、思わず椅子から立ち上がりそうになったほどだ。
その年にポートランドからはるばるバンクーバーまで車で出かけ、シマードと彼女の学生たちに会うことはできたが、同様の見識をもつ別の研究者とランドスケープ(訳注/ひとまとまりの生態圏を包み込んだ景観)を見つけるにはさらに数年もの時間がかかった。
そしてそれらが増えるにつれて、私は書く価値があるものをしっかり理解できたように感じた。たいていの人は学校の理科の授業で習ったことなどほとんど忘れているだろうが、ずっと頭に残っている概念もいくつかはあるだろう。
「適者生存」もそのひとつにちがいない。チャールズ・ダーウィンは、40億年近く続いてきた多くの試練になんとか勝ち残った者たちが、現在、私たちのまわりで生きている種だと結論づけている。
つまりすべての生き物は、資源を手に入れ、食うか食われるかのさまざまな危険を乗り越えて、繁殖に成功することを目指し、その目的を達成するために大昔の祖先から脈々と受け継がれてきた変化の頂点に立っていると考えたわけだ。
そして他の思想家たちもダーウィンが出した結論に飛びつき、競争の概念を生物学の野蛮な創造者に祭り上げた。それからというもの、競争が支配するという考えが私たちの集団脳にとどまり、離れなくなっている。進化論を否定している人も、その仕組みをよく思い出せない人も、詩人テニソンが嘆き悲しんだ通りに自然は「歯と爪を(血で)赤く染めている」と考えてしまう─生き物は乏しい資源をめぐり、凶暴で終わりのない生存競争を繰り広げているとみなしているのだ。
科学者さえも、その多くは自然界でどれだけ広範囲にわたって助け合いの交流があるかを理解していない。「今の生態学者たちは、生命体ははじめから互いに競い合うようにできているというパラダイムの中で育ってきたのです」と、生物学者のリチャード・カーバンは私に話した。
「植物などの生命体がどれだけ緊密に協力し合っているかを知って、驚く生態学者がたくさんいますよ。彼らは自分たちの研究で、協力を見出そうなどとは思っていませんから」。その結果として、人は自然をゼロサム・ゲームとみなすようになったらしく、私たちが(人間だけでなく、カラス、イトスギ、侵入性のニンニクガラシなど、あらゆる生物が)何かを手に入れたとき、そのすべては他の生き物や共有された環境全体を犠牲にした結果なのだとみなしてしまう。この見方に従うと、私たち人間の数が増え続けるにつれ、残念ながら世界の残りの部分は苦しむことになる。
けれども、もし私たちがダーウィンの洞察を誤ったやり方で世界にあてはめ、自然界に存在している寛容さと協力関係を見落としているとしたらどうだろう。シマードの研究を知って、私はそう考えはじめた。そしてもし私たちが、もっと広い世界の寛容さと協力関係を知らずにいれば、自分たち自身の調和のあるつながりをも見落としてしまうだろう。
もちろんそれは、私たちが自然の一部だからだ。私たちは、周囲の自然との複雑で創造的で活気に満ちた関係に支えられ、自然の一部として存在しているからこそ、生きることができる。わが家の玄関近くの木でくつろぐアライグマや道路沿いに生えた雑草と、まったく同じだ。
異なる種や同じ種の間の協力関係が自然界を支え、大いに繁栄させていることを、もし私たちがしっかり理解すれば、その行動はどのように変化するだろうか? 私があの画廊で青いものを探すよう指示されたように、もし私たちがそうした協力関係を探すとしたら?
そうすれば、自分たち人間は搾取者、植民者、破壊者などではなく、相棒として手助けをする立場にいて、より大きな、互いに与え合う仕組みの一部だとみなしはじめることができるだろうか?
科学は人間が自然からの収穫の限度を理解する道具
現代の科学の最良にして最も重要な使い道とは、自然がどのように機能しているかを見つけ出すこと─この本で私が話を聞いたすばらしい科学者たちの多くがそうしている─そして人類が自分たちの行動を変え、これまで自然に対して加えてきた傷を癒やすとともに、これ以上の傷を与えずにすむよう手助けすることだと、私には思える。そうすれば、世界が繁栄するようにとの願いに希望を与え、支援することができる。
もちろん私たちはその恩恵を受けることになるだろうが、それだけが目的ではない。人間以外の生き物も私たちと同じように繁栄する権利をもっていて、人間によって利用されるために存在しているわけではないからだ。
昔の文化が自然界での自分たちの居場所をどのように考えていたのか、そして人間が必要とするものと他の生き物が必要とするもののバランスをどう保っていたのか─そうしたことから学んでいる科学者は大勢いる。もし私たちが周囲の自然を破壊するのではなく尊重することを学べば、私たち自身ももっと寛大になり、互いに成長を促し合うようになるだろう。
「ムーブメント・ジェネレーション・ジャスティス・アンド・エコロジー・プロジェクト」の活動家であるゴーパル・ダヤネニは、次のように言っている。「あなたが人間に対してすることは、土壌に対してすることであり、あなたが土壌に対してすることは、人間に対してすることだ。これは、陸上で暮らす数多くの先住民の伝統に共通した概念になっている」
私たちを取り巻く自然との、こうした敬意に満ちた絆を最もみごとに表現していると思われる人物は、ネイティブ・アメリカンの植物学者で作家のロビン・ウォール・キマラーだ。
とにかく、私は彼女の著作と記録に魅了されている。人間は生きるために自然から奪わなければならないが、それが正当な収穫であることを確かめなければならないと、彼女は言う。
最初の植物や動物、最後の植物や動物を奪ってはいけない。許可を求めなさい─世界は物惜しみせず、創造力に富んでいるとはいえ、ときにはノーと答えることもあり、科学はその限度を理解するための強力な道具になる。与える害をできる限り小さくとどめなさい。そして感謝の気持ちを忘れずに、分け合い、お返しをしなさい─私たちはもらったものに報いる方法を学ぶ必要がある。
人間はあまりにも多くのものを手にしながら、たいていは十分な敬意を払っていない。海で魚をとったり畑でトマトを育てたりするとき、大草原や森から土地を奪って家を建て町を作るとき、都会や農地に水を引くとき、他の人の労力や信頼を利用するとき……すべてが敬意を払うべき機会だ。この本では、人間社会とその周辺で生き物と生態系を団結させるような協力関係を、そして互いのためになる結びつきの機会を、探していこうと思う。それは感動を呼び起こす科学になるにちがいない。
だがこの本で最もワクワクするのは、周囲の自然が私たちから何を必要としているかについての新しい知見に基づき、多くの人が実際にどう行動しているかを目にする部分だと思っている。それらの人々は、生き物の世界と手を結ぼうという決意、この使命を果たすために互いのパートナーになろうという決意をして、荒涼とした光景が私たちに共通の運命などではないことを示している。
本書は、クリスティン・オールソンによる『Sweet in Tooth and Claw - Stories of Generosity and Cooperation in the Natural World』を邦訳したもので、邦題『互恵で栄える生物界―利己主義と競争の進化論を超えて』が伝える通り、私たち人間もその一員であるこの地球上の生物は、互いに助け合いながら栄えてきたことを教えてくれる1冊だ。
「私たちは、周囲の自然との複雑で創造的で活気に満ちた関係に支えられ、自然の一部として存在しているからこそ、生きることができる」という言葉が、まさに著者が本書に込めた気持ちを言い表している。
そして、学校の生物の時間に習ったダーウィンの「適者生存」やドーキンスの「利己的な遺伝子」といった言葉が伝える「競争」、「勝ち残り」、「利己主義」の概念にとらわれているかぎり、人類がこれから歩む道にはいっそうの苦難が待ち受けていることも教えてくれる。
8つの章はどれも興味深い。
第1章ではカナダの森に分け入り、森の木をすべて切り倒してから材木に適した同じ種類の苗木だけを整然と植えるという従来の商業林の問題を明らかにする一方、それぞれの樹木が地中の(私たちの目には見えない広範囲にわたる)菌根菌ネットワークを通じて互いに助け合っている様子を描く。種類の異なる樹木、大小さまざまな樹木が、土の中で連絡をとりながら足りないものを融通し合っていることなど、地面の上に立つ私たちには想像もつかないが、多くの研究者の努力によってその事実がわかってきている。この章を読んだあとでは郊外で森や林を目にしたときに見える景色は大きく違ってくるだろう。いや、庭先の小さな木を見ても、土の中の会話が聞こえてくるように思えるにちがいない。
第2章では、少しごまかして労力を省いてしまうかわいらしいマルハナバチを想像しながら、互いに力を貸しあって繁栄してきた生き物の相利共生についてさらに考える。そして、人間の相互扶助の大切さを説いたクロポトキンにも思いを馳せる。クロポトキンという名前を聞いたことはあっても何をしたかよく知らない読者は多いと思うが、「実在のスーパーヒーローを探している映画制作会社があれば、この人物には映画の主人公にするにふさわしい、大いなる価値があると感じるにちがいない」と著者が言うほどの波乱万丈の一生からは、最後まで目を離せない。
その後の章では、想像力を最大限に発揮して私たち一人ひとりがもっている目に見えない微生物叢を思い描き、砂漠化していた放牧地に豊かな緑と水とビーバーダムを取り戻したアメリカ西部を訪問し、環境再生型農業に取り組む農地を訪れ、メキシコのコーヒー農園で長年研究を続ける学者から話を聞く。コーヒー好きな読者は、コーヒー農園の様子に興味を惹かれること請け合いだ。
そしてどの章を読んでも、地球上の生物すべてがつながりあって、互いに協力しているからこそ、私たち人間も生きていられると実感する。さらに、サーモンが遡上する川の再生が進みつつあるオレゴン州の太平洋岸などを訪ね歩いたあと、最後に大都市に戻るのは、「私はこの本を締めくくる章を、都市をめぐるものにしたいと思っていた。都市で暮らす人々が人口の大半を占めているからだ」という著者の考えに沿ったものだ。
こうして最後の第8章では、多くの読者にとって身近と思われる都市のこれからについて考える機会がある。「都市に密度の高い樹冠があれば、木陰では路面の温度が日の当たる場所より摂氏11度から25度も低くなることがある」、「その他の緑樹も都市の熱を下げる働きをする」、「舗装道路から見上げるような位置の屋上緑化でさえ、下方の歩道の温度を下げる効果を果たす」、「都市の緑化は大気汚染も減らしてくれる」といった緑の効用には、近年の夏の酷暑に危険を感じているにちがいない多くの読者が、惹きつけられずにいられないだろう。
もちろん建築物の高断熱化や都市計画などの大規模な施策が必要になるが、一人ひとりの小さな努力で庭先やベランダに緑を増やせれば、誰もが大きな自然の力の一部になって、相互扶助、相利共生に加われるのではないだろうか。ほんのわずかな力でも、自然が仲間に入れてくれることを信じたい気持ちでいっぱいだ。
著者のクリスティン・オールソンは、オレゴン州ポートランド在住のライター、作家で、オールソンの書いた記事はさまざまな新聞や雑誌などに掲載されている。2014年に出版した前著『The Soil Will Save Us―How Scientists, Farmers, and Foodies Are Healing the Soil to Save the Planet(土は私たちを救う─科学者、農場主、食通はいかにして土壌を癒やし、この惑星を救っているか)』では、人間がこれまで誤ったやり方で農場と牧場を拡大してきたことで、土壌に含まれていた炭素の80パーセントを失ってしまったと指摘した。
そしてその炭素は今では大気中にあるから、このままではたとえ化石燃料の利用をすぐにやめたとしても地球温暖化は続くと警鐘をならす。その一方、私たち人間の力で大気中の炭素を再び土壌に戻す方法があると説く。
それに続く本書の執筆には「およそ6年をかけ」、「考えを巡らせていた期間は数十年にもなる」と謝辞にあるから、数多くの学者のもとを実際に訪ねて研究の内容を自分の目で確かめたうえで深い考察を巡らせた、著者渾身の作と言えるだろう。そうした著者の熱い気持ちが、訳文を通して読者に伝わることを願っている。(後略)