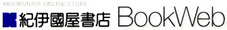ƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚é گ«–\—حƒTƒoƒCƒoپ[‚ئ•v‚½‚؟پ{‰ٌ•œ‚جچإ‘Oگü
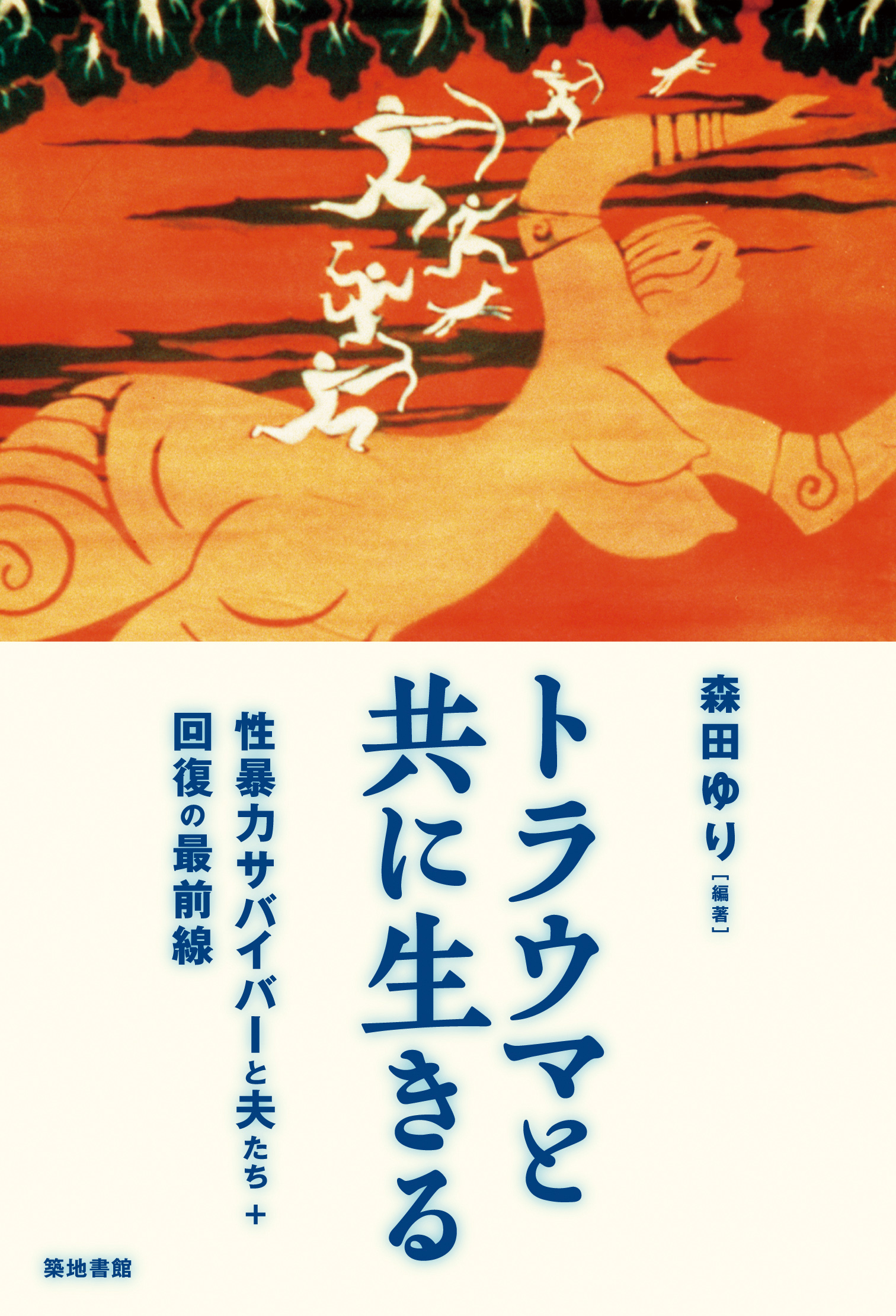
| گX“c‚ن‚èپm•ز’کپn 2,400‰~+گإپ@ژlکZ”»•ہگ»پ@328•إپ@2021”N1Œژٹ§چsپ@ISBN978-4-8067-1612-9 ژq‚ا‚àژ‘م‚جگ«–\—ح”يٹQƒTƒoƒCƒoپ[’B‚جگش—‡پX‚بڈطŒ¾‚ئپA ƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚é–L‚©‚ب’mŒb‚ئ–ô“®‚·‚é‚¢‚ج‚؟پB ‚±‚ج–â‘è‚ةگو‹ى“I‚ةژو‚è‘g‚ف‘±‚¯‚ؤ‚«‚½’کژز‚ھپA گ¢ٹE‚جچإ‘Oگü‚جژ‹“_‚ئژx‰‡‚ج‹ï‘ج“I•û–@‚ً’ٌژ¦‚·‚é‘ز–]‚جڈ‘پB |
گX“c‚ن‚èپi‚à‚肽پE‚ن‚èپj
چى‰ئپ@ƒGƒ“ƒpƒڈƒپƒ“ƒgپEƒZƒ“ƒ^پ[ژهچة
Œ³ƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒA‘هٹwژه”CŒ¤‹†ˆُپAŒ³—§–½ٹظ‘هٹw‹qˆُ‹³ژِپB
1981 ”N‚©‚çCalifornia CAP Training Center پA1985 ”N‚©‚çƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒAڈBژذ‰ï•ںژƒ‹اژq‚ا‚à‚ج‹s‘ز–hژ~ژ؛‚جƒgƒŒپ[ƒiپ[‚ئ‚µ‚ؤ‹خ–±پB1990 ”N‚©‚ç‚W”NٹشپAƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒA‘هٹwژه”CŒ¤‹†ˆُپuƒ_ƒCƒoپ[ƒVƒeƒBپEƒgƒŒپ[ƒiپ[پv‚ئ‚µ‚ؤپA‘½—lگ«پAگlژيچ·•تپAگ«چ·•ت‚ب‚اپAگlŒ –â‘è‚جŒ¤ڈCƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚جٹJ”‚ئ‘هٹw‹³گEˆُ‚ض‚جŒ¤ڈCژw“±‚ة“–‚½‚éپBژQ‰ءŒ^Œ¤ڈC‚ج•û–@ک_‚ئƒXƒLƒ‹‚ًٹJ”‚µپADiversity Training Guide ‚ًƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒA‘هٹw‚©‚çڈo”إپi‰pŒê”إ‚حگâ”إپB“ْ–{Œê”إ‚حپw‘½—lگ«ƒtƒ@ƒVƒٹƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“پEƒKƒCƒhپx‰ً•ْڈo”إژذپjپB
1997 ”N“ْ–{‚إƒGƒ“ƒpƒڈƒپƒ“ƒgپEƒZƒ“ƒ^پ[‚ًگف—§‚µپAچsگ‚âٹé‹ئ‚جˆث—ٹ‚إپA‘½—lگ«پAگlŒ –â‘èپA‹s‘زپA‚c‚uپAگ«–\—حپAƒˆپ[ƒKپAƒ}ƒCƒ“ƒhƒtƒ‹ƒlƒXلز‘z‚ب‚ا‚ًƒeپ[ƒ}‚ةŒ¤ڈCٹˆ“®‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚éپBƒAƒچƒnپEƒLƒbƒYپEƒˆپ[ƒK‚ًژهچة‚µپAژ™“¶—{Œىژ{گفپAژ™“¶گS—ژ،—أژ{گف‚ب‚ا‚إƒqپ[ƒٹƒ“ƒOپEƒˆپ[ƒK‚ئلز‘z‚ً‹³‚¦‚é‚ئ“¯ژ‚ة‚»‚جƒٹپ[ƒ_پ[‚ً—{گ¬پB2016 ”N“xƒAƒپƒٹƒJƒ“پEƒˆپ[ƒKپEƒAƒ‰ƒCƒAƒ“ƒXڈـژَڈـپB
‹s‘ز‚ةژٹ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½گe‚ج‰ٌ•œƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پuMY TREE ƒyƒAƒŒƒ“ƒcپEƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پv‚ً2001 ”N‚ةٹJ”پBٹe’n‚ة‚»‚جژہ‘Hژز‚ً—{گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‘و57 ‰ٌ•غŒ’•¶‰»ڈـژَڈـپB
پuMY TREE Jr ‚‚·‚ج‚«ƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پFگ«–\—ح‰ءٹQƒeƒBپ[ƒ“ƒY‚ج‰ٌ•œپvپuMY TREE Jr ‚³‚‚çƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پF–\—ح”يٹQژq‚ا‚à‚ج‰ٌ•œپvƒڈپ[ƒNƒuƒbƒN‚ًٹJ”پBلز‘zŒP—û‚ً‚ئ‚à‚ب‚¤‘وژO”gچs“®—أ–@‚جژq‚ا‚à‚جگ«‰ءٹQ‚ج‰ٌ•œƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚جژہ‘HژزŒ¤ڈC‚ًژہژ{’†پB
1979 ”N‚©‚çچ،“ْ‚ـ‚إپAگوڈZƒAƒپƒٹƒJپEƒCƒ“ƒfƒBƒAƒ“‚جگlŒ ‰ٌ•œ‰^“®‚ًژx‰‡‚µپA“ْ–{‚ئƒCƒ“ƒfƒBƒAƒ“‚ئ‚جŒً—¬‚ةŒg‚ي‚ء‚ؤ‚«‚½پBپwگ¹‚ب‚éچ°پ\Œ»‘مƒAƒپƒٹƒJپEƒCƒ“ƒfƒBƒAƒ“ژw“±ژزƒfƒjƒXپEƒoƒ“ƒNƒX‚حŒê‚éپxپi‹¤’کپA’©“ْگV•·ژذپj‚إ1988 ”N“x’©“ْƒWƒƒپ[ƒiƒ‹پEƒmƒ“ƒtƒBƒNƒVƒ‡ƒ“‘هڈـپAپw‚ ‚ب‚½‚ھژç‚é ‚ ‚ب‚½‚جگSپE‚ ‚ب‚½‚ج‚©‚炾پxپi“¶کbٹظڈo”إپj‚إ1998 ”N“xژYŒoژ™“¶ڈo”إ•¶‰»ڈـژَڈـپB
ژه‚ب’کڈ‘پwژq‚ا‚à‚ئ–\—حپxپwژq‚ا‚à‚ض‚جگ«“I‹s‘زپxپiˆبڈمپAٹâ”gڈ‘“XپjپAپw‚µ‚آ‚¯‚ئ‘ج”±پxپw‹Cژ‚؟‚ج–{پxپiˆبڈمپA“¶کbٹظڈo”إپjپAپw‘ج”±‚ئگي‘ˆپxپi‚©‚à‚ھ‚يڈo”إپjپAپw‹s‘زپEگe‚ة‚àƒPƒA‚ًپxپw’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚ؤپxپw–ü‚µ‚جƒGƒ“ƒpƒڈƒپƒ“ƒgپxپwگس”C‚ئ–ü‚µپxپiˆبڈمپA’z’nڈ‘ٹظپjپAپwƒGƒ“ƒpƒڈƒپƒ“ƒg‚ئگlŒ پxپw”ٌ–\—حƒ^ƒ“ƒ|ƒ|چىگيپxپiˆبڈمپA‰ً•ْڈo”إژذپjپA‚»‚ج‘¼“ْپE‰pŒê’کڈ‘پE–َڈ‘‘½گ”پB
ƒpپ[ƒg‚h ‹êڈa‚ج“ْپX‚ًŒo‚ؤپAچ،ƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚é
‚PپAژq‚ا‚à‚½‚؟‚ً”يٹQژز‚ة‚à‰ءٹQژز‚ة‚à‚µ‚ب‚¢‚½‚ك‚ة –ِ’Jکa”ü
پ@پ@پu‚ا‚¤‚â‚ء‚ؤ‰ٌ•œ‚ًژx‚¦‚½‚ج‚إ‚·‚©پHپv “c‘؛“Wڈ«
‚QپAƒڈƒ^ƒVƒnپcپc‘½ڈdگlٹi‚¾‚ء‚½ —é–طژOگçŒb
پ@پ@‰ن‚ھ‰ئ‚ح‚¢‚آ‚àƒ\پ[ƒVƒƒƒ‹ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX —é–طŒ’“ٌ
‚RپA–¢—ˆ‚حˆê‚آ‚¶‚ل‚ب‚¢ چH“،گçŒb
پ@پ@’n—‹‚ح‘±‚‚وپA‚ا‚±‚ـ‚إ‚àپiڈخپj چH“،—zˆê
‚SپA100گlˆبڈم‚جگlٹi‚½‚؟‚ئ‚ج‘خکbپFڈ¬ژ™ٹْƒ}ƒCƒ“ƒhƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‰؛‚جگ«–\—ح‚ئ‰ءٹQ‚ج‹گ§ ƒTƒ“ƒUƒV
‚TپA“¯ˆس‚ج‚ب‚¢گ«چsˆ×‚حگ«–\—ح‚إ‚· ژR–{پ@ڈپ
ƒpپ[ƒg‡U —‰ً‚ئƒPƒA‚جچإ‘Oگü گX“c‚ن‚è
‚PپAژq‚ا‚àژ‘م‚جگ«–\—ح”يٹQ‚ج’·ٹْ“I‰e‹؟
ƒTƒoƒCƒoپ[‚©‚çƒXƒ‰ƒCƒoپ[‚ض
‚o‚s‚r‚c”گ¶—¦‚جچ‚‚³
گg‘ج‚ض‚ج‰e‹؟„ں„ں’†گ•گ«‰ك•qڈاŒَŒQپi‚b‚r‚rپj‚ئ‚¢‚¤گVƒpƒ‰ƒ_ƒCƒ€
‚`‚b‚dپi‹t‹«“Iڈ¬ژ™ٹْ‘جŒ±پjŒ¤‹†ڈذ‰î‚إ–Y‚ê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ
ƒ|ƒٹƒrƒNƒeƒBƒ€پi‘½ڈd”يٹQپj
گ«–\—ح‚ج‰ٌ•œ‚ة‚¨‚¯‚鈤’…‘خڈغ‚ج—ح
گS‚ج‰‹}ژè“–
‚QپAƒgƒ‰ƒEƒ}‚ً–ü‚·‚ئ‚ح
–ü‚·‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚جƒ‹پ[ƒc
Œ»‘مگl‚ج•sˆہ
ٹO“Iژ©‘R‚ئ“à“Iژ©‘R
ژµ‘w‚جڈo‰ï‚¢
–ü‚µ‚ئ‚حڈo‰ï‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ
ƒ{ƒfƒBپ[ƒgپ[ƒN
ƒCƒ“ƒiپ[ƒtƒ@ƒ~ƒٹپ[‚ج‰~‘ى‰ï‹c
ƒCƒپپ[ƒWچأ–°ƒZƒ‰ƒsپ[
’jگ«ƒTƒoƒCƒoپ[‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ج“à‚ب‚éژq‚ا‚à
ƒˆپ[ƒK‚ئلز‘z‚جŒّ‰ت
ƒqپ[ƒٹƒ“ƒOƒˆپ[ƒK
گ«–\—حƒTƒoƒCƒoپ[‚ة‚ح‚µ‚ب‚¢ƒ|پ[ƒY
–ˆ“ْ5•ھ‚جلز‘z‚جƒpƒڈپ[
ƒˆپ[ƒK‚ح”]ƒgƒŒپEƒˆپ[ƒK‚ح‹طƒgƒŒ
‚`‚k‚n‚g‚` ‚j‚h‚c‚r ‚x‚n‚f‚`‚s‚lپiƒAƒچƒnپEƒLƒcƒYپEƒˆپ[ƒKپj‚ج“ء’¥
‚RپA‰ً—£پ@‚c‚h‚cپ^‚n‚r‚c‚c‚»‚µ‚ؤڈ¬ژ™ٹْƒ}ƒCƒ“ƒhƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹
–ت‘O‚c‚u‚جٹG
3‚آ‚ج‚e”½‰پ@
‘n‘¢“I‚بگ¶‘¶گي—ھ
ڈ¬ژ™ٹْƒ}ƒCƒ“ƒhƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹
’¹‚©‚²ک_
‚SپAگ«‰ءٹQ‚ً‚µ‚½چكˆ«ٹ´
ژ©•ھ‚ً‹–‚·ƒZƒŒƒ‚ƒjپ[
ƒgƒ‰ƒEƒ}‚جچؤ‰‰
‹گ§‚³‚ꂽگ«‰ءٹQ
ƒpپ[ƒg‡V چ،پAژq‚ا‚à‚ج”يٹQ‚ًƒgƒ‰ƒEƒ}‰»‚³‚¹‚ب‚¢‚½‚ك‚ة گX“c‚ن‚è
‚PپAگ«ƒw‚جŒ’چN‚ب‹»–،‚©گ«‰»چs“®‚©
4‚آ‚جٹîڈ€
‘خکb—ح
‚ ‚ب‚½‚ة‚à‚إ‚«‚éگS‚ج‰‹}ژè“–
’®‚پiژ¨پ@ڈ\ژlپ@گSپj‚جƒpƒڈپ[
‚QپAگ«–\—ح‚ًژَ‚¯‚½ژq‚ا‚à‚جکb‚ً’®‚ƒvƒچƒgƒRƒ‹
ٹJژ¦‚حˆêکA‚جƒvƒچƒZƒX
”ي‹s‘زژ™‚ئ‚ج‘خکb‚ج‹Z–@
‚µ‚ؤ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢‚±‚ئ
پuگ«“I‹s‘زڈ‡‰ڈاŒَŒQپv‚ًچؤ‚ر
‚RپAگ«‰ءٹQ‚·‚éژq‚ا‚à‚ج‰ٌ•œپu‚l‚x ‚s‚q‚d‚dپ@ƒWƒ…ƒjƒAپE‚‚·‚ج‚«ƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پv
ژq‚ا‚à‚جگ«”يٹQ‚ج‰ءٹQژز‚ج”¼•ھ‚ھژq‚ا‚à
‰ءٹQ‚©‚ç‚ج‰ٌ•œ‚ح”يٹQ‚جƒPƒA‚©‚ç
“{‚è‚ج‰¼–ت
‚SپAپuڈ¬ژ™گ«ˆ¤پv‚ئ‚¢‚¤–َŒê‚حژ€Œê‚ة
–|–َŒêپuڈ¬ژ™گ«ˆ¤پv‚ھ‚à‚½‚炵‚ؤ‚¢‚éگ[چڈ‚ب”يٹQ
“ق—اژsڈ¬ˆêڈڈ——U‰ûژEگlژ–Œڈ‚ج‰ءٹQژز
ƒyƒhƒtƒ@ƒCƒ‹‚àگ«‚ج‘½—lگ«پH
‚ ‚ئ‚ھ‚«
ژQچl•¶Œ£
پw’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚ؤپxپi’z’nڈ‘ٹظپA1992”Nپj‚حگ«–\—ح”يٹQ‚ًژَ‚¯‚½“ْ–{‚جڈ—گ«‚½‚؟‚جگ؛‚ًڈW‚ك‚½چإڈ‰‚ج–{‚إ‚µ‚½پB30”N‘O‚ج1990”N‚ةپu“–ژ–ژز‚جگ؛‚±‚»‚ھژذ‰ï‚ً•د‚¦‚é—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ ‚ب‚½‚جگ؛‚ًپv‚ئگV•·‹Lژ–‚ً’ت‚µ‚ؤŒؤ‚ر‚©‚¯‚½‚ئ‚±‚ëپAپuژ„‚àپvپuژ„‚ة‚à‹N‚«‚ـ‚µ‚½پvپuMe Tooپv‚ئ‚²ژ©گg‚جگ«”يٹQ‘جŒ±‚ًŒê‚éژèژ†‚ھژںپX‚ئ‚ئ‚ا‚ـ‚邱‚ئ‚ب‚“ح‚«پAژ„‚½‚؟‚ً‹ء‚©‚¹‚ـ‚µ‚½پB
پ@Me Too ‰^“®‚ح“ْ–{‚إ‚à30”N‘O‚ةژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB
پw’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚ؤپx‚إ22گl‚ج“ْ–{‚جگ«–\—حƒTƒoƒCƒoپ[‚½‚؟‚حپA‚»‚ꂼ‚ê‚ج‹°•|‚â‹ê”Y‘جŒ±‚ًŒê‚邱‚ئ‚إگ«–\—ح‚ج‚µ‚¶‚ـ‚ً‚â‚ش‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@“¯ڈ‘‚إپAژ„‚ح–â‘è‚ج—ًژj“Iژذ‰ï“I”wŒiپAگ«–\—ح–â‘è‚ض‚ج‘خ‰‚جٹî–{ژpگ¨پA–â‘è‚ج‹•‘œ‚ئ
ژہ‘شپA—\–h‚ج‹ï‘ج“I•û–@‚ة‚آ‚¢‚ؤک_‚¶پAژں‚ج‚و‚¤‚ةŒؤ‚ر‚©‚¯‚ـ‚µ‚½پB
پuگlگ¶‚جƒlƒKƒeƒBƒu‚ب‰ک“_‚إ‚µ‚©‚ب‚©‚ء‚½‚»‚ج‘جŒ±‚حپA‚»‚ê‚ًŒê‚èپAˆسژ¯‰»‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚éƒvƒچƒZƒX‚ج’†‚إپA‚»‚جگl‚ج‹‚³‚ج‹’‚è‚ا‚±‚ë‚ئ‚ب‚èپA‚»‚جگl‚ج‘¶چف‚جٹj‚ئ‚à‚ب‚è‚ـ‚·پBŒê‚è‚ح‚¶‚ك‚邱‚ئپA‚¢‚ـ‚¾‘¶چف‚µ‚ب‚¢Œ¾—t‚ً‘{‚µ‚ب‚ھ‚çپA‚½‚ا‚½‚ا‚µ‚‚ئ‚àŒê‚è‚ح‚¶‚ك‚邱‚ئپBŒê‚邱‚ئ‚إڈo‰ï‚¢‚ھگ¶‚ـ‚êپAژ©•ھ‚ج‹P‚«‚ًگM‚¶‚½‚¢گl‚½‚؟‚ج‚¢‚ج‚؟‚ةکA‚ب‚éƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚ھ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚‚إ‚µ‚ه‚¤پB
‚ذ‚ئ‚½‚ر’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚½‚»‚جگ؛‚ً‘ه‚«‚چL‚پA“ْ–{ژذ‰ï‚ج‚¢‚½‚é‚ئ‚±‚ë‚ة‹؟‚«“n‚点‚ؤ‚¢‚‘ه‚«‚ب—¬‚ê‚جƒ€پ[ƒuƒپƒ“ƒg‚ج’S‚¢ژè‚ةپA‚ ‚ب‚½‚à‰ء‚ي‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پv
پ@‚»‚µ‚ؤگ«–\—ح‚ج’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚郀پ[ƒuƒپƒ“ƒg‚ھ“ْ–{‘Sچ‘‚إ‚ن‚ء‚‚è‚ئچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB
پw’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚ؤپx‚ةٹٌچe‚µ‚½گl‚½‚؟‚ج’†‚©‚ç‚àپAچظ”»‚ة‘i‚¦‚½گlپA–{‚ًڈo”إ‚µ‚½گlپAƒTƒoƒCƒoپ[‚جƒAپ[ƒg“W——‰ï‚ًٹJ‚¢‚½گlپA‚b‚`‚oپiژq‚ا‚à‚ض‚ج–\—ح–hژ~پjƒvƒچƒOƒ‰ƒ€‚ًٹwچZ‚ة“ح‚¯‘±‚¯‚ؤ‚¢‚éگl‚ب‚ا‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب•\Œ»ٹˆ“®‚ً‘±‚¯‚éگlپX‚ھگ¶‚ـ‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚éچs“®‚ح•K‚¸‚µ‚àŒ¾—t‚إ‚ب‚‚ؤ‚¢‚¢پB‰¹ٹyپA—x‚èپAژچپA‰f‘œ‚ب‚اپB‰ك‹ژ‚ج‹ê‚µ‚ف‚حژ©•ھ‚ب‚è‚ج•\Œ»ژè’i‚ً“¾‚½‚ئ‚«پA‚»‚جگl‚جگ¶‚«‚é—ح‚ج—h‚é‚ھ‚ب‚¢ٹjگS‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
پ@—cژ™ٹْ‚ة‹ٹ‚³‚ꂽ‚½‚ء‚½ˆê“x‚ج‘جŒ±‚ًٹٌچe‚µ‚½پuˆêگl•é‚炵‚ج”kپv‚حپuڈ‰‚ك‚ؤ•¶ژڑ‚ة‚µ‚ؤ70—]”N”é‚ك‚½‹¹‚جڈ‚ھ—ـ‚ئ‚ئ‚à‚ة—n‚¯‚ؤ‚ن‚پv‚ئڈ‘‚«‚ـ‚µ‚½پB“–ژ78چخ‚¾‚ء‚½‚±‚ج•û‚ح‚»‚جŒمپA‚ا‚ج‚و‚¤‚بگlگ¶‚ً‘—‚ç‚ꂽ‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB
پ@“ْ–{‚جگ«–\—ح”يٹQژز‚½‚؟‚ة110”N‚à‚جٹشپA’¾–ظ‚ً‹‚¢‚ؤ‚«‚½‹ٹچك‚ھ‘ه•‚ة‰üگ³‚³‚ê‚ؤ2”N‚àŒo‚½‚ب‚¢2019”NڈtپB•ں‰ھپA–¼Œأ‰®پAگأ‰ھپA•lڈ¼‚ج’nچظ‚إگ«–\—حژ–Œڈ”يچگ‚ض‚ج–³چك”»Œˆ‚ھ‘±‚«‚ـ‚µ‚½پBƒoƒbƒNƒ‰ƒbƒVƒ…پi—h‚è–ك‚µپj‚إ‚·پB’P‚ةچظ”»ٹ¯Œآگl‚جŒ©‰ً‚ج–â‘è‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژq‚ا‚à‚âڈ—گ«‚جگlŒ ‚ھˆê•à‚إ‚à—ح‚ً“¾‚é‚ئپAٹù“¾Œ ‚ً‹؛‚©‚³‚ê‚é•sˆہ‚ة‹ى‚ç‚ê‚éگlپX‚ھپA—h‚è–ك‚µ‚ً‚©‚¯‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚±‚ج50”NپA•ؤچ‘‚إ‚à‰½“x‚àŒJ‚è•ش‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚إ‚µ‚½پB
پ@‚µ‚©‚µ2020”N2Œژ‚ة•ں‰ھچ‚چظ‚ھپA3Œژ‚ة‚ح–¼Œأ‰®چ‚چظ‚ھ‹t“]—Lچك”»Œˆ‚ًڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پB
“ْ–{‚جژi–@‚ض‚جگâ–]‚ھٹَ–]‚ة•د‚ي‚è‚ـ‚µ‚½پB‚±‚جٹَ–]”»Œˆ‚ًڈo‚³‚¹‚é‚ـ‚إ‚ة‚حپA‘Sچ‘ٹe’n‚ةچL‚ھ‚ء‚½ƒtƒ‰ƒڈپ[ƒfƒ‚پAژx‰‡•ظŒىژm‚ç‚ب‚ا‚½‚‚³‚ٌ‚جگlپX‚جگs—ح‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚إ‚à“¬‚¢‚ح‚ـ‚¾‚ـ‚¾‘±‚پBƒoƒbƒNƒ‰ƒbƒVƒ…‚ح‚±‚ê‚©‚ç‚à‰½“x‚àڈP‚ء‚ؤ‚‚é‚ج‚¾‚©‚çپB
پ@–¼Œأ‰®چ‚چظ‚ج‹t“]”»Œˆ‚ًژَ‚¯‚ؤŒ´چگڈ—گ«‚ح’·•¶‚جƒRƒپƒ“ƒg‚ًڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پuژ„‚جŒoŒ±‚µ‚½پAگM‚¶‚ؤ‚à‚炦‚ب‚¢‚آ‚炳‚ًپA‚±‚ê‚©‚ç‹~‚¢‚ً‹پ‚ك‚ؤ‚‚éژq‚ا‚à‚½‚؟‚ة‚ح‚ا‚¤‚©–،‚ي‚ء‚ؤ‚ظ‚µ‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژ„‚حپAچK‚¢‚ة‚àپA‚â‚ء‚ئژç‚ء‚ؤ‚‚ê‚éپAٹٌ‚è“Y‚ء‚ؤ‚‚ê‚é‘هگl‚ةڈo‰ï‚¦‚ـ‚µ‚½پv
پ@5چخ‚جژ‚جگ«–\—ح”يٹQ‚ًگ¶‚«‚ؤ‚«‚½کa‰ج‚âژچ‚ًپw’¾–ظ‚ً‚â‚ش‚ء‚ؤپx‚ة‚¢‚‚آ‚àٹٌچe‚µ‚ؤ‚‚ꂽ•—ژq‚³‚ٌ‚ح30”N‘O‚ةپA‚·‚إ‚ةMe Too ‰^“®‚جٹَ–]‚ًŒؤ‚ر‚©‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
‚±‚جژw‚ئ‚ـ‚êپ@پ@پ@پ@‹kپ@•—ژq
ژ©•ھ‚ًˆ¤‚µ‚½‚¢گlپ@‚±‚جژw‚ئ‚ـ‚ê
”é–§‚ًژ‚ء‚½گlپ@‚¨‚¢‚إ‚و‚±‚±‚ة
ژOگlٹٌ‚ê‚خپ@ƒqƒ\ƒqƒ\‚ئچ‚گ؛‚جƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹
Œـگl‚ة‚ب‚ê‚خپ@‚ة‚¬‚â‚©‚¾
ژµگl‚ة‚ب‚ê‚خپ@گS‚à‚ ‚ء‚½‚©
ڈ\گl“ٌڈ\گl‚ة‚ب‚ê‚خپ@‹°‚¢‚à‚ج‚ب‚µ
ژOڈ\گlŒـڈ\گl‚ة‚ب‚ê‚خپ@—F‚ھ—F‚ًŒؤ‚ش
•Sگl‚ة‚ب‚ء‚½‚çپ@گ¢‚ج’†‚à•د‚ي‚é
‚¾‚©‚çپ@‚±‚جژw‚ئ‚ـ‚ê
پ@–{ڈ‘‚إ‚ح“ْ–{‚ة‚¨‚¯‚éگ«–\—ح‚ض‚جژو‚è‘g‚ف–ٌ30”N‚ً“¥‚ـ‚¦‚½پAژں‚جگV‚µ‚¢ژ‹“_‚ئ’mŒ©‚ً’ٌژ¦‚µ‚ـ‚µ‚½پB
1پAƒpپ[ƒg‡T‚إƒTƒoƒCƒoپ[‚½‚؟‚حپA”يٹQ‚جƒgƒ‰ƒEƒ}‚ًچژ•‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚حپA‚ق‚µ‚ëƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚ؤ‚«‚½‰ك‹ژ‚ًژœ‚µ‚فپAŒ»چفپA–¢—ˆ‚àƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‚آ‚«‚ ‚¢‚ب‚ھ‚çگ¶‚«‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤گV‚µ‚¢ƒTƒoƒCƒoپ[‚جژ‹“_‚ًŒê‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒgƒ‰ƒEƒ}‚ح‹ê‚µ‚ف‚إ‚ ‚ء‚½‚¯‚ê‚اپAگV‚µ‚¢‚¢‚ج‚؟‚جŒ¹‚إ‚à‚ ‚é‚ج‚إ‚·پB
2پAƒpپ[ƒg‡U‚إ•Mژز‚حپAƒgƒ‰ƒEƒ}‚ئ‹¤‚ةگ¶‚«‚邽‚ك‚ج—‰ً‚ئƒPƒA‚جچإ‘Oگü‚ًک_‚¶‚ـ‚µ‚½پB
ڈ]—ˆ‚جگ«–\—حٹضکA–{‚إ‚حژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢گV‚µ‚¢’mŒ©پA‚ـ‚½Œأ‚‚©‚ç‚ ‚é‚ج‚ةپAژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢—LŒّ‚بژx‰‡•û–@پAچؤ”Fژ¯‚³‚ꂽƒˆپ[ƒK‚âلز‘z‚ج‹ء‚‚ׂ«Œّ‰تپAچأ–°‚ًژg‚ء‚½ƒ\ƒ}ƒeƒBƒbƒN‚بƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ب‚ا‚إ‚·پB
3پAƒpپ[ƒg‡V‚إ‚حپAژq‚ا‚à‚جچ،‚جگ«”يٹQ‚ًƒgƒ‰ƒEƒ}‰»‚³‚¹‚ب‚¢ژx‰‡‚ج‚ ‚è•û‚ئ‹ï‘ج“I‚بƒXƒeƒbƒv‚ً’ٌژ¦‚µ‚ـ‚µ‚½پBگg‹ك‚بگl‚ھ‚ب‚é‚ׂ‘پ‚‚ةژœ‚µ‚ف‚ً‚à‚ء‚ؤژè“–‚ؤ‚·‚邱‚ئ‚إپAƒŒƒWƒٹƒAƒ“ƒX‚ھ‹N“®‚µ‚ـ‚·پB
4پAپuگ«–\—حپv‚ة‚m‚n‚ً“ث‚«‚آ‚¯‚é”يٹQژزژx‰‡‚جگ¢ٹE‰^“®‚ح1970”N‘م‚ةژn‚ـ‚èپAˆب—ˆ‚»‚ê‚ً’S‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚حڈ—گ«‚½‚؟‚إ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µگ«–\—ح‚ج‰ءٹQژز‚ج9ٹ„ˆبڈم‚ھ’jگ«‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤ“¯ژ‚ةˆ³“|“I‘½گ”‚ج’jگ«‚ھگ«–\—ح‚ً—ا‚µ‚ئ‚µ‚ب‚¢گl‚½‚؟‚إ‚ ‚邱‚ئ‚à‚ـ‚½ژ–ژہ‚إ‚·پB
پ@ڈ—گ«‚½‚؟‚ج‰^“®‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚©‚ç–ٌ50”N‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پBچ،‚ـ‚إ–Tٹدژز‚¾‚ء‚½’jگ«‚½‚؟‚ھپA“–ژ–ژزˆسژ¯‚ًژ‚ء‚ؤƒtƒچƒ“ƒgƒ‰ƒCƒ“‚إپAگ«–\—ح‚ئ‚¢‚¤’jگ«–â‘è‚ةژو‚è‘g‚فپA—ًژj‚ً•د‚¦‚éژ‚ھ—ˆ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB–{ڈ‘‚ةƒTƒoƒCƒoپ[‚ج•v‚½‚؟‚جژè‹L‚ً“ü‚ꂽ‚ج‚حپA‰ٌ•œ‚ة•K‚¸•v‚جژx‰‡‚ھ•K—v‚ب‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚ھپAگ«–\—ح–â‘è‚ة“–ژ–ژز‚ئ‚µ‚ؤٹض‚ي‚é’jگ«‚جگg‹ك‚ب—ل‚ئ‚µ‚ؤپA’jگ«“اژز‚ة“ا‚ٌ‚إ—~‚µ‚©‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚·پB