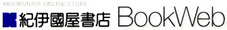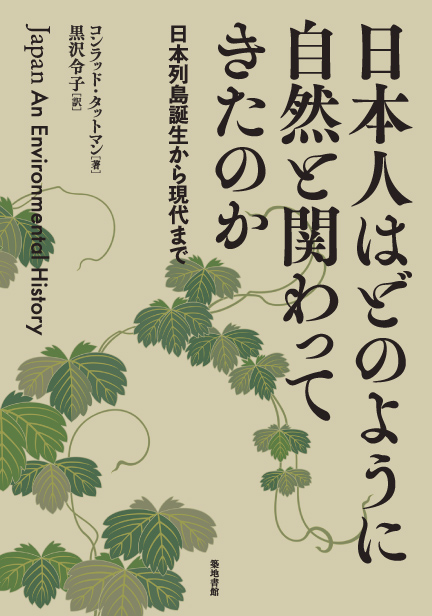日本列島の自然と日本人
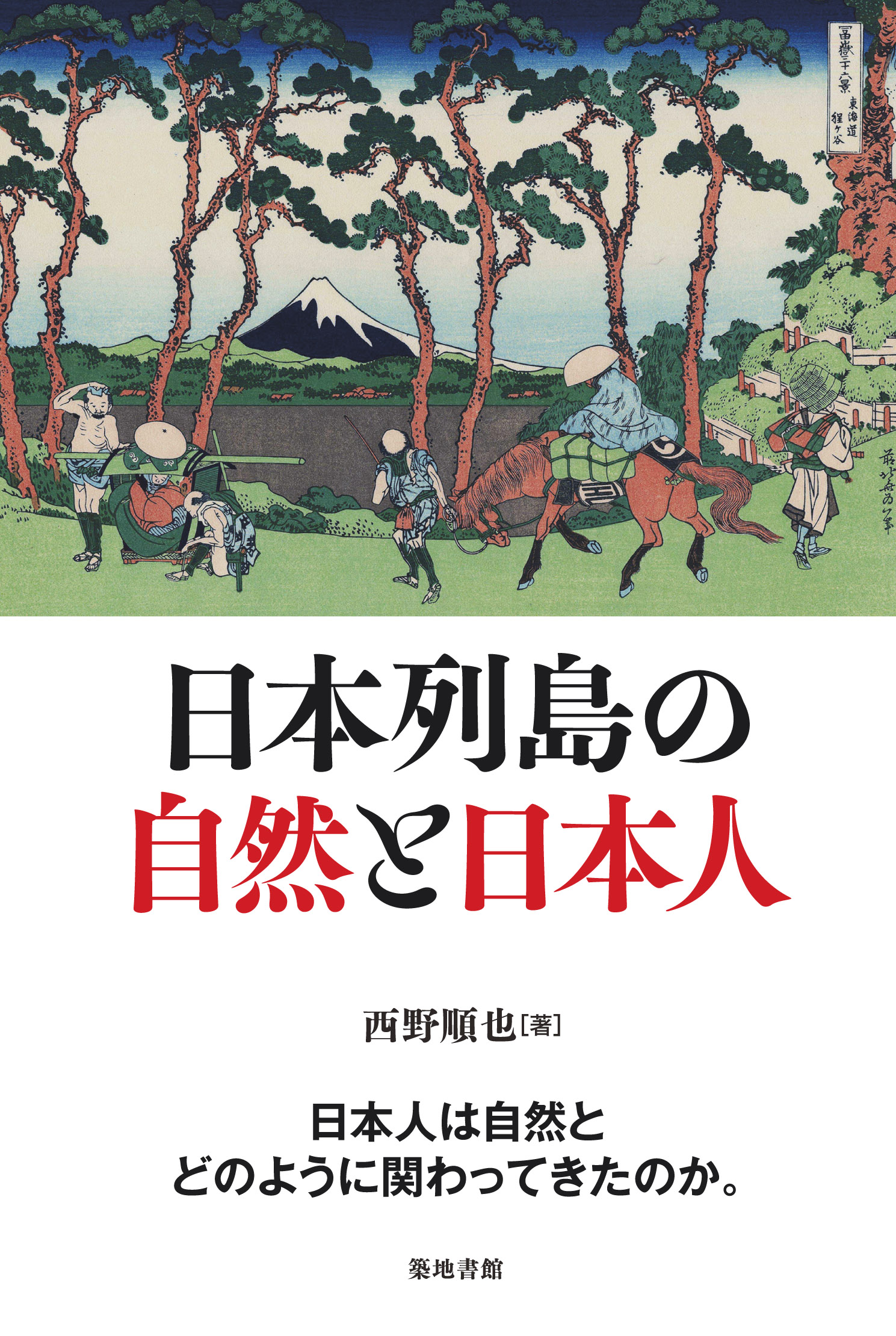
| 西野順也[著] 1,800円+税 四六判並製 184頁 2019年2月刊行 ISBN978-4-8067-1579-5 緑豊かな国で、縄文の時代から現代まで、人々はさまざまに自然の恵みを活用し、 時には痛めつけ、一方でその大いなる存在を敬い、畏れ、愛でてきた。 万葉集に登場する数々の草花、戦や築城による森林破壊、 江戸時代の園芸ブーム、信仰と自然の深いつながりが息づく年中行事など。 日本人の自然観はどのように育まれていったのか。 そしてそれは、どのような文化を生み出していったのか。 日本人と自然の深い関わりを見つめ、 これからの私たちが自然とどう向き合っていくべきかを問いかける。 |
西野順也(にしの・じゅんや)
1954 年宮城県生まれ。
東北大学工学部工学研究科応用化学科博士課程後期修了。工学博士。
石川島播磨重工業(株)[現在(株)IHI]に勤務後、宇部工業高等専門学校物質工学科教授を経て、
現在、帝京平成大学健康メディカル学部医療科学科教授。専門は環境化学、環境プロセス工学。
著書に『やさしい環境問題読本─地球の環境についてまず知ってほしいこと』(東京図書出版)、
『火の科学─エネルギー・神・鉄から錬金術まで』(築地書館)がある。
序章
第1章 日本の自然と風土
1 日本の自然
2 日本の風土
3 神話の自然観
4 大地と信仰
5 山水と仏教
6 昔話にみる自然観
第2章 自然との共生
1 定住生活以前の風土
2 定住生活の始まりと自然の利用
(1)縄文人の台頭
(2)落葉樹林帯と照葉樹林帯の違い
(3)縄文人の食料事情
(4)クリ材の利用
3 北方系と南方系の自然利用
4 縄文人の自然観
5 縄文人と山
6 非稲作民と山間地域
第3章 自然と信仰
1 三輪山と富士山
2 農耕と祭祀
3 自然の中の暮らし
(1)正月
(2)春を迎える行事
(3)夏の行事
(4)盆の行事
(5)秋から冬にかけての行事
(6)冬の行事
第4章 花卉(かき)と日本人
1 花への関心
2 サクラの品種の変遷
3 自然界と花
第5章 近世の都市と自然
1 自然と人工
2 環境と再利用
(1)都市の実情
(2)人気の高い下肥
3 「もったいない」の文化
第6章 森林の破壊と再生
1 古代から中世の略奪期
2 近世の森林破壊
3 近代の森林育成
4 明治時代以降の森林事情
5 輸入材の変遷
6 森林と温暖化
7 森林と日本人
第7章 自然と環境問題
1 エネルギーと自然
2 食料生産と水問題
3 ごみと環境問題
終章
参考文献
あとがき
日本は緑の豊かな国である。国土の三分の二は森林だ。平地にも田畑の緑が絨毯のように広がっている。温暖で湿潤な気候は日本の国土に豊かな緑を育んでくれている。日本の森林は樹種が豊富である。シイやカシなどの照葉樹やサクラ、モミジやクリなどの落葉樹が四季折々の装いを見せてくれる。春になるとサクラは花を咲かせ、秋にはモミジが葉を彩らせる。このような変化に人々は季節の移ろいを感じ、歌に詠んできた。同時に、これらの自然は豊かな恵みを提供してくれた。田畑からは米や野菜が、森林からはクリやクルミの実や柿などの果実、ワラビやゼンマイ、キノコなどの林床植物、ウバユリ、ヤマイモ、タケノコなどの根茎類がとれた。これらの食料は日本人の生活を支えてきたのだ。
だからといって日本人は自然を大切にしてきたわけではない。生活するには火を焚く薪が必要だし、住居を建てるにも木材が必要だ。これらは森林から伐り出された。田畑を開発するためにも森林が伐り開かれた。森林の伐採が進み山が禿山同然だったこともある。もちろん、山から木を伐り出しても時間がたてば森林は自然の力によって復活する。祖先が農耕を始めた弥生時代以降、森林は常に人による伐採の圧力と自然の再生力との力関係の中にあった。万葉集に最も多く詠まれている樹木はハギである。ハギは低木で、周りに高木が生い茂っている森林では目立たない木である。ハギが人目につくところに生えているということは周りの高木が伐り倒されていたことを示している。また、歌川広重の東海道五拾三次や葛飾北斎の富嶽三十六景を見ても、山に描かれている木はマツが多い。マツは森林が伐採された後、最初に生えてくる木である。万葉集が詠まれた飛鳥時代から奈良時代にかけてと、広重や北斎の絵が描かれた江戸時代後期は、日本の森林がかなり荒廃していたことを表している。
日本は島国である。海の外との交易が発達していない時代、祖先はあるもので生活するしかなかった。森林が荒廃し、土砂崩れや洪水などの災害が起こっても、大陸の民のようにその土地を捨てて他の土地に移っていくことはできなかった。森林の回復を待ちながら、自然が与えてくれる恵みの範囲内で生きていくしかなかったのだ。幸い湿潤で温暖な気候に恵まれた日本の自然は生命力にあふれていた。しかし、恵み深い自然も時として猛威を振るう。大雨、暴風、旱魃など、猛烈な力を見せつけ、人々が営々と積み上げたものを一瞬にして無に帰してしまう。祖先は豊かだが不安定な自然に適応する努力を数千年積み重ねてきたのだ。その結果、自然に対する緻密な観察力と自然の変化に対する鋭敏な感受性、そして自然の驚異と奥深さに対する感覚が磨き上げられた。やがて、それは日本人特有の精霊信仰的な自然観を育んだ。万葉集巻三の、
土形娘子(ひぢかたのをとめ)を泊瀬(はつせ)の山に火葬(やきはぶ)る時に、柿本朝臣人麻呂が作る歌一首
こもりくの泊瀬の山の山の際(ま)にいさよふ雲は妹(いも)にかもあらむ
隠り処の泊瀬、この泊瀬の山の山あいに、行きもやらずにたゆとう雲、あれはわがいとしい人なのであろうか。
(伊藤博訳注『万葉集』角川学芸出版)
と詠んだ人麻呂の関心は山あいに雲のように漂う魂にあり、亡骸には示されていない。万葉集には多くの挽歌が収められている。万葉人にとって大切なのはあくまでも魂の行方であり、山をとりまいている雲や霧に死者の魂がのぼっていくと考えられていた。
もともと日本語に英語の「Nature」に相当する言葉はなかった。明治時代にこの言葉が入ってきた時、日本語の「自然(あるがまま)」という言葉があてられた。西欧人は自然を人と対峙する物理的な対象として、また征服すべき対象としてとらえてきた。そのような態度が自然の摂理を発見し、科学技術の発展をもたらし、今の工業化社会を築いてきた。一方、日本人は人と自然を明確に区別していない。西欧人が思い描く自然と日本人の自然とは違うのである。豊かな自然環境の中で自然と一体となって暮らしてきた日本人にとって、自然を物理的な対象としてとらえる考え方は必要なかったのだ。日本人の思い描く自然とは周囲の山や川、森、さらにそこに植生している植物や動物であり、しかも、それらすべてのものに人と同じように魂が宿るとして心を通わせてきた。それは日本人の美意識にも表れている。日本庭園にしても、盆栽、山水画、自然を詠んだ和歌や俳句にしても、そこにあるのは自然を冷静に観察する人の姿ではなく、草木や花、鳥などとのふれあいを愉しむ人の姿である。
このような日本人特有の自然観はどのように育まれたのだろうか。祖先が自然に手を加え、自然と対峙しながらも折り合いをつけ共生する生活を始めたのは縄文時代、最終の氷河期が終わる一万数千年前である。平和で安定した採集狩猟生活は一万年以上も続き、縄文土器や土偶に代表される精神性豊かな縄文文化を築き上げた。しかし、現代の日本人はDNA分析によると他の地域に住む人々に比べて東南アジアから東北中国・朝鮮半島まで、混血性が非常に高い。縄文人の血はほとんど流れていないのだ。縄文時代末期の人口は全国でおよそ7万6000人、しかも、稲作が伝来し主に伝播した近畿以西の人口は一万人足らずであった。それに対し、稲作に続いて伝わった金属器とともに大陸や朝鮮半島から渡ってきた人は弥生時代、古墳時代を通して100万人以上といわれている。縄文人は数で圧倒されてしまったのである。現代の私たちの生活の中に見る日本古来の食べ物や慣行、儀礼や神社の信仰は、水田稲作の起源である中国江南地方やそこから稲作が伝わった朝鮮半島の文化と、平地がほとんどない日本列島に暮らした土着の山の人々の文化の混淆だろう。
だが、岡本太郎は縄文時代の火焔土器に日本芸術の源流を見出したのである。岡本の鋭敏な感性は火焔土器に込められた縄文人の心性に日本文化の奥底に流れるものを感じ取ったにちがいない。それ以来、縄文文化に対する評価は見直され、今では縄文文化が基層となり、その上に弥生時代以降の文化が積み重なって日本文化が形成されたと考えられるようになってきた。
では、縄文人はどのような自然観を持っていたのだろうか。考古学者の小山修三は、縄文人の自然観として、縄文人は人間にとって特別に大切なもの、力のあるものをカミとして祀っており、カミを中心におき、人間も生き物も風、雨、太陽、月などの自然現象も精霊を祀ったカミをとりまく平等な存在とみなす、「円の発想」だと述べている。だから、人間はどんなものとでもお互いに友達同士になる。一種の精霊崇拝から生じたものだが、縄文人は自然界のすべてのものに畏怖、畏敬の念を持ち、尊敬と親しみを持って接していたのである。
角田忠信は、耳鼻科医として難聴の治療にあたるなかで日本人と外国人とで音を聞く時の脳の使い方に違いがあることを見出した。泣き、笑いなどの感情音、動物や虫などの鳴き声、小川のせせらぎ、波、風、雨などの自然音を聞く時、日本人は左脳(言語脳)で処理するが、多くの外国人は右脳(非言語脳)で聞くというのだ。つまり、外国人は自然音を単に音として聞くが、日本人は声として聞くのである。これは日本語と外国語の音節の違いによるのだという。日本語は母音で終わる開音節で、同じ発音でもいろいろな言葉があり、一つ一つの母音が多彩な意味を持っているため、母音は言語脳で処理される。一方、外国語の多くは子音で終わる閉音節のため、母音は非言語脳で処理される。感情音や自然音の音波構造は母音の音波構造と似ているため、母音を言語脳で処理する左脳優位の日本人はこれらの音も左脳で処理されるのだそうだ。周囲の山や川、森、さらにはそこに植生している植物や動物すべてのものに人と同じように心を通わせてきた日本人の自然に対する想いと通じるものがある。日本人は自然と対話をしているのだ。
しかも、日本人以外で母音を左脳優位で処理するのはポリネシア語圏のトンガ、サモア、ニュージーランドの現地語で育った人々だけだそうである。弥生時代以降にこれらの言語を持つ人々が日本語に影響を与えたとは考えられないので、この音認知の特徴は縄文時代以前に培われたものであろう。さらに、音認知の脳の特徴は6〜9歳までの言語環境によって左右される。日本人でも外国語の環境で育つと外国人と同じになり、外国人でも日本語の環境で育つと日本人と同じ脳の特徴を持つようになる。つまり、弥生時代以降、朝鮮半島や大陸から多くの人が渡来し、さまざまな生活様式や慣習、言語、文字などが持ち込まれ、おそらく縄文人が話していた言葉も大きく変わってしまったであろう。にもかかわらず、日本語そのものを変える言語環境の変化は起こらなかったのである。数のうえでは圧倒され、社会の構造や制度が大きく変容しても、縄文人は外来の文化を冷静に見極めて選択し、自らの価値観の中に消化吸収していったのだ。そこには自らの文化に対する縄文人の自信と自負が感じられる。縄文人の文化は外来文化によってその面影がわからないまでに形を変えながらも生き残り、現代に受け継がれているのだと思う。
日本の昔話には人と動物との交流が描かれたものが多い。昔話は、ある時代の文化が時の経過とともに不要なものは捨てられ、新しい要素が付加され、変形しながらも語り継がれ習い覚えられてきたもので、民俗学、文学、宗教学などで研究対象とされてきた。基層にある文化の根がその痕跡をとどめるものの一つに縄文人のカミであった動物がある。なかでも、動物が人間の姿になって人と交わる話は日本の昔話の特徴の一つだ。古事記の山幸彦と海幸彦の説話で、海宮で山幸彦の子を産んだ豊玉姫(とよたまひめ)は和邇(わに)だった。日本書紀、崇神(すじん)天皇十年九月の条、三輪山(みわやま)の説話で活玉依姫(いくたまよりびめ)のもとに通ってくるオオモノヌシノカミはヘビの化身である。罠にかかったところを助けられたツルが娘の姿になって恩返しをする「鶴の恩返し」はよく知られている。近代の作品にも動物との交流を描いたものがある。宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」では下手なチェロ奏者ゴーシュとネコやネズミ、カッコウ、タヌキの動物仲間との心温まる交流が描かれている。金子みすゞの詩、
「私と小鳥と鈴と」
私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のように、
地面(じべた)を速(はや)くは走れない。
私がからだをゆすっても、
きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴は私のように
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。
(金子みすゞ『金子みすゞ童謡集』角川春樹事務所)
この詩には、すべてのものに心を通わせる日本人の意識構造がよく表れている。現代のアニメ作品、宮崎駿監督の映画「となりのトトロ」では、サツキとメイの姉妹と森の主トトロとの交流が描かれており、日本人の精霊信仰的な自然観が表れた作品である。ここで大切なのは、トトロは人里離れた奥山に住まうのではなく、人里のクスの大木に住んでいることだ。
明治時代以降、日本人の自然との関わりは大きく変化した。一つは、生活全般において大量のエネルギーを投入できるようになったこと、一つは、ものの移動を通して地球全体の自然と関わりを持つようになったことである。もはや、日本人の自然との関わりを論ずるには、日本一国の問題としてではなく、全世界的な視点が必要になった。
蒸気機関の発明を契機に起こった産業革命の波は19世紀に全世界に波及した。石炭や石油などの化石資源を燃やしてエネルギーに変換し、さまざまな製品が生産されるようになった。さらに、20世紀初めにアメリカで始まった大量生産・大量消費の経済活動は、戦後、怒濤のごとく押し寄せ、日本をのみ込んでしまった。
現代はグローバル化の時代といわれ、世界中からモノが入ってくる。私たちの周りにはモノがあふれている。情報のグローバル化も手伝い、インターネットでモノを注文すると海外から航空便で品物が届く、そんな時代である。次から次へと提供される新しいものは人々の物質的欲求を刺激し、それを満たすことが幸福感につながっている。経済的要求に応じることができる限り、私たちは欲しいものを何でも手に入れることができる。大量生産・大量消費は、島国の中で自給自足の生活を送ってきた日本人のものに対する価値観や意識を変えてしまった。
毎日大量にモノが捨てられている。大量生産・大量消費の社会は大量のごみを生み出したのだ。大量生産によってモノの値段が下がり、修理したり、使いまわすより新しいものを買った方が安いとなれば、まだ修理すれば使えると思っていても捨ててしまうのだ。
「もったいない」という言葉がある。島国の限られた資源の中で暮らしてきた日本人にとってものは貴重だったのだ。不要になったものを捨てるのではなく他の用途に利用し、壊れても修理して使うのは当然だった。しかし、周りにものがあふれている現代、ものを大切に使う「もったいない」の言葉は死語になってしまった。
「『もったいない(MOTTAINAI)』を世界の共通語に」を提唱したのは、2004年にノーベル平和賞を受賞したケニアの人権・環境活動家ワンガリ・マータイである。彼女は2005年に初めて来日した時、この言葉に感銘を受けたという。地球上では毎日、大量の資源を投入してものが生産され、その一方で、二酸化炭素を含めて、大量のものが廃棄されている。その代償として、温暖化や砂漠化、森林破壊などの環境汚染や環境破壊が地球をむしばんでいる。砂漠化の進行を少しでも食い止めようと長年、アフリカで植林活動を行ってきたマータイは、「もったいない(MOTTAINAI)」の言葉に、3R「リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)」の精神と、モノに感謝し大切にするリスペクト「尊敬(Respect)」の精神を見出したのである。
地球の平均気温が上昇している。1880年から2012年の間に世界の平均気温が0.8℃上昇した。石炭や石油などの化石資源を大量に燃やしたため、大気中の二酸化炭素の濃度が高くなり、地球の温室効果が増しているのが主な原因の一つである。気温の上昇は日本でも起きている。東京の年平均気温は1880年の14.1℃に対し、2012年は16.3℃だった。日中の最高気温が35℃以上の猛暑日の日数は、1880年から1889年の10年間にたった1日だったのに対し、2008年から2017年の10年間には57日に増え、逆に、最低気温が氷点下に下がる冬日の日数は、754日から51日に減っている。極端に暑い日が増え、極端に寒い日が減っているのだ。
石炭や石油を燃やした時に排出される硫黄酸化物は、気管支炎や喘息など人々に健康被害をもたらし、さらに、硫黄酸化物は水に溶けるため酸性雨の原因となり、樹木の立ち枯れや土壌、河川、湖沼の酸性化を引き起こす。
人工的に合成した化学物質も環境に悪影響を及ぼす場合がある。農薬の一種であるDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)は環境中で分解されにくく、生物の体内に蓄積されやすいため、食物連鎖によって鳥類に濃縮され、繁殖率の低下を招いた事例は『沈黙の春』(レイチェル・カーソン、1962年)で紹介された。さらに、化学物質は自然界や生態系に対してだけでなく、人体にも悪影響を及ぼすことが、『奪われし未来』(シーア・コルボーン、1997年)で取りあげられた。また、有機リン系除草剤の一種であるグリホサート(N−ホスホノメチルグリシン)は、世界保健機関(WHO)の専門組織・国際がん研究機関(IARC)が2015年に発がん性のおそれがあると発表したにもかかわらず、日本では今でも使われており、化学物質の毒性や安全性に対する関心が低い。
これらの環境問題は人間のエネルギーを使った活動、すなわち、利便さと物質的豊かさを追求した活動が、自然界に大きな影響を与えた結果である。
このような問題について日本人も他人事ではすまされない。日本で使用する天然資源の55.5パーセント(2015年度)は輸入だ。エネルギー資源でみると日本は世界の3.6パーセントを消費しており、その94.5パーセントが輸入である。食料もカロリーベースで62パーセントを輸入している。資源を採掘すれば自然に負荷がかかる。採掘するにもエネルギーが必要である。食料を生産するにもエネルギーと水がいる。これらはすべて輸入相手国の自然に依存しているのだ。日本は自国面積の何倍もの自然に負荷を与えている。
反対に、日本で作られた製品のうち重量で27パーセントが輸出されている。輸出された製品がその国でどのように使われ、どのように処分されているのか、私たちはほとんど関心がないし知らない。日本では廃棄物を種類ごとに分別して収集し、再利用、再資源化できるものを除いた後、焼却によって減容、無害化できるものは焼却処理される。その他の廃棄物と焼却残渣は有害物が溶け出して環境汚染や生態系に悪影響を与えないように対策を講じたうえで埋め立て処分されている。しかし、製品の輸出先は日本のように廃棄物を適正に処理、処分できる能力がある国ばかりではない。むしろ日本のような処理を行っている国は少ない。先進国を除けば、廃棄物は大部分が埋め立て処分である。環境汚染などの対策を講じていない地域や、廃棄物の回収処分すらしていない地域もある。廃棄された日本の製品がもとで環境を汚染し、生態系に悪影響を与えているとしたら、やはり無関心ではいられないはずである。
人類の活動が地球の自然に影響を与えるほどにまで大きくなった今、人と自然との関わりが改めて問われている。地球の環境が破壊され人類の生存に適さなくなっても地球を捨てて他に行くところはないのだ。これからの人類に望まれるのは大量の資源を投入して活動する社会ではなく、人間の活動を地球の再生能力の範囲内に抑えた自然と共存する社会である。日本の自然は、かつては森林の伐採が進み、崩壊寸前にまで環境が悪化したこともある。しかし、崩壊には至らなかった。温暖で湿潤な気候は樹木の成長が速く、森林の復元力が強いという好条件に恵まれたこともあるが、限られた資源を上手に使い、祖先は閉ざされた環境にうまく適応したのである。そこから日本特有の風土と文化が生み出されてきた。人類はこれからの地球環境にうまく適応していけるだろうか。ここでは、これまでの日本人と自然との関わりと、その関わりを通して育まれてきた文化について見つめ、その特徴を拾い出してみたい。そして、現代の大量生産・大量消費の社会における自然との関わりについても触れ、今後の人類と自然との関わり方について考えてみたい。
10年前に会社を辞め教職に転身し、環境について教えることになった。それまでも装置の開発で環境とはかかわっていたが、地球の自然や生態系について、基礎的なことを講義していると、機械や技術といった視点から見ていたものとは違ったものが見えてきた。
すべてのものは「エントロピー増大」という宿命から逃れられない。「秩序ある状態は無秩序な方向に進む」という熱力学の法則である。生物でいえば老化である。宇宙もこの法則には逆らえない。放っておくと地球のエントロピーはどんどん増加する。よい例が月である。巨大衝突説によれば、月は巨大な隕石が地球に衝突し、その破片の一部から誕生したとされ、地球とは兄弟星である。しかし、40億年経過した現在の月は地球とは全く違った姿をしている。地球では、まず植物や植物プランクトンが太陽からのエネルギーを使ってエントロピーの低い糖やたんぱく質を合成する。それをほかの生物が次々に利用する。生物も何もしないとどんどん老化してエントロピーが増大し、死に至るので、外部から摂取した食物をエネルギーと栄養素に分解し、それを使って新しいものを合成し老化した部分に置き換えている。代謝である。増大に向かおうとする自らのエントロピーを先回りして新しく作り替えることで低い状態を維持している。生物学者の福岡伸一はそれを「動的平衡」と呼んでいる。それでも増加するエントロピーの速さには勝てず、やがて死がおとずれる。
地球全体としては、古くなったものを壊す、生物の場合は食べられることで増大したエントロピーを廃棄し、得られた物質とエネルギーを使って新たにものをつくり、エントロピーの低い状態を維持している。山火事で森林が焼失するのも暴風で木がなぎ倒されるのもその一部である。つくっては壊し、壊してはつくることで地球のエントロピーが増大し破局に至るのを防いでいるのだ。そのとき生成した二酸化炭素と水蒸気は大気が上空に運び、最終的に温度が下がりエントロピーが高くなった熱だけを宇宙に捨てている。
「生物は負のエントロピーを食べて生きている」とはオーストリアの物理学者エルヴィン・シュレディンガーの言葉である。生物は自らの分をわきまえ、お互いに共生し、ある時には食物連鎖によって食べられることで地球全体が一つのバランスを保っている。太陽から届いたエネルギーをものに変え、それを生物同士が受け渡しながら地球の中でうまく循環させているのだ。生物の種類が多く多様なほどお互いの接点が多くなりその仕組みは強固で柔軟なものとなる。地球は40億年かけてその仕組みをつくりあげてきた。その中で、人間だけが分を逸脱し、自然をそして生態系を壊している。人はできるだけ頑丈なものをつくって、増えるエントロピーに対抗しようとする。そして古くなると捨ててしまう。地球の全く逆の発想に会社員時代は気が付かなかった。
もう一つ自然と人との関わりについて考えさせられる出来事があった。東日本大震災である。その時、私は山口県の宇部にいた。テレビで津波にあらわれた宮城県の閖上海岸の光景を見たとき私の中の記憶の一部が削り取られたような衝撃を受けた。私は小学生の頃を宮城県の仙台で過ごした。閖上海岸には両親がよく連れて行ってくれた。きれいな松林と夜には満天に輝く星空が印象に残っている。幼い頃の思い出のひとつだった。その思い出の場所が突然消えたのだ。後になって、その時の衝撃こそが無常観だと実感した。
日本は自然の豊かな国だ。森の木々は四季折々の装いを見せ、木の実や果実など豊かな恵みを提供してくれる。そんな自然も東日本大震災のように時として猛威を振るいすべてを無に帰してしまう。そればかりか多くの人の命まで奪ってしまう。しかし、これも地球の代謝活動の一部である。人の力ではどうすることもできず、天災として無理やり納得するしかない。
島国という限られた空間の中で、そして恵み深いが移り変わりの激しい自然の中で暮らしてきた日本人は自らの分をどのようにわきまえ、自然と関わってきたのだろうか。人と自然との関わり、そしてそこから育まれた風土、文化を辿ってみたい。そんな思いにさせられた出来事だった。
著者はエンジニアとして長く務めたのち、大学で環境について教えるうちに、会社員時代には気がつかなかった、地球がバランスを保っている仕組み、生物たちが自らの分をわきまえ、共生し、エネルギーを循環させている一方で、人間だけが分をわきまえず、自然環境と生態系を破壊していることに思いいたる。
また、幼少期を宮城県仙台で過ごした著者は、両親とともによく訪れていた閖上海岸が、東日本大震災で一変するのを目の当たりにする。慣れ親しんだ景色、幼少期の思い出が一瞬で消え去ってしまった時、無常観というものを強烈に思い知ることになる。
自然豊かな島国、日本。木の実や果実などの恵みを与えてくれる自然は、時に猛威を振るい、全てを一瞬にして無に帰してしまう。そんな自然とともに暮らしてきた日本人は、どのように自然と関わり、折り合いをつけてきたのだろうか。そして、どんな風土、文化が生まれてきたのだろうか。
自身の経験から突き動かされるようにして、日本人と自然について考察した一冊。