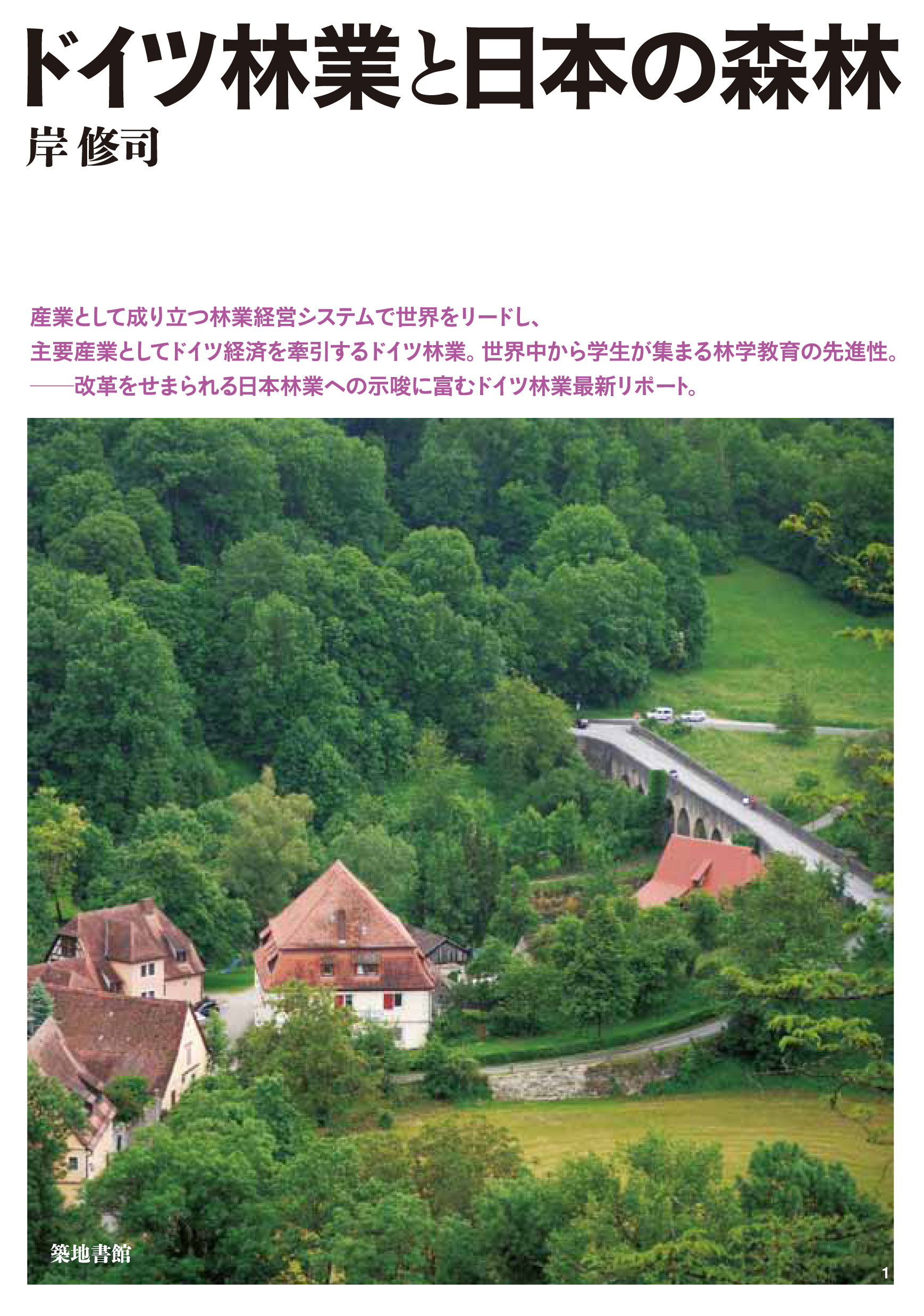スイス林業と日本の森林 近自然森づくり

| 浜田久美子[著] 2,000円+税 四六判並製 224頁 2017年7月刊行 ISBN978-4-8067-1541-2 氷河に削られた痩せた国土、急峻な山国のスイスで、 豊かな林業が成立しているのはなぜか。 徹底して「自然」を学び、 地域社会にとっての森林価値を最大限に上げる「近自然森づくり」を進めるべく、 一斉人工林から針広混交林へと移行したスイス林業。 その担い手を毎年日本の森に招き、その取り組みを地域の森林で活かそうと 奮闘を続ける日本の林業者たち。 両者を長年取材してきた著者が、日本の森林と林業の目指す姿を探る。 |
浜田久美子(はまだ・くみこ)
1961年、東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、横浜国立大学大学院中退。
精神科カウンセラーを経て、木の力に触れたことにより森林をテーマにした著述業に転身。
森とひとの関わりを取材している。スイスへもたびたび取材に赴き、スイスの実践的な林業教育を日本で応用できないかと模索している。
東京の自宅とは別に、長野県伊那に国産材30種以上の樹種を使った木の家を建て、休日には山仕事のかたわら薪を作り、ストーブ、ボイラー、風呂で活用する日々を送っている。
著書に『森をつくる人びと』『木の家三昧』(以上、コモンズ)、『森がくれる心とからだ』(全国林業改良普及協会)、『森の力』(岩波書店)、『基礎から学ぶ森と木と人の暮らし』(農山漁村文化協会、共著)、『スイス式[森のひと]の育て方』(亜紀書房)などがある。
はじめに 木を使うこと、森をつくること
1 木を使う暮らし
2 木を使っても森づくりにつながらない
3 森の三方よし──近自然森づくり
4 社会の基盤となっている「近自然」の考え方
序章 森と人の豊かな関係を求めて
1 雑木林のような家を建てる
2 「使うが鍵」のジレンマ
3 針葉樹も広葉樹も育てる国、スイス
4 「どちらか」ではなく「どちらも」へ
1章 近自然森づくりの考え方
1 太陽と森と近自然
2 光の調整
3 「自然」と「コスト」の関係
4 「森林のプロ」への道
5 理想像から目標、そして手段へ
6 変化は小さく
7 観察! 観察! 観察!
8 収穫がそのまま「手入れ」に
2章 森の見方
1 現在──あなたは誰?
2 過去──どこから来たの?
3 未来と目標──どこへ行くの?
4 目標へのたどり着き方
5 育成木を決める
6 育成木のライバルとサポーター
7 下僕と呼ばれる大事な木々
3章 ロルフのワークショップ
1 フォレスターの対応力
2 虚心坦懐に森を見る
3 育成木とその周辺
4 目の前の森を生かす
4章 環境と経済が両立する仕組み
1 4つのポイント
2 森林管理と森林経営
3 木の成長量分で木材生産
4 森林をめぐる法律
5章 森の仕事と教
1 それぞれの役割
2 全体を俯観する
6章 日本の針葉樹人工林での近自然森づくり
1 ゼロか100かではなく
2 現行制度の中でできること
3 観察しながら変化を促す
4 近自然で若木の手入れ
5 過去に学ぶ
6 山の都合と人の都合
7 鍵を握る現場の理解者
7章 広葉樹が主役の地域で
1 豪雪地帯で──利賀
2 地域の森の豊かさを生かす
3 人材育成の一歩
4 「環境林業先進地」をめざして
5 広葉樹の木材生産
6 匠の里──飛騨
7 森と街からのアプローチ
8 広葉樹でまちづくりを
8章 まかれる種
1 「いい山」にするために
2 自治体にも変化の兆し
3 現場で学ぶ体制づくり
4 実習で変わる高校生
5 自分たちも自然の一部
6 つながる、つなげる視点
9章 地域に根ざす人
1 地域の中の森林
2 日本版現場フォレスターをめざして
3 枠組みの転換
4 森林管理への一本道
5 集落全体の中での管理
終章 「気持ちいい」森で生き延びる
1 新しい価値観
2 林業を誇りに
3 「やらない選択」もあり
4 「考え方」のトレーニング
5 少しずつ試すところから
おわりに
1 木を使う暮らし
「地域の木で家を建てて、休日の山仕事で出てくる材を燃料に使えるようにしよう」。この構想のもと、わが家が完成したのが2000年早々。それから17年がたつ。
当時、私は日本の森──人工林も同規模ある里山も──の手入れがされないのは「木を使わない」暮らしが当たり前になったことが大きな一因だと思っていた。正確に書けば、日本でも木材は大量に使ってはいたが、その大半が外材になっていた。1990年代は輸入率がほぼ80%前後で推移し、最高の輸入率になったのはわが家が完成したその年、2000年だ。輸入率は82%。国産材の占める割合はわずか18%にまで落ちていた。曲がっていたり節があったりと品質の高くない木々の行き場がないのはもちろん、「こんなに太くてまっすぐなのに……」と思う木々でも、樹種によって見向きもされず、間伐されてそのまま森の中に転がされている時代だった。
人工林では補助金で間伐が推進されてはいたが、当時は「切り捨て間伐(伐った木を運び出さずに林内に残す間伐)」が主流だった。日本中に広がる間伐手遅れ問題が山積する現状だったので、「切り捨て」はやむをえない策であるとは思っていた。林内に光が入らないことには、木々が育たないだけでなく、多層に重複している森の公益的機能が低下するのだから、材を捨ててでも伐ることを優先するのはやむなし、と。
ただ、当面は最低限の間伐が進むことが緊急事態ではあるとしても、補助金頼みでは将来が不安だ。森がずっと良い状態に維持されるためには「伐ったら使う」という循環の輪がまわる必要が人工林ではある。森づくりと利用、このセットが連動することが欠かせない、と当時強く思っていた。
何より、数十年と育った木々が何にも利用されないでただ伐られるのは、状況は「やむなし」と理解していてもせつなくてもったいなかった。ごくごく単純に目の前に転がる木々をどうにか使いたかった。その昔、木が燃料として利用されていたことは、山とのつきあいが欠かせなかった時代にはとても理にかなっていたのだとよーくわかるようになっていく。
今ならば、再生可能エネルギーの1つとして不思議に思われなくなった木質燃料だが、わずか20年近く前は、木の燃料は遠い昔話になってしまっていた感が強い。いや、一部では贅沢品の地位にあった。薪ストーブは、憧れの別荘、田舎暮らしの重要アイテムの筆頭に置かれているものだったから。しかし、日常的に木の燃料が考えられるような気運ではなかった。そもそも、使うには設備がいる。その設備がふつうの住宅から一掃されて久しいので、「使いたくても使えない」のが実態だ。だから、わが家に生じた住宅問題を機にその設備を組み込んだ家を建ててみることにした。個人レベルでできることをしてみようと思ったのだ。
やってみて、個人のライフスタイルとしての充実感は、素晴らしいものだった。年間にすれば数えるほどにしかならないものの、休日の山仕事をして、そこで出てくる材をこつこつ薪にして、ストーブ、ボイラー、風呂と3種の薪設備で利用している。日々、少しずつやる薪割りはエクササイズのようになり、東京に滞在が長引くと「つまらない」と思うほどになった。山仕事は、最初は家族だけで、途中から仲間と地域の森の手入れをすることになったので、地域ぐるみの活動の充実感も加わった。
木を燃料にする良さという点では、文句なく太鼓判を押せる。単なるエネルギーの変換ではなく、ライフスタイルそのものが変わった。もちろん、薪、という形態は都会での広がりには適さないが、山が間近にある地域は日本中にあり、そこでは大いに可能性があると確信した。何も薪だけで日本中のエネルギーをどうこうしようというのではないのだから、できるところがやってみるのは理にかなう。これは、ある意味では2011年の東日本大震災以降、現実として広がっている。
2 木を使っても森づくりにつながらない
しかし、思っていなかった事実にもぶつかった。木を使うことと森づくりとは「自動的に」連動するわけではない、ということに。
この暮らしを始めるとき「利用が進めば森づくりも進む」と私は考えていた。おそらく、今、日本中で木を使うことが推進されている中で、多くの人は私と同じように受け止めていると思う。そのように喧伝されているし。しかし、そうなるためには、当たり前だがきちんと「筋道」が必要なのだった。計画と言ったらいいか。
こう書けば、「計画がないのか?」と問われることになる。計画はないのか?
あるような、ないような。そんなので森を扱っていいのか!? と驚かれそうだが、身近な里山では、実はこれでもできてしまう。「伐ってほしい」という所有者の希望で伐ることだけが主眼の作業だからだ。それでも、まったく何もせずに放置されている状態よりはマシ、と考えて作業をしていた。そして同じ作業をするならば、利用する方がいいのだから、という流れでこれが続けられてしまう。実際に、間伐で林内に光が入るようになると、後にわさわさと樹木も草も生えてくる。その中から将来森と育っていく、と希望的に考えていた。何を育てる、という明確な目標がなくても、できる作業がこうして実利を伴ってあるのだった。
そもそも、里山は明確な将来の森の姿を意識して維持されてきたわけではない。利用が持続することこそが目的だったから、その結果、森の姿がある程度決まった形になるという順番だ。
去年採りすぎたから今年足りない、だからヨソから買おう、というようなわけにはいかない時代には、毎年毎年の必要な利用のためにどうするか? は大きな問題だ。だから、たとえば草を刈り始める日が厳格に決められたり、使える刃物が決められたり(形状や刃の長さまで)、と「制限」がしっかりあったのだ。好き放題使い放題では、枯渇してしまう。それほど、みんなが里山を酷使していた時代が当たり前にあった。持続的な利用のために、みんなで抑制をしてバランスをとる。その結果として、里山は循環していたのだ。それでも、人口の増加や社会の発展で、たいていは利用過多で負荷がかかることの方が多かった。
現代の里山には、循環の要となる決定的な利用がない。そして、放置され樹木は大きくなり林内が込み、結果植物相が単調化し、生物層も単調化していく、という流れになっていた。だから、放置よりも、たとえ将来の森の姿が決まっていなくとも、度を越す利用でなければ里山は再び多層化する方向に向かう、と希望的に思っていた。何しろ、昔と違い使う人がごく少数なので、小さな面積でのごく小集団での利用では、樹木や植物の成長力に対して利用の方が圧倒的に少なかった。薪ユーザーは、劇的に増えていったりはしていなかったから、単純な足し算引き算で、まだまだだ、と思っていた。
だから、将来の明確な森の姿を決めることがなくとも、作業と利用は続けられていく。
人工林の場合は、別な背景がある。戦後、人工林の拡大造林政策(広葉樹を伐って針葉樹の人工林に変えていく)が大々的にとられた中で、多くの新しい人工林が作られている。人工林割合は全森林の41%。人工林は、一般的には1haに3000本程度を標準にして針葉樹苗木を植林して、下刈り、収穫までに2〜3回の間伐、モノによって枝打ち、40〜50年で収穫……というステップが作られていたので、放置によって途中のステップが崩れていても、その流れに戻る感覚でまずは間伐、とやるべき作業が出てくる。
そして、針葉樹人工林は木材生産のためと決まっていたので、「計画」はマニュアルにのっとってある。「森の将来の姿は?」とあらためて問うこと自体がない(もっと綿密に細かく計画し、目標を持つ林業家はいるが)。だから、人工林に対しては、まさしくさまざまな手遅れている作業をすることが、そのまま「森づくり」と称される。私もそのことに大きな違和感を持っていたとは言えない。ただ、先々のことを思うとき、これらの人工林は収穫後はどうなるのだ? とずっと思っていた。人工林を繰り返しつくり続けることは、どこまでできるものなのか? と。
いずれにしても、私自身が関わる森の明確な姿を決めることなく(正確には決められる立場でもないのだが)、作業と利用だけで十数年続けていた。
3 森の三方よし──近自然森づくり
でも、だから、目からウロコが落ちた。スイスで実践されている「近自然森づくり」を知ったとき。
近自然森づくりは、木材生産と環境の向上の両方を経済性を無視せずに達成することを求める森づくりだ。木材生産だけを考えてはいけないし、環境面だけを考えるのでもいけない。経済性を無視してやみくもに税金を投入するのもいけない。いけない、というよりは、このどれかが欠けても合理的ではない、ということだ。森をつくる作業は、経済的な整合性のもとで常に何かしらの木材を生産すると共により良き環境・景観向上に資するようにするのが「近自然森づくり」の合理性だった。そして、その3点が押さえられることで、森と人ともどもにプラスを得るという道筋。
「森における三方よしではないか」と思った。「三方よし」は近江商人の心得とされていたもので「売り手よし、買い手よし、世間よし」といって売り手と買い手が共に満足し、かつ社会貢献もできるのが良い商売であるとしていた。「近自然森づくり」は、「人よし、森よし、地域よし」という具合ではないかと思ったのだ。
そう、同じ作業をするならば、すべてにプラスがいいに決まっている。自分たちの薪を得ると同時に、その森の木々が将来にわたって良い木材に育ち、景観も多様で公益性が高まる、そして、誰かだけが得したり損したりしない、そんな欲張りなことを要求するのが「近自然森づくり」に思えた。
あらためて書けば、ここでの「良い木材」は薪などの木質燃料をさすのではない。燃やしてしまう木材は、確かに資源としての材だが、利用という点でいけば最終段階の材だ。建築や家具などに使った後の、残る材から得て、最終的に何にも利用できないところまでいって「燃やす」というのが、もっとも資源を無駄にしない使い方になる。だから、扱う森の中で、将来「良い木材」として育てられそうな木を育成木(ドイツ、オーストリアでは「将来木」と呼ばれている)として決めていく。その育成木を育てるために何をどうするか? という流れで作業工程は決まっていく。森を多段階で利用できるようにするには、最初の計画が肝心なのだ。
その育成木を育てる中で、育成木にとって邪魔な木が出てくる。それを伐ることで必ず材が出てくる。燃やす木材は、それらから利用することになる。森の木々を最初から全部燃料として扱うのではなく、将来にわたって太く大きく育てる木も混在させるのだ。そして、その将来にわたって育てる育成木は針葉樹だけがなるのではない。針葉樹か広葉樹かの選別が問題なのではなく、その森で安定して育つ樹木は何か? が重要になる。そこの自然に適する樹木の中で、用材として将来性のあるものをできるだけ育てる……。将来性
といってもスイスでの木材の収穫は100年を超すスパンなので、簡単に予測ができるものではない。
また、森の中で1種類だけの樹木の単調さは病気や害虫、災害に見舞われたときに集中して被害を受ける可能性が高くなるので、できるだけ多種の木材を生産するようになっている。そのリスク分散は、将来性に対してもそのまま使われるものだった。自分たちが存在しない将来に、今は重視されていない木の価値が高まっているかもしれないからだ。そこでも、木材生産としても環境面としても両方にかなうように思考され、選択されていく。
4 社会の基盤となっている「近自然」の考え方
「近自然」は英語で書くとClose to Nature となり、「自然に近づく」と訳される。自然が自然のままであることではなく、人が自然に近づくことで人が必要なものを得ていこうとするあり方、考え方をさしている。自然に近づいて自然に逆らわずに極力得るものを増やすために求められるのは、徹底して自然を学ぶことだとされている。「自然を知れば知るほど、コストが下げられ手間が省ける」というのがスイスフォレスターの常識になっている。
ちなみに、スイスでは近自然はすべてのジャンルの基盤となる考えになっている。森づくりだけでなく、川づくり、街づくり、教育やビジネスなど社会の基盤で、自然の仕組みから学ぶことが基本になる。自明のことではあるが、自然のキャパシティーを超えて自然に負荷をかければ、いずれ破綻する。持続可能性という言葉がさまざまに使われるが、具体的に持続可能にしていくための基盤として「近自然」はスイス社会に浸透しているのだ。
大事なのは、破綻を恐れてガマンが強要されたり、節約を強いられる、というようなものではないこと。ガマンは、持続せずにいずれ破綻する、という現実に根ざしている。だから、近自然の考え方による持続可能性は、豊かさと発展と共にある。ただし、その豊かさと発展は「今を生きている人間だけ」を指標にはしないのだ。人間(社会)も自然全体も、共に将来にわたって豊かに。その最大公約数がどこになるか、の折り合いをつける考え方が、近自然だ。
その近自然が社会のすみずみまで実践されるために、古くからの職業教育がいかに効果的か。森に関して言えば、現場技術者がステップアップをしてフォレスターになる仕組み、森林所有者との密で長年にわたるコミュニケーション、社会全体への普及活動、そもそも森林の重要性を全市民が理解するために小学校で必ず受ける森林教育など──近自然森づくりを知っていくことは、スイスの社会のあり方を知っていくことでもあった。
日本とは異なる社会システムを持ち、異なる国民性であること、何より、拠って立つ自然が大きく違うことは、言うまでもない。だから、スイスで実践されていることがそのままそっくり日本でうまくいくと思ったのでは決してない。
ただ、スイスだからとか日本だからという、国や地域を超えた普遍性が「近自然森づくり」にはあると思ったのだ。自然に逆らわずに、極力自然を利用させてもらうにはどうするかという具体的な実践は、国や地域を超えて人類社会が抱えている命題だからだ。自然を阻害すれば人間にとってメリットがない、という一点を決して外さない。そのために自然を学び、自然を理解しようとし続け、その中からできることを探して実践する、という姿勢は、謙虚であると同時に、とても実用的だと私は思ったのだ。
今、日本では戦後以来最大の木質燃料利用の波が訪れようとしている。木質バイオマス発電施設の計画が日本中に100をくだらない状況にある中、「未利用材」という名のもとに林内の残材(確かに私がもったいないと感じていたものだが)のみならず、放置されていた山々を一気に利用する策としても考えられている。人工林だけでなく、里山も奥地の山々も。
あらためて書きたい。使いさえすれば森づくりになるのではない、と。私自身が漠然とそう思ってしまっていたことを考えれば、「使うことはいいことだ」となるのはたやすいと思えてならない。大面積に効率化だけが特化していくことを本当に恐れる。
しかし、利用が大事なことはゆるがない。ようやく利用の循環の輪ができようという機運である今、本当の循環にするためには何をしたらいいのか? あらためて確認したい。さらに暮らしのそばにある里山の利用が、暮らしのレベルで広がる可能性も大きくなっている。田園回帰という言葉が出てきたように、I/Uターンで自然に近い暮らしを望む人が増えている。もし、「森の三方よし」を知っていれば、燃料だけにとどまらず多様な森の構成と多様な利用とを連動させることで、人にも森にも地域にも経済的でより豊かにできる可能性が広がる。
この本は、20数年にわたりスイスで近自然森づくりを実践しているフォレスターの日本におけるワークショップを中心に、そもそもの「近自然」の考え方と具体的な近自然森づくりについて紹介している。ワークショップでは日本の各地で「ただ作業しているだけではなく、本当に森をつくるには?」「人工林が成立しないまま放置された森はどうしたらいいのか?」「補助金を使わざるをえないが、現行の補助金を使いながらも将来にも良い森づくりに結びつけたい」などと現場で悩む人たちに出会った。
日本中で、同じような悩みや壁にぶつかっている人たちがいると思う。自分のふるさとの山々が、気持ち良く手入れがされ、かつ、良い材が育ちながら日々の燃料のみならず、暮らしにいろいろ利用される……さまざまな人が地域の自然に向き合いだしている今、「私たち」のふるさとの森がそういう豊かなものになるための一助となれるような1冊になっていることを願いつつ。
100年、200年先の木材市況など、誰も予測できない。自分たちがコントロールできない100年先の木材価格を当てにして、材木を生産するなど、ナンセンスではないか。日本に比べ、圧倒的に手厚い林業従事者への給与や社会保障を実現しつつ、小規模林業が成り立つスイスは、どのような仕組みを持って、そうした困難な条件を乗り越えているのだろうか。
スイス林業の現場で活躍するフォレスターに同行し、日本の様々な森づくりの現場をていねいに取材しながら、これからの日本列島の森づくりの指針―――生産林としてもレクリエーション林としても美しい森が、100年スパンで見て、最も生産性が高い森である―――を鮮やかに描く。
森づくりを深く取材しながら、市民としての視点を失わない著者だから書けた本書は、著者の家の内装を施工した有賀恵一さんの共著書『樹と暮らす』と併読していただくと、読書の楽しみが倍加します。