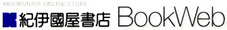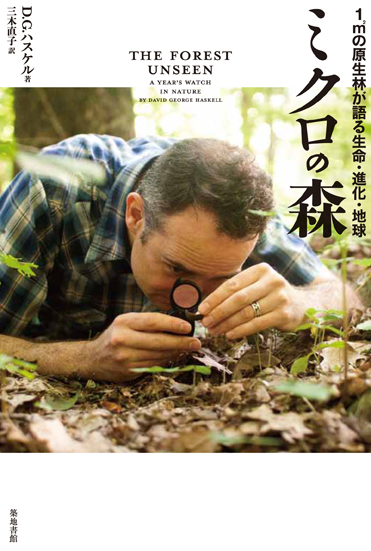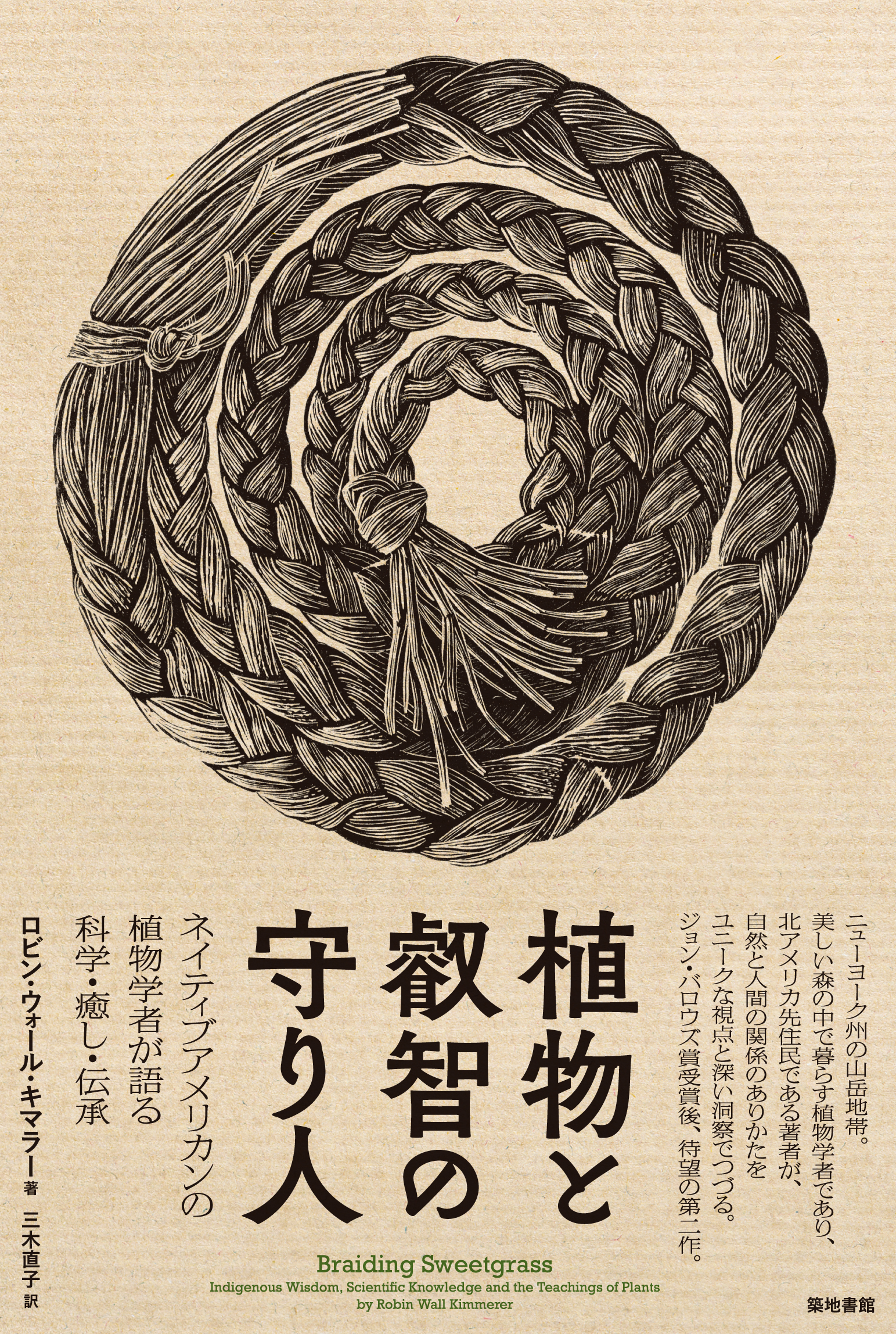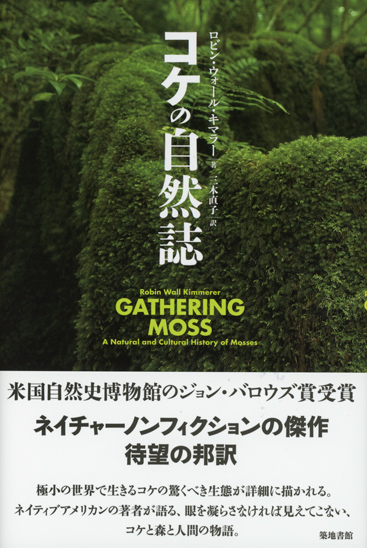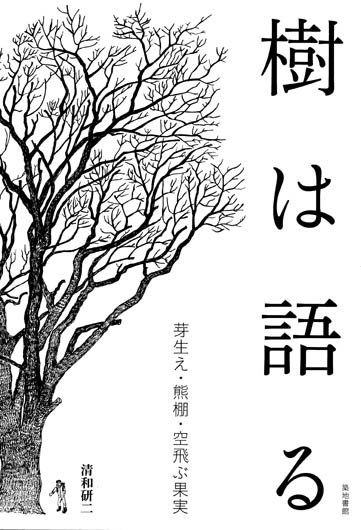�X�͉̂� �A���E�������E�l�̊W���ʼn����X�̐��Ԋw
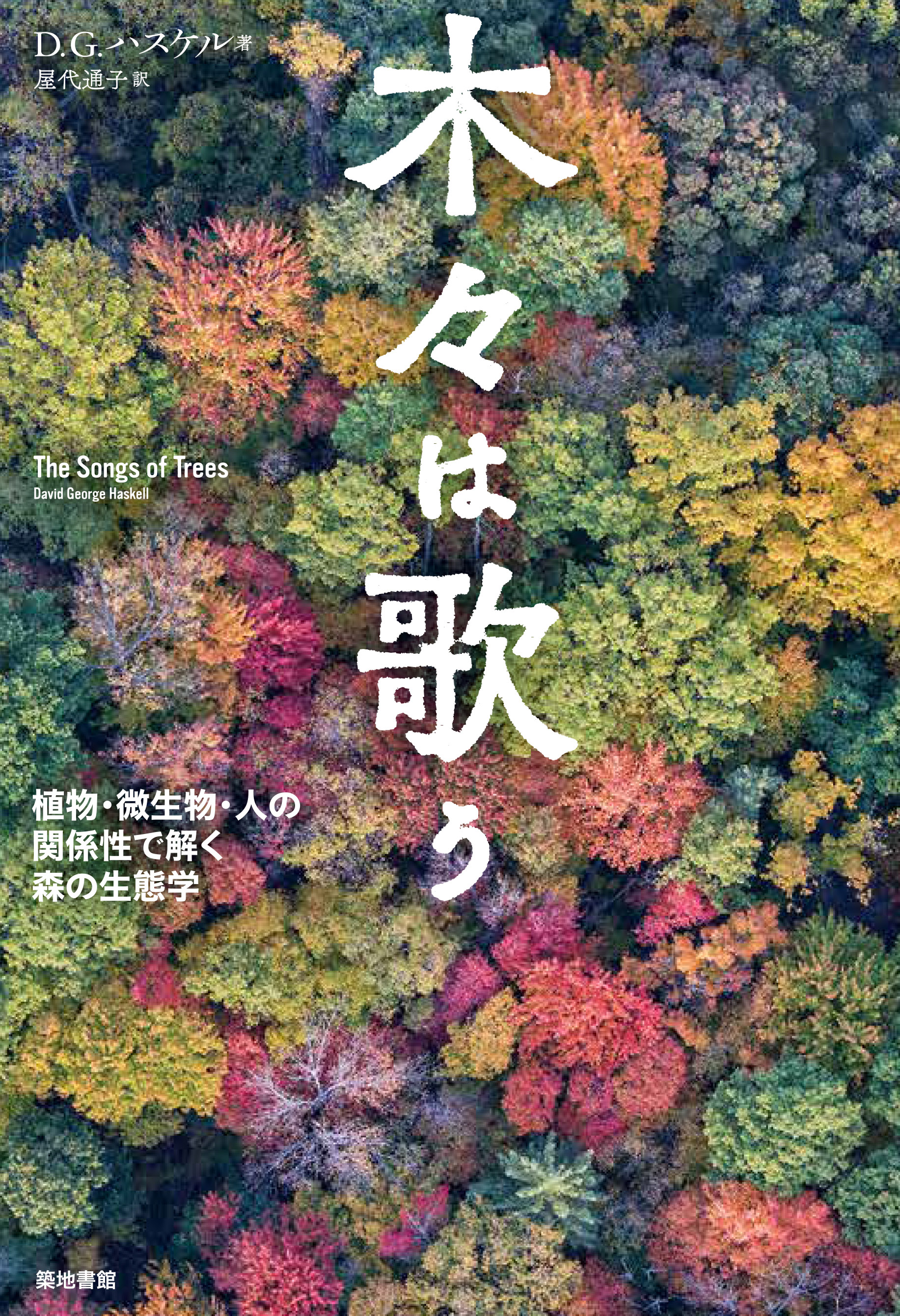
| D.G.�n�X�P���m���n�@����ʎq�m��n 2,700�~+�Ł@�l�Z���㐻�@368�Ł@2019�N5�����s�@ISBN978-4-8067-1581-8 �W�����E�o���E�Y��܍�A�Җ]�̖|�� �A�}�]���̐�Z���̐X�тւ̐[���q�d�ƐX�̍\�����Ƃ��Ă̊W���A �C�X���G���ƃp���X�`�i�̃I���[�u�_�Ƃ̓`���Ɖ��v�A ��s�s�j���[���[�N�̂P�{�̊X�H�����猩���Ă���R�~���j�e�B�̎p�A 400�N�O���疽���Ȃ����{�̖~�͂Ɍ���l�Ǝ��R�\�\�\ �P�{�̎�����������A���A�P���m�A�X�A�l�̕�炵�ցA ���j�E�����E�o�ρE���E���Ԋw�E�i�����ׂĂ����݂Ɋ֘A���Ă���B �������鎩�R�E�̕��G�őn���I�Ȑ����̃l�b�g���[�N���A ������āA�k���ʼnȊw�I�Ȋώ@�ŕ`���o���B [���E��] �����ԕ����Ă����{�B �l�Ԃ�����܂ŁA���̒n��Ɏ��������̋��ꏊ��^���Ă���Ă��� ���̐����l�b�g���[�N��f�₳���Ă������Ƃ��A�܂������ɍ������Ă���B �f���B�b�h�E�n�X�P�������̊j�S�Ɋ钮�f��̉��Ɏ��������āA �������炠�ӂ�o�����Ɖ��y�Ɏ����X���Ăق����B �\�\�w�������̒m��ꂴ�鐶���x���҃y�[�^�[�E���H�[�����[�x�� ���҂��E�F�u�T�C�g �{���ɏo�Ă���T�E���h������A���Ȃǂ̃J���[�ʐ^���ς邱�Ƃ��ł��܂��B �����{�o�ϐV��7/6�i�y�j�Ǐ������Љ�����܂����B �M�҂͒����~�ώ��i�_�ˑ�w�����j�ł��B |
�f���B�b�h�E�W���[�W�E�n�X�P���iDavid G. Haskell�j
�A�����J�A�e�l�V�[�B�Z���j�[�ɂ���T�E�X��w�̐����w�����B
�W�����E�T�C�����E�O�b�Q���n�C���L�O���c����t�F���[�V�b�v��^��������B
�I�b�N�X�t�H�[�h��w�œ����w�̊w�m���A�R�[�l����w�Ő��Ԋw�Ɛi�������w�̔��m�����擾�B
��������Ƃ�ʂ��āA�����A���ɖ쒹�Ɩ��Ғœ����̐i���ƕی�ɂ��ĕ��͂��s���A�����̘_���A�Ȋw�Ǝ��R�Ɋւ���G�b�Z�C�⎍�Ȃǂ̒���������B�����́A�Ȋw�A���w�̈���A���R���̂��̂��v������Ƃ���֍L�����Ă���B
�O���w�~�N���̐X�x�i�z�n���فj�́A�s�����b�c�@�[�܍ŏI���ƂȂ����ق��A���ۃy���N���u�E�Z���^�[�̑I�o����E. O. �E�B���\���Ȋw���w�܂Ŏ��_�ƂȂ�A�S�ĉȊw�A�J�f�~�[�̍ŗD�G�}���ɂ��I��Ă���B
����ʎq�i�₵��E�݂����j
���Ɍ����{�s���܂�B�D�y�ݏZ�B�o�ŎЋΖ����o�Ė|��ƁB
��ȖɁw�V���[�}���̒�q�ɂȂ��������A���w�҂̘b�x��E�����A�w���ƕ����x�w�n�̎��R���x�w�O����̃E�\�E�z���g���Ȋw����x�i�ȏ�A�z�n���فj�A�w�i�`�������E�i�r�Q�[�V�����x�w�����T���ɕς���x�i�ȏ�A�I�ɚ������X�j�A�w�s�_�n���x�w�}���A�E�V�r���E���[���A���x�i�ȏ�A�݂������[�j�ȂǁB
���{��łւ̏����\�ٓ����̖̗t���ے��������
�܂�����
Part1
�Z�C�{ Ceibo �n��50���[�g���̐��Ԍn
�G�N�A�h���A�e�B�v�e�B�j�����
���0�x38��10�E2 ���o76�x8��39�E5
�t�̌��t
�V��̌�
�X�̒��̑��l��
�����ȋ��҂���
�W�c�ɐ��������
�X�ɗn�����ސ��삽��
�Ζ��̖���y�n
�A�}�]���̐�
�o���T�����~ Balsam Fir �X�͎v�l����
�I���^���I�B�k���A�J�J�x�J�t�H�[���Y
�k��48�x23��45�E7 ���o89�x37��17�E2
������ׂ�ȃA�����J�R�K������
���̋L���Ɩ������ɂ����閲
�������o���T�����~�̋L��
�Θb����A���ƃo�N�e���A
�y�̂��Ă閧�₩�ȉ�
�ƏW�c�̂����܂��ȋ��E
�l�b�g���[�N�\�����̍����I�Ȑ���
���Ձ\�є�E�����E�؍�
�����h�T�b�g�\�k�̐X�̓y��m��
�j�t�ƍ��Ɣ������ƋہA�����Đl��
�T�o�����V Sabal Palm ���l������
�W���[�W�A�B�A�Z���g�E�L���T�����Y��
�k��31�x35��40�E4 ���o81�x09��02�E2
�o���A���̃R�~���j�e�B
����݂Ȃ��ς��Â���n
���Ƃ����g�ɏ��T�o�����V
���ɐ��߂āA���J��������
�A�J�E�~�K���̌Â��C�݂̋L��
�g�̖A�̔��i�������j�\�C�̔������̃R�~���j�e�B
�v���X�`�b�N�����������
�C�ʏ㏸�����
�C�ӂɐ����錫�҂ƂȂ邷��
�g�l���R Green Ash �|���߂��鐶�������̐��E
�e�l�V�[�B�A�J���o�[�����h�����A�V�F�C�N���O�E�z���[
�k��35�x12��52 �E1 ���o85�x54��29�E3
�R���\�L�N�C���V
�S���\�g�`�m�L
�T���\�~�\�T�U�C
�U���\�K���K���w�r
�W���\�̓�
10���\���������̒ʂ蓹
11���\���������̐���������
12���\���X�f
�P���\��q�̂�肩��
�Q���\�|����Ƃ�
�ŏ��̒a����
��x�ڂ̒a����
���� �~�c�}�^ Mitsumata ���Ɛ_�̋L��
�z�O�s�A���{
�k��35�x54��24�E5 ���o136�x15��12�E0
Part2
�n�V�o�~ Hazel ���Ί펞��̐l�X��{��
�X�R�b�g�����h�A�T�E�X�E�N�C�[���Y�t�F���[
�k��55�x59��27�E4 ���o3�x25��09�E3
���̍H�����Ăъo�܂�������
�n�V�o�~���x������
�̋��т��z�v�̖����~��
�n�V�o�~�ƐΒY�ɂ���鉊
�W����������
�Z�R�C�A�ƃ|���f���T�}�c Redwood and Ponderosa Pine �X���킽�镗�����Âƌ�����Ȃ�
�R�����h�B�A�t�����T���g
�k��38�x55 ��06�E7 ���o105�x17��10�E1
����̍���
���𞀁i���j���A����j�t
���̋ꂵ�݂̉�
�ߐ����_
�Ђ͐X�т̎p��ς���
���Ɖ��Z�R�C�A
��ɍ��܂ꂽ�����̗��j
�ӂ��̐j�t���̐���
�����l�b�g���[�N�ɑ�����^��
���� �J�G�f Maple ��{�̃J�G�f���a����
�m�T�n�\�e�l�V�[�B�A�Z���j�[
�k��35�x11��46�E0 ���o85�x55��05�E5
�m�U�n�\�C���m�C�B�A�V�J�S
�k��41�x52��46�E6 ���o87�x37��35�E7
�J�G�f�m�T�n�\�~�A�������ȕω��̉�������
�J�G�f�m�U�n�\���@�C�I�����̉��F
�J�G�f�m�T�n�\�l���A���J�̉�
�J�G�f�m�U�n�\�������̂����
�J�G�f�m�T�n�\��t
�J�G�f�m�U�n�\�w�ʼn���
�J�G�f�m�T�n�\��������k�肷�鏬�}
�J�G�f�m�U�n�\�̑��̐l��
�J�G�f�m�T�n�\���}�̂Ȃ��̃��Y��
�J�G�f�m�U�n�\���𐁂��Ԃ���
Part3
�q���n�n�R���i�M Cottonwood �����̖Ɛ�ƕ����߂��鐶���̃l�b�g���[�N
�R�����h�B�A�f���o�[
�k��39�x45 ��16�E6 ���o105�x00��28�E8
�ӂ��̐삪��������R���t���G���X����
���H�ɎT����鉖�Ɛ�̐���������
�r���I�Ȏ��R
���R�ƔR
�l�X�Ɛ��������W���ꏊ
�삪�l�X�̈ꕔ�ɂȂ�
�}���i�V Callery Pear �X�H���̓R�~���j�e�B�ւ̓����
�}���n�b�^��
�k��40�x47��18�E6 ���o73�x58��35 �E7
�̈ꕔ�ƂȂ�X�̉�
�s�s�Ɠc�ɂ̐������l��
�l�̓s���ɍ��E�����A������
�łQ������
�X�H���Ƃ̐S���J
�̍��̋�Ԃ��l�X�̋��ꏊ��
�X���s�����₷
���̉��ɐ��܂��Љ�
�I���[�u Olive �藣���Ȃ��Ɛl�Ԃ̉^��
�G���T����
�k��31�x46��54�E6 ���o35�x13��49�E0
�G���T�����̗��j�ƃI���[�u
��Ж�i�Ȃ��j�̓�
���Łu��тɖ����A�Ԃ̍炫���ڂ��v�y�n
�I���[�u�т��a������
�_���l�b�g���[�N���č\�z����
�R�~���j�P�[�V�����Ƌ���
�I���[�u�̉ԕ�����镶���̐���
�W�����ۂm��
�S���E�}�c Japanese White Pine ���̖��Ɛl�Ԃ̖��͊W���̂Ȃ��ɒz�����
�{���A���{
�k��34�x16��44�E1 ���o132�x19��10�E0
���V���g���c�b
�k��38 �x54��44�E7 ���o76�x58��08�E8
����̃��[�c��K�˂�
��{�̖��ۂ��Ɗ�����
��C�E�E�X�̊W���Ƃ̑Θb
�ӎ�
��҂��Ƃ���
�Q�l����
����
�@
�Y�ꂪ�������{�̐X�ɏo���킵���̂́A�v���������Ȃ��Ƃ��낾�����B���̎��킽���́A�����w�i�����ӂ����E�k���{���j�̃z�[���ɂ����B�ٓ����̂Ȃ��ɁA�X�����R�Əo�������̂��I
�@
�w�ɒ����܂ł킽����15�L�����������A�_�Ђ⎆���i���j���H�[�A�c�ɓ����߂����Ă��Ă����B�r�͂ς�ς�ɂȂ�A���y�R�������̂ŁA���X�ŕٓ������߂����������B�����̂Ɏ��{�����߂������������̂����A������̂͂���ȏ�̂��́\�����̈Ӗ���s�i�͂�j��Œ[�R�Ƃ����ɑ�����ꖇ�̃��~�W�̗t�������B
�@
���N���o�������Ƃł��A���̎��̗t���킽���͂͂�����ƋL���ɂƂǂ߂Ă���B
�@
�t�́A�ٓ��̔т̏�ɂĂ��˂��ɏ����Ă����B�R�����悤�ȐԂ��F���킽���̖ڂ��ł����A���̌`�ɓ�����Ă킽���̎v���͐X�ւƔ�B����͍��}���B���悻�X�Ƃ͉����������ꂽ����ȏꏊ�����A�����Ƃ���������̂��݂ȁA�l�G�̈ڂ낢�̂Ȃ��ɂ��̋��ꏊ�������Ă���Ƃ����i�������j�Ȃ̂��B
�@
�l�̎肪���ݏo�����Y�Ƃ̂����Ȃ��Ł\�R���N���[�g����̃v���b�g�z�[����v���X�`�b�N���ٓ̕����A�Z�p�̐�����������ԂɈ͂܂�Ă��Ă��A�X�͐��������Ƃ킽���̂Ȃ��ɔ�т���ł����B�S���w�̃z�[���ɂ��Ȃ���A�킽���̐S�Ƒ̂́A�����R�~���j�e�B�̐[�����ɕ�����Ă����B
�@
���̎��̂��Ƃ��A�Ȃ������܂ł͂�����Ɗo���Ă���̂��낤���B
�@
�ٓ����̂��̂͂������肫����̈����ȉw�قɂ����Ȃ���������ǁA���~�W�̗t���A�s�ӑł��ł킽���ɂ��ꂽ�̂́A�X�Ƃ̍��̂ӂꍇ���������B����́A���{�̐l�X�ƖX�Ƃ̓��ʂȊW����肩���Ă������̂������B���̂���܂łɂ킽���́A���w��ʂ��ē��{�̖X�Ɛl�X�Ƃ̊W���w��ł��āA���҂̌��т��������\���ɐ������o����Ă����B�킽���ɂƂ��ĕٓ����̃��~�W�̗t�́A�͂��炸���A���{�l�ƖX�Ƃ̊W���̃V���{���ɂȂ����̂������B
�@
�������A���{�Ől���X�сA���邢�͊��p��������͈�l�ł͂Ȃ��B���̍��͕��������R�����L���ʼn��[���B�X�Ɛl�X�Ƃ̊W���y�n�⎞��ɉ����Ă��܂��܂Ȍ`���Ƃ�B���̑��l�ȏK���̂Ȃ��ɁA�k�A�����J�������Ă����ώ@�҂ł���킽�����A�Ƃ�킯�S�䂩�ꂽ���̂�����������B
�킽���̒m���������Ă��邱�ƂƊO���l�ł���䂦�ɁA������������ۂ͂��Ƃ�����Ό���Ă��邩������Ȃ����A�����̕s�[���ȂƂ���͑��X���邾�낤�B���̖K��҂ł����Ȃ��g�Ƃ��āA����Ă����Ƃ���Ό����ɔ��Ȃ������B
�@
���{�ł́A�G�߂̈ڂ�ς��������A�́i�����j����K�킵�����ɔ��B���Ă���B���������c�݂̒��S�ɁA���X�ɂ��Ď����݂�B�F��ς���t�A�t�Ɍ����̉�A�炫�ւ�A�₪�ĎU������ԁB�����G�߂����ł镗�K�́A�����ƕ��L�����ۂ�����肱�݁A�Ⴆ�Γ���������Ώ��ɂ܂Ŗڂ���������B��N�s���邱�������Ղ��V���́A�n���̌��]�����i���Ƃفj���ł���̂��B�����Ă��������V����K�����A�����̎��R���̋��X�i���݂��݁j�ɂ܂Ō܊����L���邱�Ƃ��\�ɂ��A�̋��̒n�Ƃ킽�������Ƃ����т���B
�@
���{�ȊO�́A���ɍH�Ɖ��̐i���X�ł́A��������Ď��R���Ɏv����y�i�́j����@��ȂǂقƂ�ǂȂ��܂܂Ɉ�N���I��邱�Ƃ��߂��炵���Ȃ��B���{�̓`���́A�킽�������������̃R�~���j�e�B�̈�����邱�Ƃ��A���̖������ŁA�ґ�Ɏv���N�������Ă����̂��B
�@
�l�Ԃ����R�ɋA�����邱�Ƃ̏́A�M�ɂ܂��K���ɂ����X������B����_�Ђ̂܂������͂ރX�M��C�`���E�B����X�ɂ̓J�~���h��B��_�����̐X�Ƃ������O�Ŗ��炩�ɐ��i�����j�߂��邱�Ƃ�����A���t����s�v�ȏꍇ������B���������������肪����̂́A�l���A�l�Ԃ���łȂ��A�����͂��߂Ƃ���A�������܂��E�ɖ��߂��܂�Ă��邱�Ƃւ̎��o�����邩�炱�����B�����̎Љ�Ɍ�����悤�ȁA�u���R�v�Ɓu�l�ԁv�Ƃ̉�R�����ʂ́A���{�Љ�ɂ͂܂������Ȃ����A�������Ƃ��Ă����������܂��Ȃ��̂̂悤���B
�@
�`���I�ȐM�K���ƌ���I�Ȑ��Ԋw�̒m���Ƃ́A�����ł͂������ĂЂƂɎ��ʂ��Ă����B�܂�A�l�͂��傫�ȃR�~���j�e�B�ɑ����Ă���A�l�ԂƐl�ԈȊO�̐����̋��E�͌����Đ�ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���݂̖ڂɂ͌����Ȃ����������E�����C�Â���̂��A�ƁB
�@
�������A������Ƃ����Ă���ȊO�̐M�K���̑��l�Ȃ������A�Ȋw�Ə@���Ƃ̋��E�ɖڂ��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������{�ɂ����āA�M�̐��E���X��X�Ɛ[�����т��Ă��邱�Ƃ͂�͂虉�ځi�������j���ׂ����B�y�n�̐N�H��C��ϓ��A�ߏ�Ȕ��̂ƁA�X�������̓��ɒ��ʂ��Ă��錻�݁A�l�Ԃ̐l�Ԃ��鏊�ȁi�䂦��j�́A���̐����Ƃ̊W���̂Ȃ��ɂ�������̂��Ƃ����^�����A�M�̌��ꂩ�甭�M����Â��邱�Ƃ͉��ɂ��܂��ďd�v�����炾�B
�@
�킽���������A�����Ă���Ӌ`���A���l��T����́A�@�������ł͂Ȃ��B�|�p���܂������Ă����B
�G����A���y���A���w���A�����ĉ��|��ʂ��āA�킽�������͕��G�Ȃ邱�̐��̈Ӗ���T�����߁A���߂Ċ�������A���邢�͖₨���Ƃ���B�|�p�̌`����Ă킽�������͔������߁A�Ȃ����^���̉��l���_�Ԍ���B
�@
���{�ɂ����ẮA���i�̂Ȃ��́A�Ƃ�킯�X�̌`��������A�|�p�̊�Ղɂ���B�X��X�̗l����A���ꂪ�`���Ă������̂�q���Ɏ�肱�����Ƃ���|�p�̂�����͑��̎Љ�ł͂��܂茩���Ȃ��B���{�ȊO�̎Љ�ł͌|�p�Ƃ̂܂Ȃ����͂ނ�����Ɍ������A������ӎ��̓��ʂ̓������Ƃ炦�悤�Ƃ��邩�炾�B���������Ӗ��ŁA���{�̌|�p�͐l�Ԃ̐��E��傫�Ȑ����R�~���j�e�B�ƂȂ��ł����̂��B
�w�X�͉̂��x�������ɂ������āA�킽���͑����̎���K�ꂽ�B���ꂼ�ꂪ�A�傢�ɈقȂ���Ő����Ă���X���B��������̗��̂��߂�����Ƃ��āA�킽���͓��{�̃S���E�}�c��I�B���悻400�N�̎�����d�˂��~�͂��B�킽�������̔��������Ŗ{�����ڂ��Ǝv�����̂́A���{�l�̖X�Ƃ̊W���A���ׂĂ̐l�X�Ɂ\���܂ꂽ�����ǂ��ł��邩�ɂ�����炸�\�A�厖�Ȃ��Ƃ������Ă����ƍl�������炾�B
�@
���܁A���E���ŐX�����Ă��鎞�ゾ���炱���A�킽�������ɂ͖X�ƌ݂��Ɍb�ݍ����Ȃ��琶���邽�߂̃��B�W�������K�v���B���̂悤�Ȑ������̎�{�͐��E���ɂ���B�A�}�]���̐l�X�͔ނ�̐X��[���m������A�����J�Ō���Ă���B�����̃I���[�u�_�Ƃ́A�`�������V������@���������B�����ă}���n�b�^���̏Z���ƊX�H���̊Ԃɂ����A�݂��Ɏx�������W�����݂���B
�@
���{�ł킽���́A�Ƃ�킯���h�ɒl����A����ł��Ċ��тƂ������ɖ������l�ƖX�Ƃ̊W�ɑ��������B���{�łӂꂽ�l�ƖX�Ƃ̂��܂��܂��J�ɂ́A�����鐶���ɒʂ���^�����������\�킽�������͌����Ă��ɑ��݂���̂ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA����^�������Ȃ��琶���Ă���̂��Ƃ����^�����B
2019�N1��18��
�f���B�b�h�E�W���[�W�E�n�X�P��
�@
�z�����X�̎���̃M���V���l�ɂƂ��āA�N���C�I�X�\�����\�͉̂ɂ���č��ꂽ�B��C�̐k���ɁA�l���̓x�ʂƋL���Ƃ��悹����B���������Ď����X���邱�Ƃ͂��Ȃ킿�A�i���c�閼����m�邱�Ƃ������B
�@
�킽���͐��Ԃ̃N���C�I�X��T���āA�X�Ɏ������B�p�Y�͌�����Ȃ������B���̂܂��ŗ��j�������悤�ȒP�Ƃ̑��݂͂ЂƂƂ��ĂȂ������B���̑���ɁA�X�̐��U�͔ނ�̉̂ɂ͂�����Ǝ�����A�����̘A���A�Ԃ̖ڂ̂悤�ɍL����W��������Ă��ꂽ�B�킽�������l�ނ��܂��A���̌��̂����ɂ���\�����Ƃ��āA�q�g�̌`���Ƃ������E�Ƃ��āB
�@
�����X���邱�Ƃ͂�����A���������́A�����Ď����̐e�������̐������Ƃł�����B
�@
���̖{�ł́A�ЂƂЂƂ̏͂ł��ꂼ�����̎���̉̂ɕ��������Ă���B�����I���݂Ƃ��Ẳ��̓�����A���������̂ɂ��镨��A�����Ă킽�������́A�̂�S�⓪������ɑ��Ď��������ɔ�₳��Ă���B�̖̂{���̑唼�́A�\�ʓI�ȉ��̋����̉��ɂ���B
�@
����䂦�Ɏ����X���邱�Ƃ́A���f����n�̔��ɂ��āA���̉��ʼnQ�����������Ƃł�����B
�@
�킽���́A�����̑傫���قȂ�y�n�ɐ�����X��T�����B
�@
��ꕔ�ɂ́A�l�ԂƂ͉����u�����ĕ�炵�Ă��邩�Ɍ�����X�̕��ꂪ�W�߂��Ă���B�Ƃ��낪���������X�Ƃ킽�������̐��U���A�ߋ������Ė����ɂ킽���āA���ꂠ���Ă���̂��B���������W���̂����ɂ́A�����̋N���ɕC�G���邭�炢�Â����̂�����B���邢�́A�Â��W�����Y�Ƃɂ���ĐV���Ɍ@��N�����ꂽ���̂�����B
���Ȃ镔�ł́A�����ċv�����X�̖��c�A����ؒY���@��o�����B�����̌ØV�����́A������n���̕���̈ꗃ��`���A�����炭�͖����ւ̏ؐl�ƂȂ�B
��O�̕��ł́A�s���c���ɐ��i���j���X�ɒ��ڂ����B�����ł͐l�Ԃ��D�ʂɂ���A���R�͒��ق��A�����~�߂Ă��邩�Ɍ�����B����ł����������ɂ�鐶���̊W���͂�������̂ɂ��݂킽���Ă���̂ł���B
�@
������̏ꏊ�ł��A�X�̉̂͊W���̂��킢���琶�܂�Ă����B��{��{�̖X�����ꂼ��Ɨ����Ă��т��Ă���悤�Ɍ����Ă��A�X�̖��̉c�݂́A���̂悤�Ɍ��q�_�I�Ȃ�������𗠐��Ă���B�����݂͂�ȁ\�X���A�l�Ԃ��A�����A�����A�o�N�e���A�������\���ł����ĂЂƂȂ̂��B�����́A�݂����݂����܂������l�b�g���[�N���B���̐����l�b�g���[�N�́A�����Ď��߂ɖ��������a�̗��z���ł͂Ȃ��B
�ނ��낻���́A���Ԃ���̗v���Ɛi���̗v�������߂������A����������Փ˂����肵�Ȃ���܂荇�������o���Ă�����Ȃ̂��B���̂悤�ȓw�͂̉ʂĂɉ��X�ɂ��Đ������т�̂́A�ق���苭���ēƗ����̍����̂ł͂Ȃ��A�W���̂Ȃ��Ɏ���n�����߂�҂������B
�@
�����̓l�b�g���[�N�Ȃ̂ŁA�l�Ԃ������番�����Ċu�₳�ꂽ�u���R�v��u���v�Ȃ���̂͑��݂��Ȃ��B�킽�������l�Ԃ��܂����������̂̈ꕔ���ŁA�u�ނ�v�ƂƂ��ɊW�����Ȃ��Ă���B
���������Đl�Ύ��R�Ƃ����A���m�N�w�̒��j�ɂ���_�́A�����w����݂�Ό����B�����́A�S�X�y����搂���A�u�Б������̐���f�r�����m��ʗ��|�l�v[�F19���I�����납��`������Ă���S�X�y��]�ł͂Ȃ��B�����āA�E�B���A���E���[�Y���[�X�̝R��̗w�����ݏo�����ǐ₵���������ł��Ȃ��B������킽�������́A���R�������o����č��d�Ƃ������́u�������܂�v�ɗ����A�u�����̗킵�����́v���䂪�߂���͂��Ȃ�[�F�u�������܂�v�̓��[�Y���[�X�̎�'A Poet! He Hath Put his Heart to School'�A�u�����̗킵�����́v�u�Ȋw�ƌ|�p�v��'The Tables Tured'�̈��]�B�킽�������̓��̂Ɛ��_�A�u�Ȋw�ƌ|�p�v�́A����܂ł������Ƃ����ł������悤�ɁA���R�ɂ��čr�X�����̂ł���B
�@
�킽�������͐����̉̂̊O�ւ͓��ݏo���Ȃ��B���̉̂������킽������������Ă���B���ꂪ�킽�������̖{�����B
�@
������킽�������́A�A�����Ă���Ƃ������Ƃ��s�������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�l�Ԃ̊��������܂��܂Ȍ`�ŁA���E�e�n�̐����̃l�b�g���[�N�����茸�炵�A�Ȃ��Ȃ����A�藣���Ă��邢�܁A�Ȃ��̂��ƁA�ً}�̉ۑ肾�B�X�Ƃ����A���R�E�̂Ȃ���̐��Ɏ����X���邱�Ƃ́A���Ȃ킿�A�����ɂ��ǂ����^���A���Ԃ������炵�A���������Ă���W���̒��ɁA�����ɏZ�܂������w�Ԃ��Ƃł�����B
�l�́A���l�Ȑ��������Ƃ�������ɁA���̃l�b�g���[�N�Ƃ����傫�ȃR�~���j�e�B�ɑ����Ă���B
�l�ԂƐl�ԈȊO�̐����̋��E�́A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�l�ԂƐl�ԈȊO�̐����́A�ڂɂ͌����Ȃ����������E����тɖ��������̂Ƃ��Ă���\�\�\
���҂̃n�X�P�����m�͐Â��ɂ킽�������Ɍ�肩���܂��B
�A�}�]���̔M�щJ�т̋��A�j���[���[�N�E�}���n�b�^�����̊X�H���A
���P�b�g�e����ь����p���X�`�i�̒n�̃I���[�u����A���������т�400�N�̖����Ȃ��L���̖~�͂܂ŁA
���E����12�{�̖ƁA����芪�����R�̃l�b�g���[�N�A�����Đl�ԎЉ�Ƃ̊W�����A���̂悤�ȕ��͂ŕ\�������̂��{���ł��B
���҂́A�����Ύ��ԂƋ�Ԃ��ꑫ��тɒ����Ă����̂ŁA�߂܂������܂����A����͐S�n�悢�߂܂��ł��B
�������̂Ɍ��f�����悤�ȐS�����ɂȂ�ł��傤�B
���{�łւ̏����ƁA�����ɂ͂Ȃ����҂ɂ��ʐ^��L�x�ɑ}���������ʔłł��B
�{��������o�����Ɖ��y�Ɏ����X���A�L���Ȏ��Ԃ����߂������������B