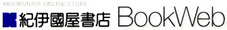斎藤公子の保育論[新版]
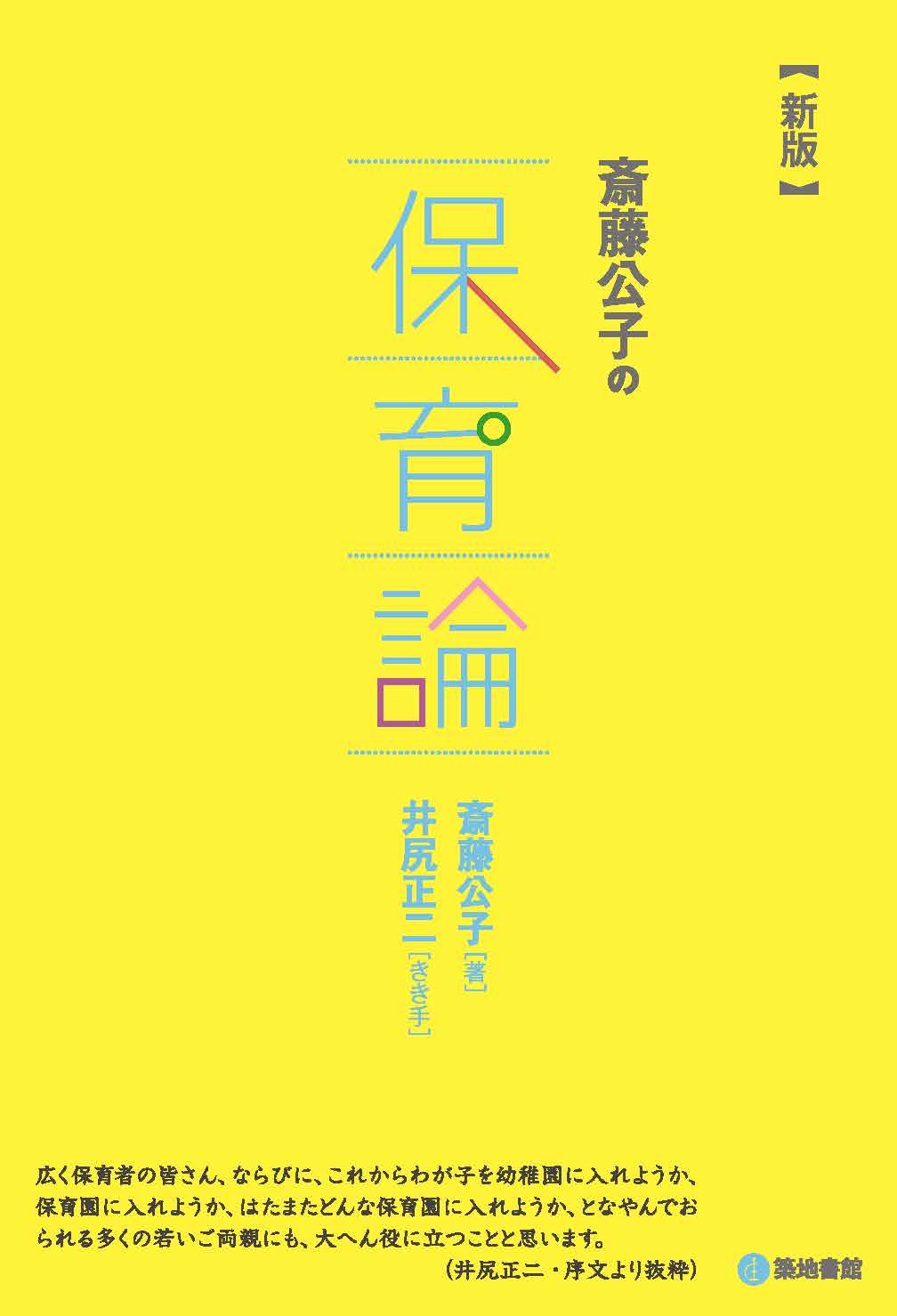
| 斎藤公子[著]+井尻正二[きき手] 1,500円+税 四六判並製 168頁 2016年12月刊行 ISBN978-4-8067-1531-3 科学と実践に基づく保育理念を語ったロングセラー、待望の復刊! 日本の保育実践に大きな影響を与えている、 「さくら・さくらんぼ保育」の原点である さくら・さくらんぼ保育園の創設者・斎藤公子が、 日本の保育園の成り立ちや、実践と科学から導きだした 0歳児保育や障がい児保育、及び保育における望ましい環境まで、 現代に通じる保育のあり方を対話形式でまとめた。 これからの保育・子育てを担う保育者に必読の一冊。 |
著者紹介
きき手紹介
目次
「本文」より抜粋