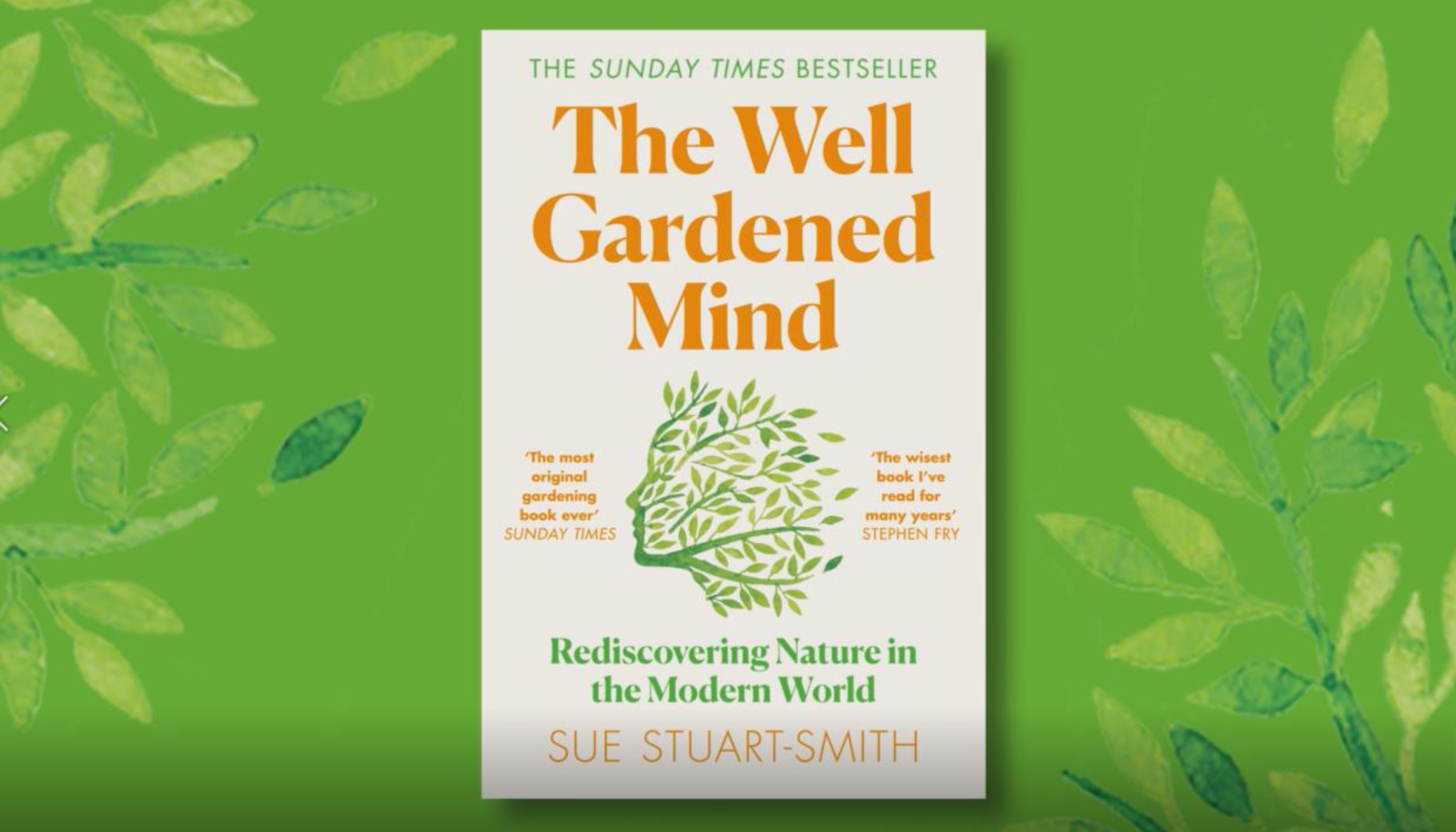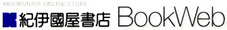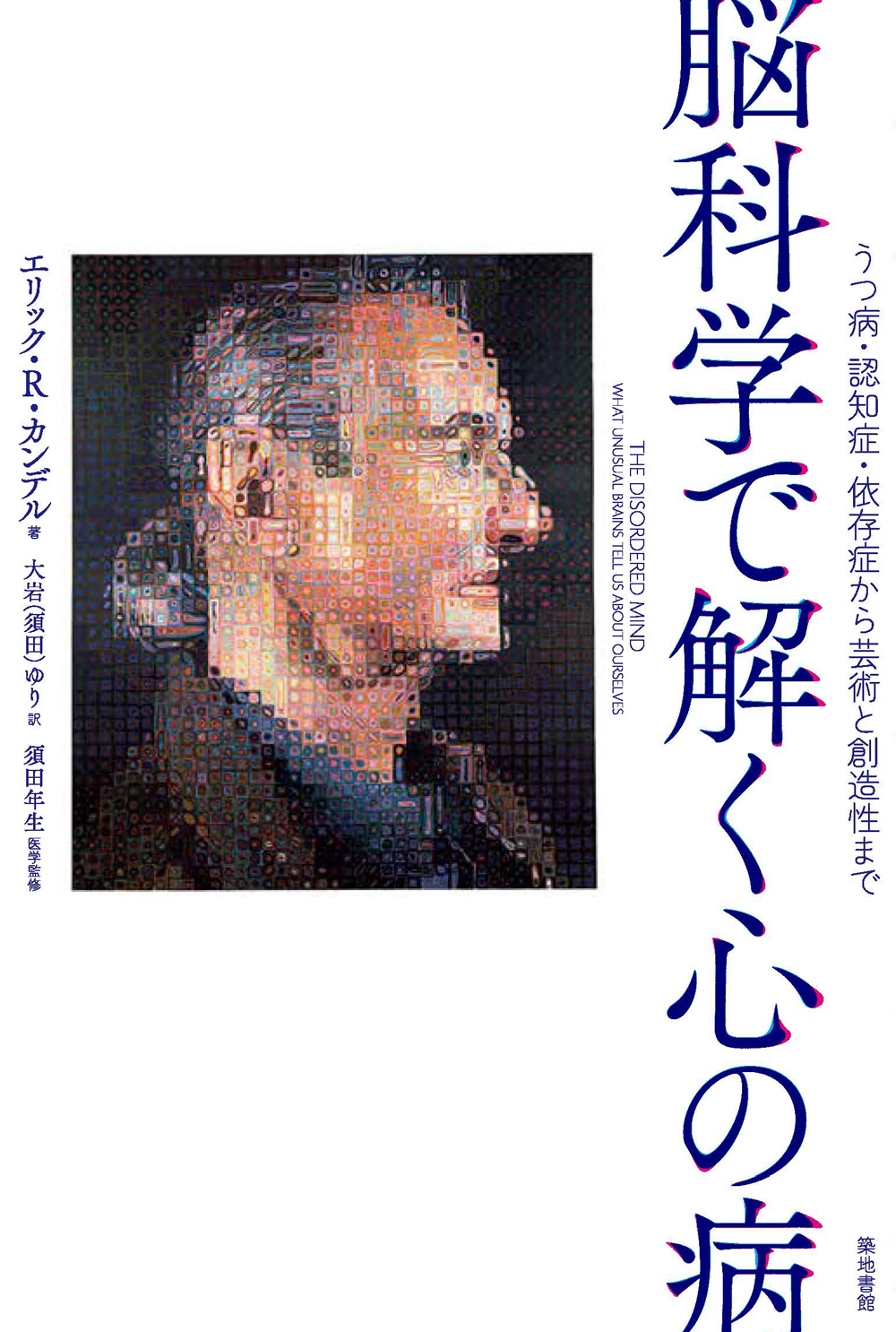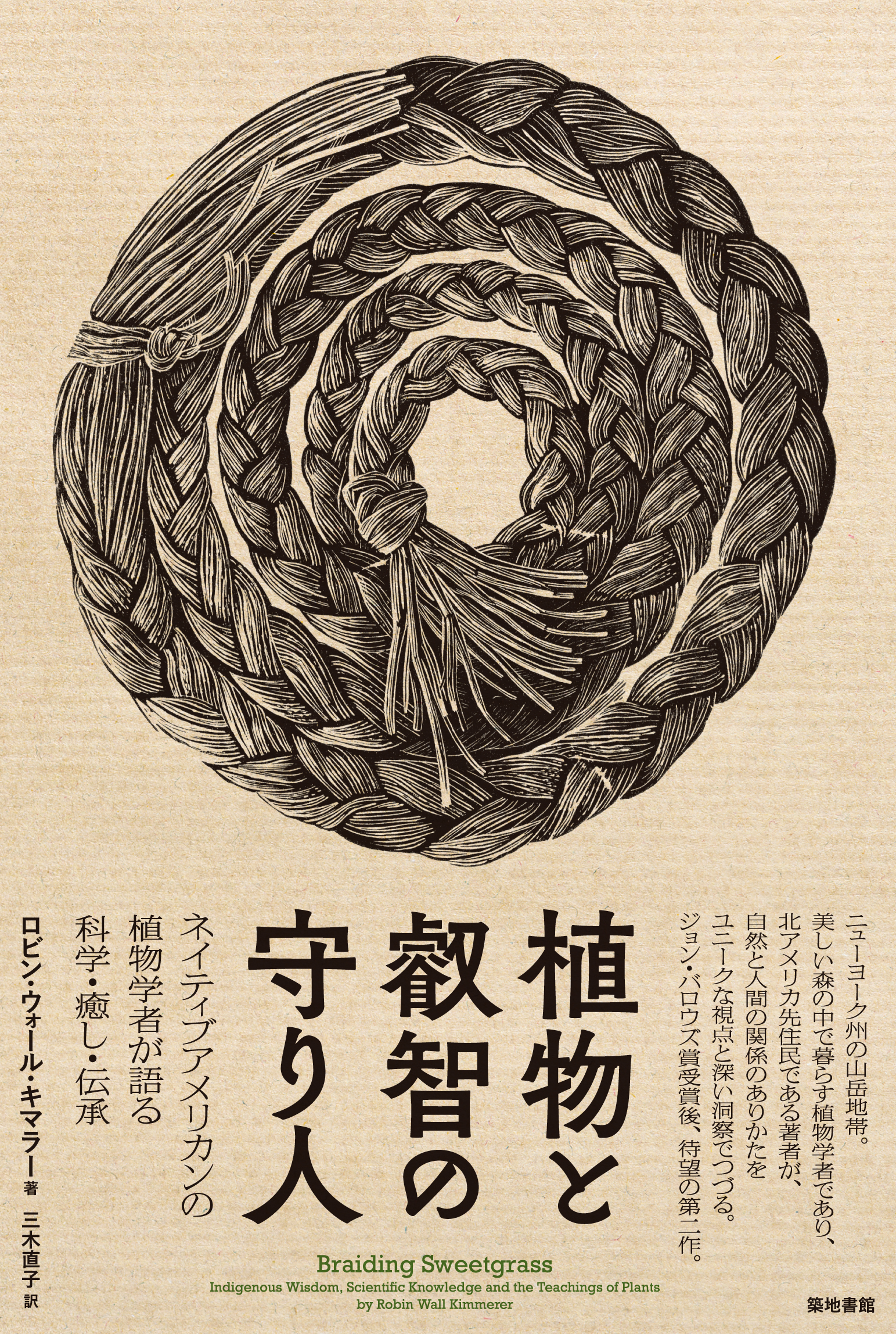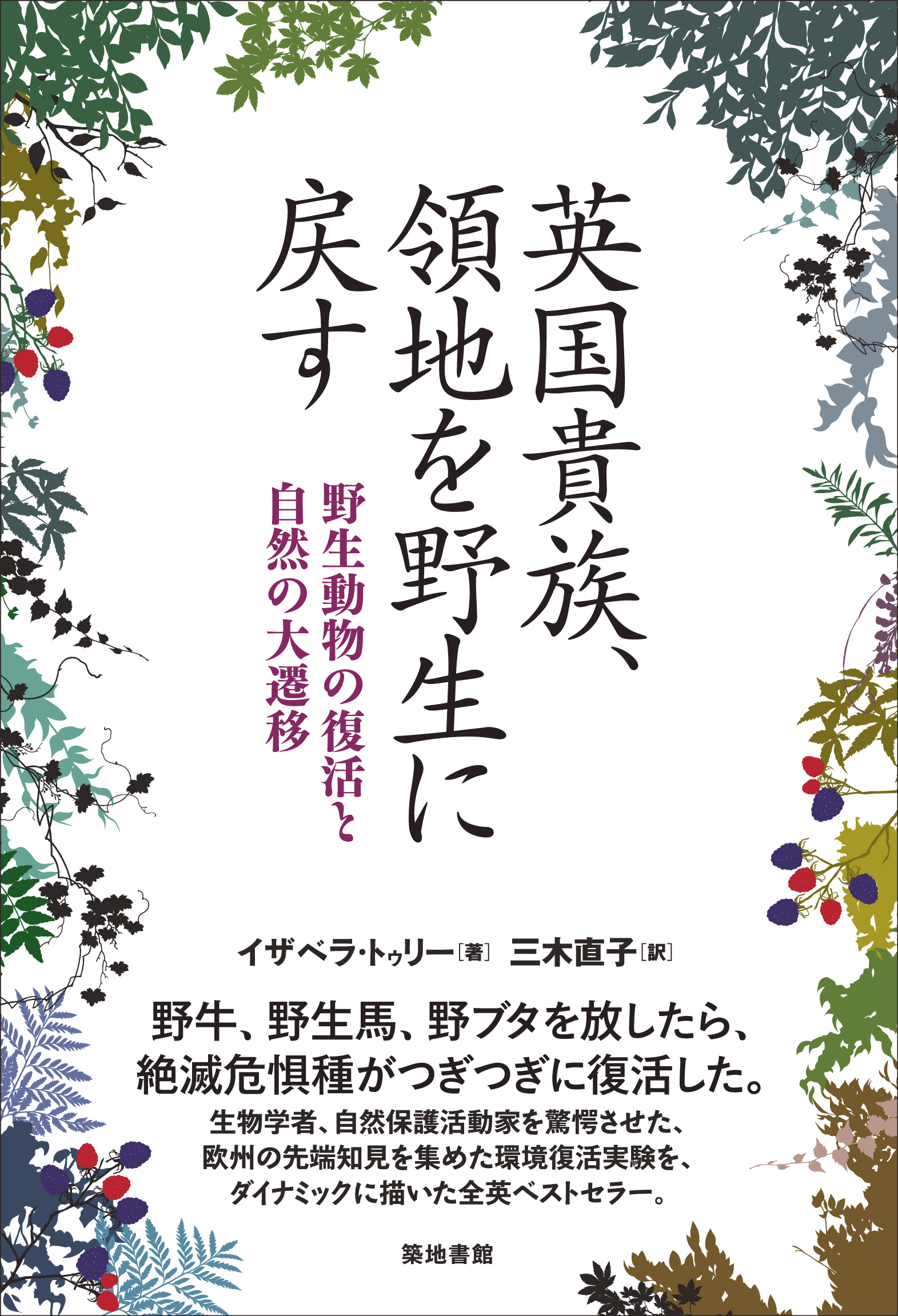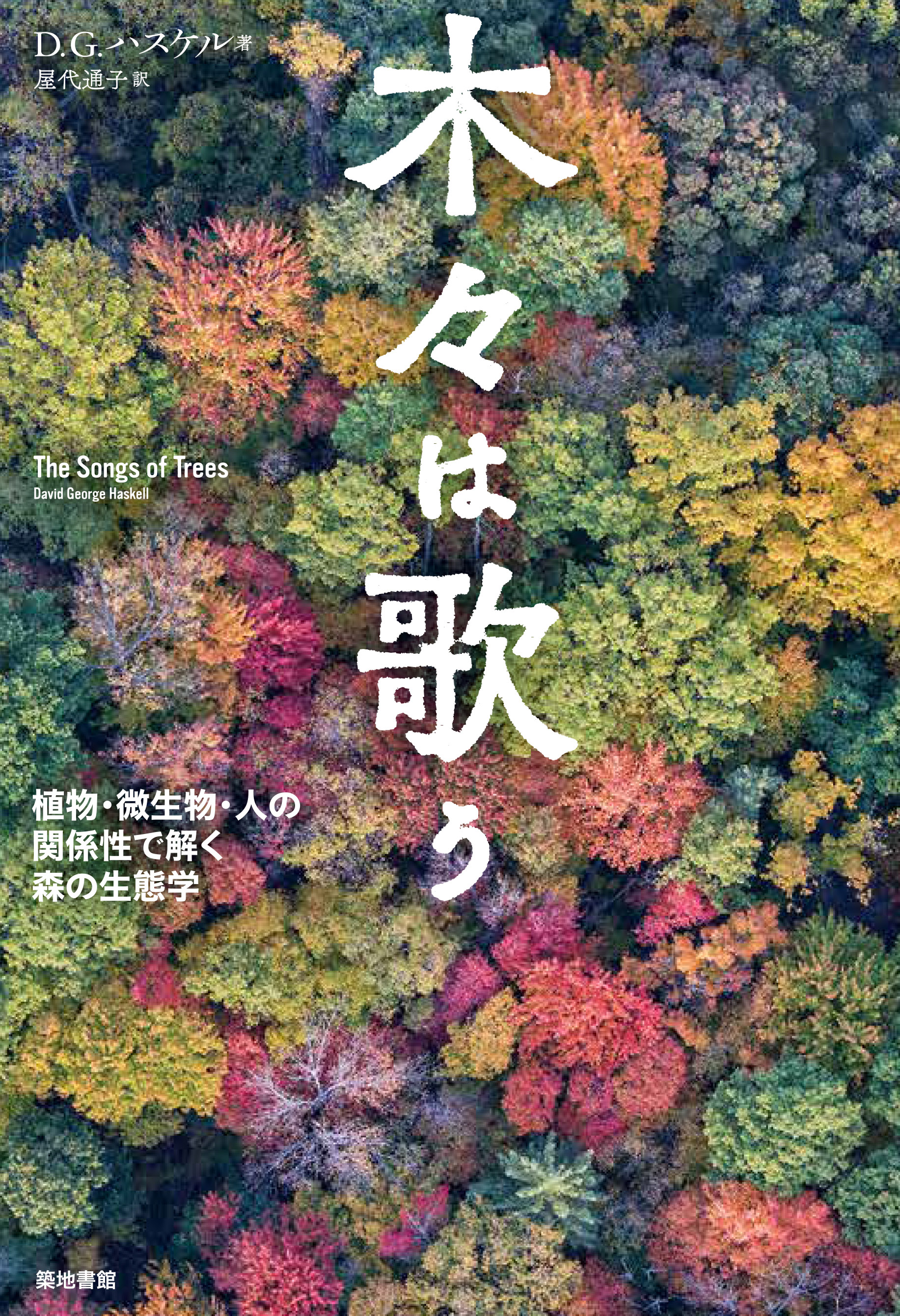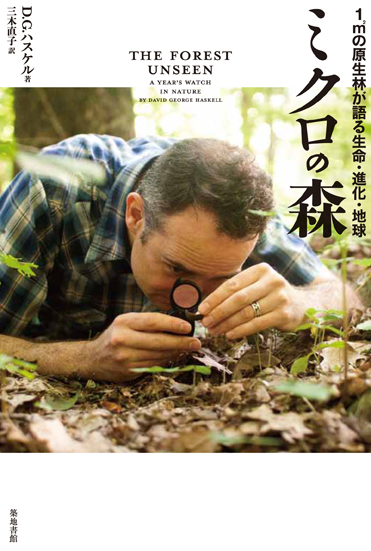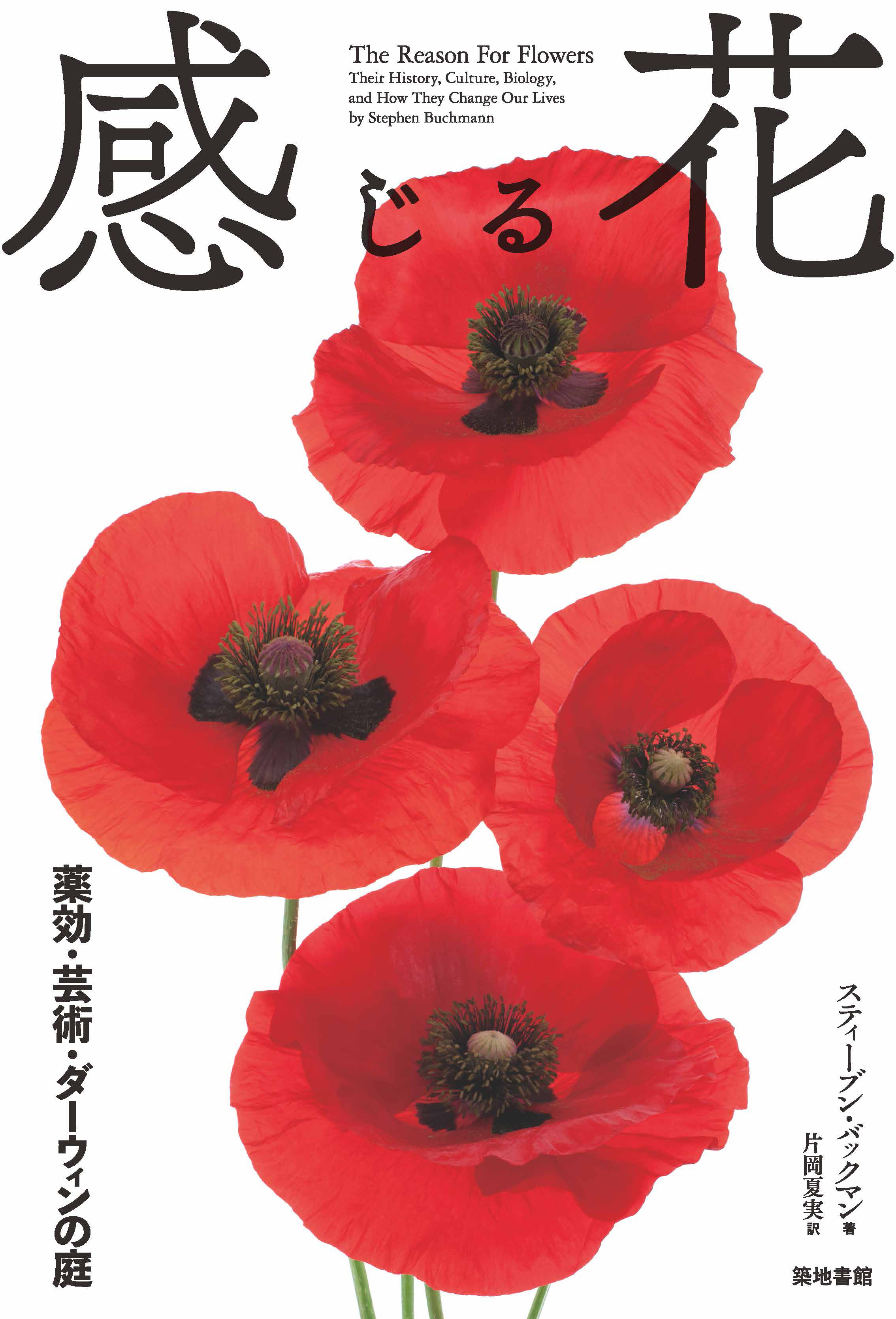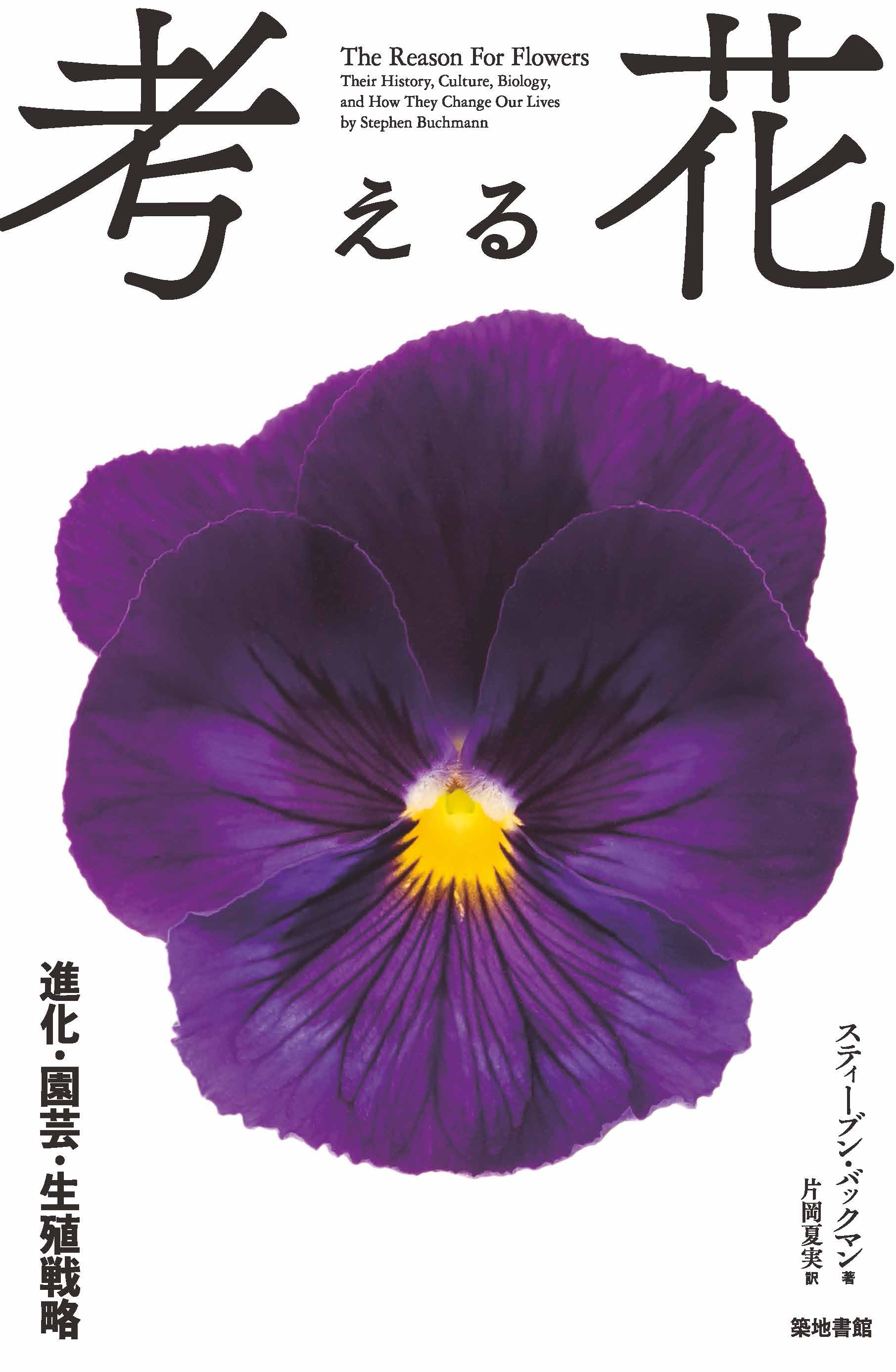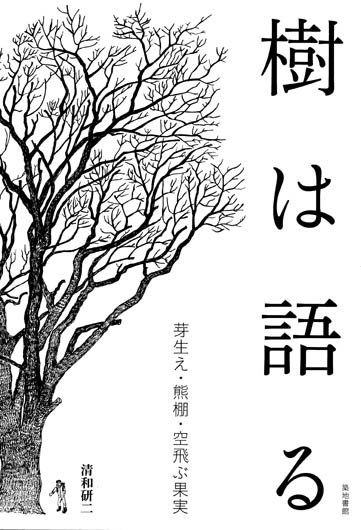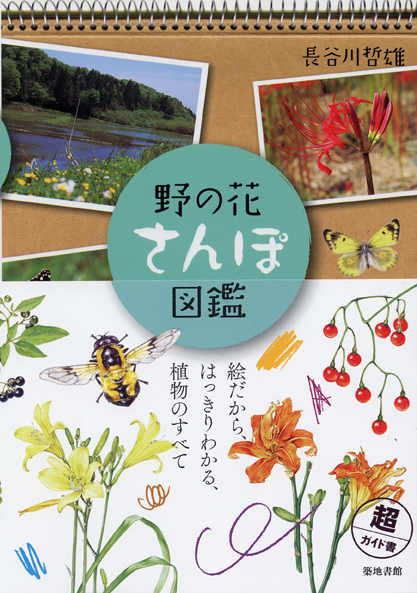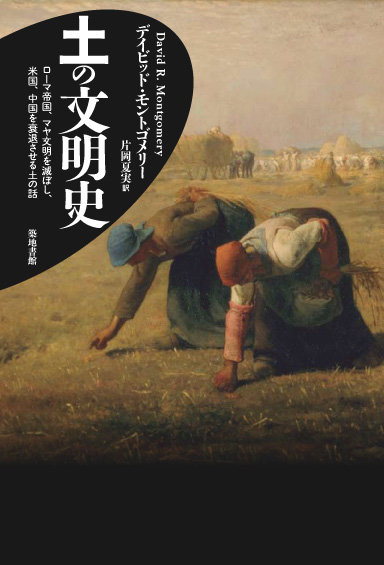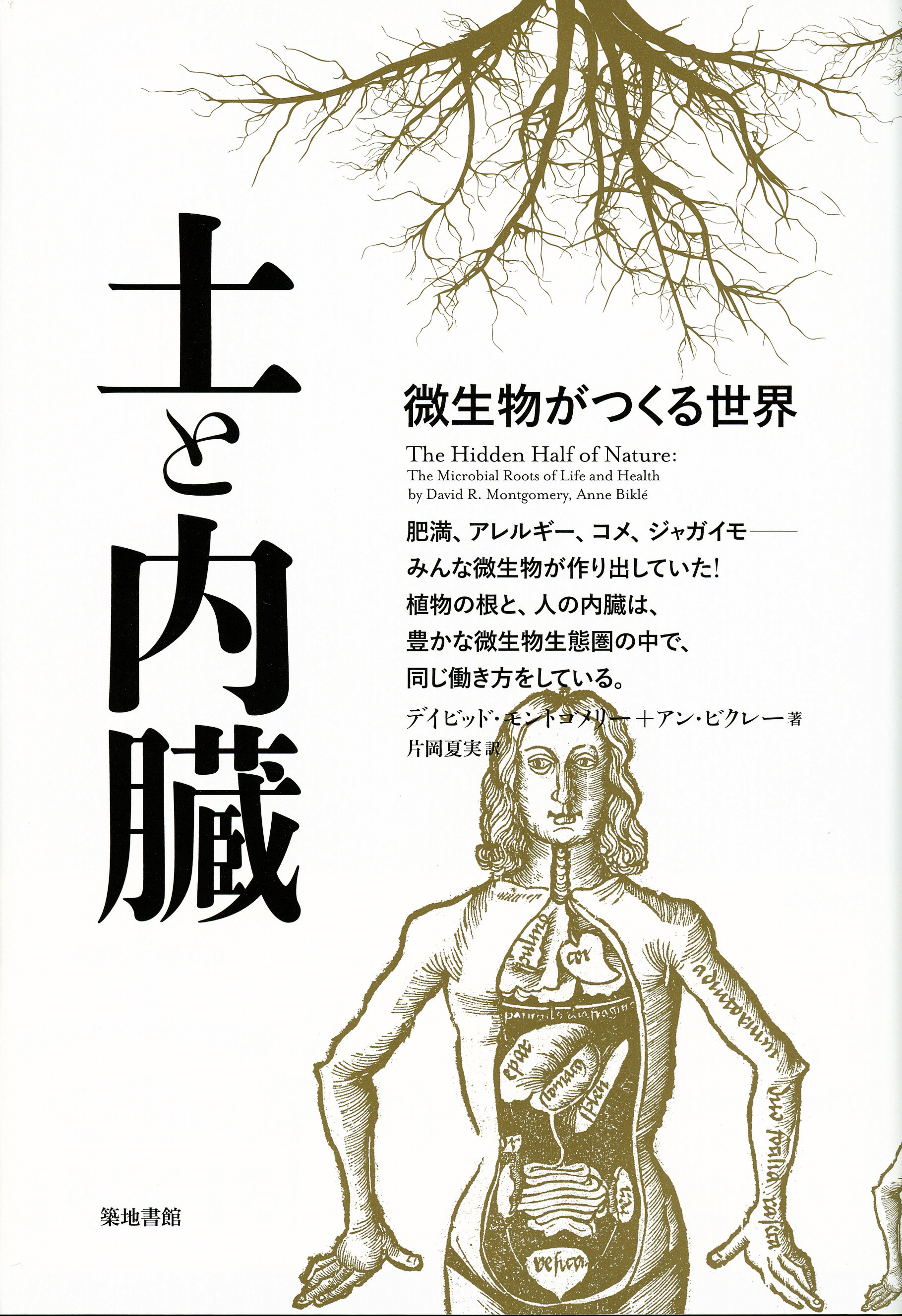庭仕事の真髄 老い・病・トラウマ・孤独を癒す庭
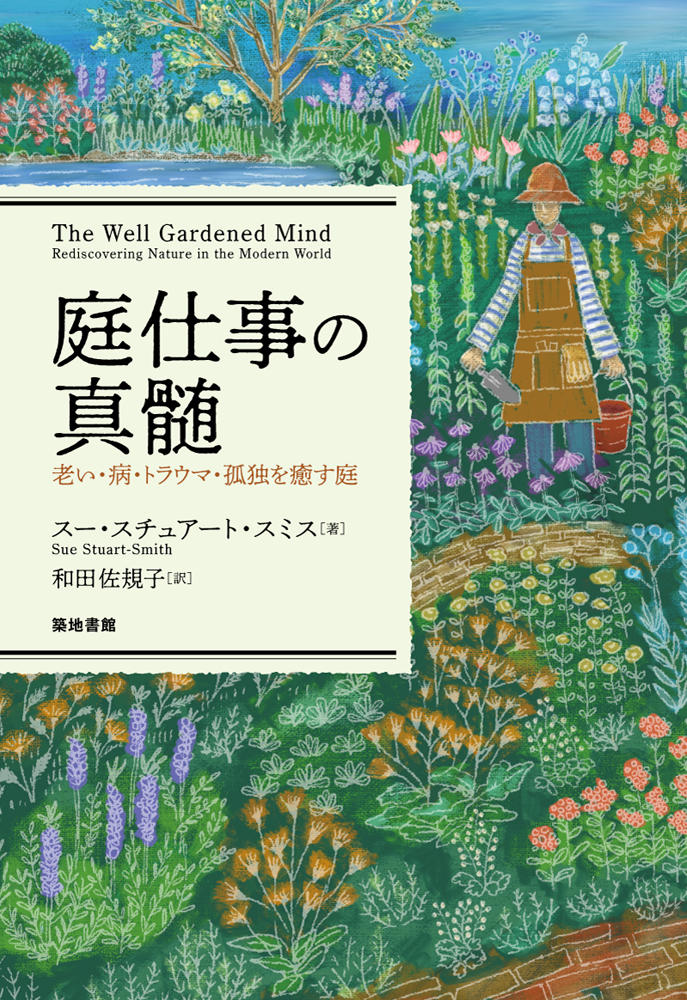
| スー・スチュアート・スミス[著] 和田佐規子[訳] 3,200円+税 四六判 416頁+カラー口絵3頁 2021年10月刊行 ISBN978-4-8067-1626-6 2022/1/16(日)読売新聞本よみうり堂欄で紹介されました。 筆者は中島隆博氏(東京大学教授・哲学者)です。 2021/12/18(土)日経新聞読書欄で紹介されました。 筆者は奥野修司氏(ノンフィクション作家)です。 「サンデータイムズ」ベストセラー タイムズ紙、オブザーバー紙「今年読むべき1冊 2020年」に選出 人はなぜ土に触れると癒されるのか。 庭仕事は人の心にどのような働きかけをするのか。 世界的ガーデンデザイナーを夫にもつ精神科医が、 30年前に野原に囲まれた農家を改造した家で、 夫とともに庭づくりを始めてガーデニングにめざめ、 自然と庭と人間の精神のつながりに気づく。 バビロンの空中庭園、古代エジプトの墓に収められた種の意味、 戦争中の塹壕ガーデン、ニューヨーク貧困地区のコミュニティーガーデン、 刑務所でのガーデニングの効果、病院における庭の役割。 さまざまな研究や実例をもとに、 庭仕事で自分を取り戻した人びとの物語を描いた全英ベストセラー。 ――――― [原著書評より抜粋] これまでに類を見ないガーデニングの本だ。資料あり、園芸あり、文学、歴史ありの本書は、 各章で参考文献や素晴らしい着想を示し、魂に栄養を注いでくれる。 ――サンデー・タイムズ(英国) 本書は庭を耕し、植物を育てる特別な喜びに関する人生を肯定する研究だ。 自然とガーデニングが精神の健康に与える影響を、著者が心からあふれ出る言葉で主張する。 神経科学上の研究と園芸療法を通じて症状が回復に向かった患者の記録にもとづいている。 ――ガーディアン 園芸が持っている癒しの効果を賢明で洞察力あふれる著者が雄弁に魂をこめて論じる。 今日の不安な時代に求められている良書。不調の時にどう対処するのか、 読者一人ひとりに適切な展望を示してくれている。 ――ブックリスト 科学としていまだに揺れている精神医学と、太古からあるガーデニングが魅力的に重なり合う。 ――フィナンシャル・タイムズ スチュアート・スミスは科学に裏づけされた洞察力で 自然の持っている癒しの効果を見せてくれる。楽しく読めて、心安らかになる本。 ――ウーマンズ・ワールド 心が躍る、刺激的で、非常に感動的な文章だ。著者は園芸療法の研究を通じて、 私たちがどれほど自然と深い関係にあるのかを明らかにしていく。 そして、自然と切り離されてしまうことが危険なことで、 自然からいかに多くの回復力を得ているか、活気に満ちた思いやりのある言葉で語り、 読者に土に触れようと忠告する。 ――イザベラ・トゥリー『英国貴族、領地を野生に戻す』(築地書館)著者 |